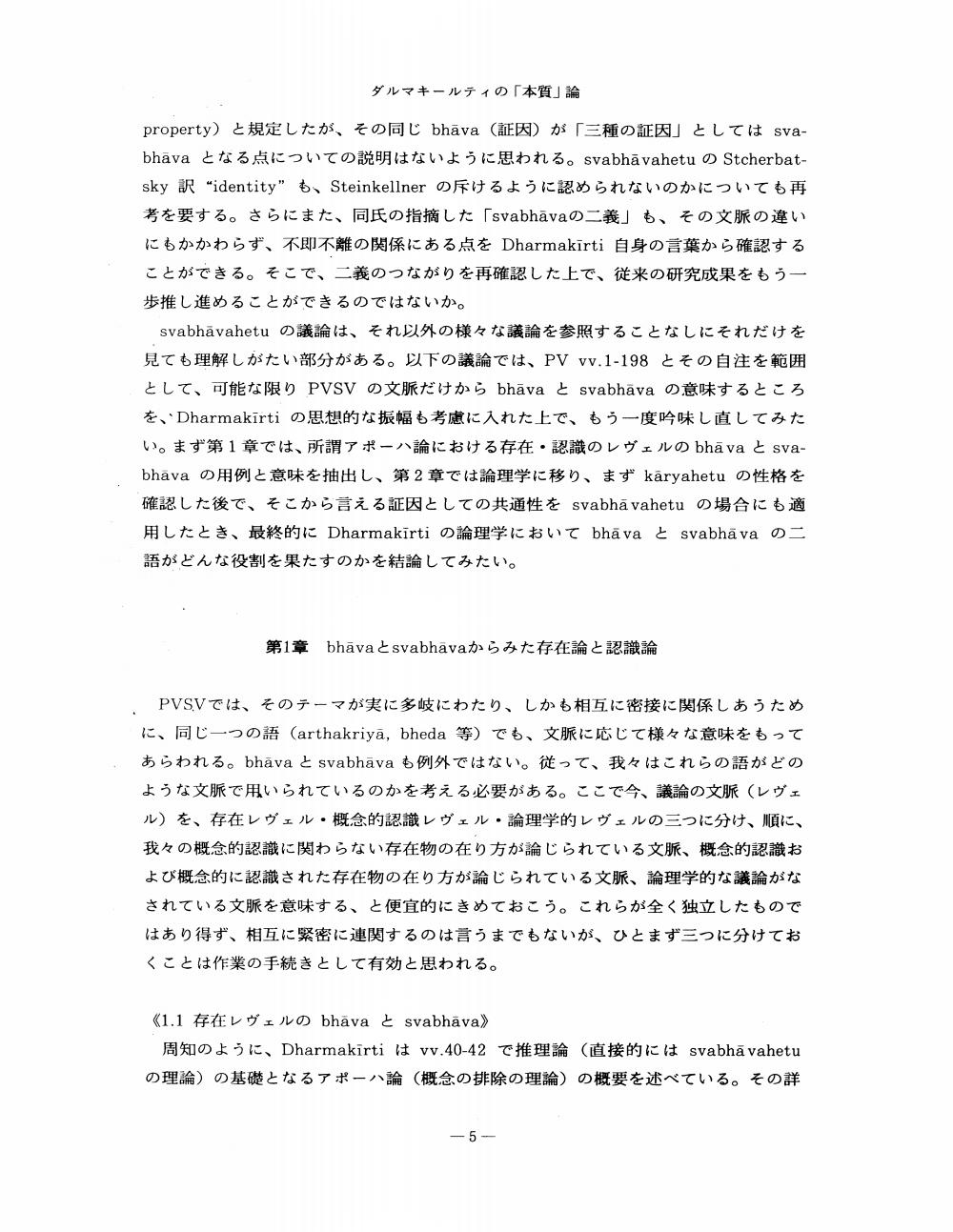Book Title: Bhava And Svabhava Author(s): Publisher: View full book textPage 6
________________ ダルマキールティの「本質」論 property)と規定したが、その同じ bhava (証因)が「三種の証因」としては svabhava となる点についての説明はないように思われる。svabhávahetu の Stcherbatsky 訳“identity" も、Steinkellner の斥けるように認められないのかについても再 にもかかわらず、不即不離の関係にある点を Dharmakirti 自身の言葉から確認する ことができる。そこで、二義のつながりを再確認した上で、従来の研究成果をもう一 歩推し進めることができるのではないか。 svabhavahetu の議論は、それ以外の様々な議論を参照することなしにそれだけを 見ても理解しがたい部分がある。以下の議論では、PVvv.1-198 とその自注を範囲 として、可能な限り PVSV の文脈だけから bhava と svabhava の意味するところ を、Dharmakirti の思想的な振幅も考慮に入れた上で、もう一度吟味し直してみた い。まず第1章では、所謂アポーハ論における存在・認識のレヴェルの bhava と svabhava の用例と意味を抽出し、第2章では論理学に移り、まず karyahetu の性格を 確認した後で、そこから言える証因としての共通性を svabhavahetu の場合にも適 用したとき、最終的に Dharmakirti の論理学において bhava と svabhava の二 語がどんな役割を果たすのかを結論してみたい。 1章 bhavaとsvabhavaからみた有 ミントンへ 心職論 . PVSVでは、そのテーマが実に多岐にわたり、しかも相互に密接に関係しあうため に、同じ一つの語(arthakriya, bheda 等)でも、文脈に応じて様々な意味をもって あらわれる。bhava と svabhava も例外ではない。従って、我々はこれらの語がどの ような文脈で用いられているのかを考える必要がある。ここで今、議論の文脈(レヴェ ル)を、存在レヴェル・概念的認識レヴェル・論理学的レヴェルの三つに分け、順に、 我々の概念的認識に関わらない存在物の在り方が論じられている文脈、概念的認識お よび概念的に認識された存在物の在り方が論じられている文脈、論理学的な議論がな されている文脈を意味する、と便宜的にきめておこう。これらが全く独立したもので はあり得ず、相互に緊密に連関するのは言うまでもないが、ひとまず三つに分けてお くことは作業の手続きとして有効と思われる。 <<1.1 存在レヴェルの bhava と svabhava>> 周知のように、Dharmakirti は vv.40-42 で推理論(直接的には svabha vahetu -5Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44