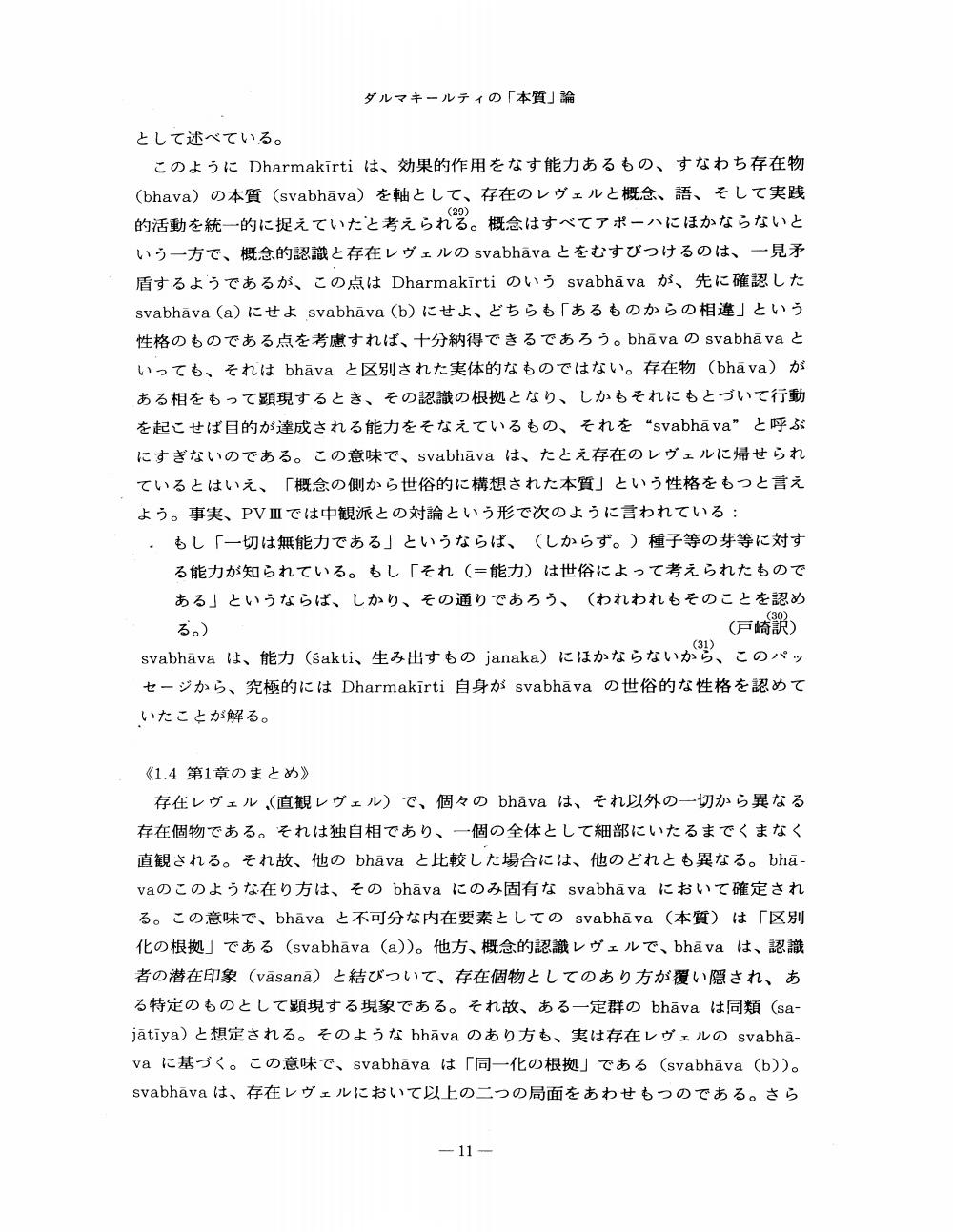Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 として述べている。 このように Dharmakirti は、効果的作用をなす能力あるもの、すなわち存在物 (bháva)の本質 (svabhava)を軸として、存在のレヴェルと概念、語、そして実践 的活動を統一的に捉えていたと考えられる。概念はすべてアポーハにほかならないと いう一方で、概念的認識と存在レヴェルの svabhava とをむすびつけるのは、一見矛 盾するようであるが、この点は Dharmakirti のいう svabhava が、先に確認した svabhava (a) にせよ svabhava (b) にせよ、どちらも「あるものからの相違」という 性格のものである点を考慮すれば、十分納得できるであろう。bhava の svabhava と いっても、それは bhava と区別された実体的なものではない。存在物(bhava) が ある相をもって顕現するとき、その認識の根拠となり、しかもそれにもとづいて行動 を起こせば目的が達成される能力をそなえているもの、それを“svabha va" と呼ぶ にすぎないのである。この意味で、svabhava は、たとえ存在のレヴェルに帰せられ ているとはいえ、「概念の側から世俗的に構想された本質」という性格をもつと言え よう。事実、PVIIでは中観派との対論という形で次のように言われている: もし「一切は無能力である」というならば、(しからず。)種子等の芽等に対す る能力が知られている。もし「それ(=能力)は世俗によって考えられたもので ある」というならば、しかり、その通りであろう、(われわれもそのことを認め (戸崎駅) svabhava は、能力(sakti、生み出すもの janaka) にほかならないから、このパッ セージから、究極的には Dharmakirti 自身が svabhava の世俗的な性格を認めて いたことが解る。 る。) <<1.4 第1章のまとめ》 存在レヴェル(直観レヴェル)で、個々の bhava は、それ以外の一切から異なる 存在個物である。それは独自相であり、一個の全体として細部にいたるまでくまなく 直観される。それ故、他の bhava と比較した場合には、他のどれとも異なる。bhavaのこのような在り方は、その bhava にのみ固有な svabhava において確定され る。この意味で、bhava と不可分な内在要素としての svabhava (本質)は「区別 化の根拠」である(svabhava (a))。他方、概念的認識レヴェルで、bhava は、認識 者の潜在印象 (vasana)と結びついて、存在個物としてのあり方が覆い隠され、あ る特定のものとして顕現する現象である。それ故、ある一定群の bhava は同類(sajatiya) と想定される。そのような bhava のあり方も、実は存在レヴェルの svabhava に基づく。この意味で、svabhava は「同一化の根拠」である(svabhava (b)). svabhava は、存在レヴェルにおいて以上の二つの局面をあわせもつのである。さら -11
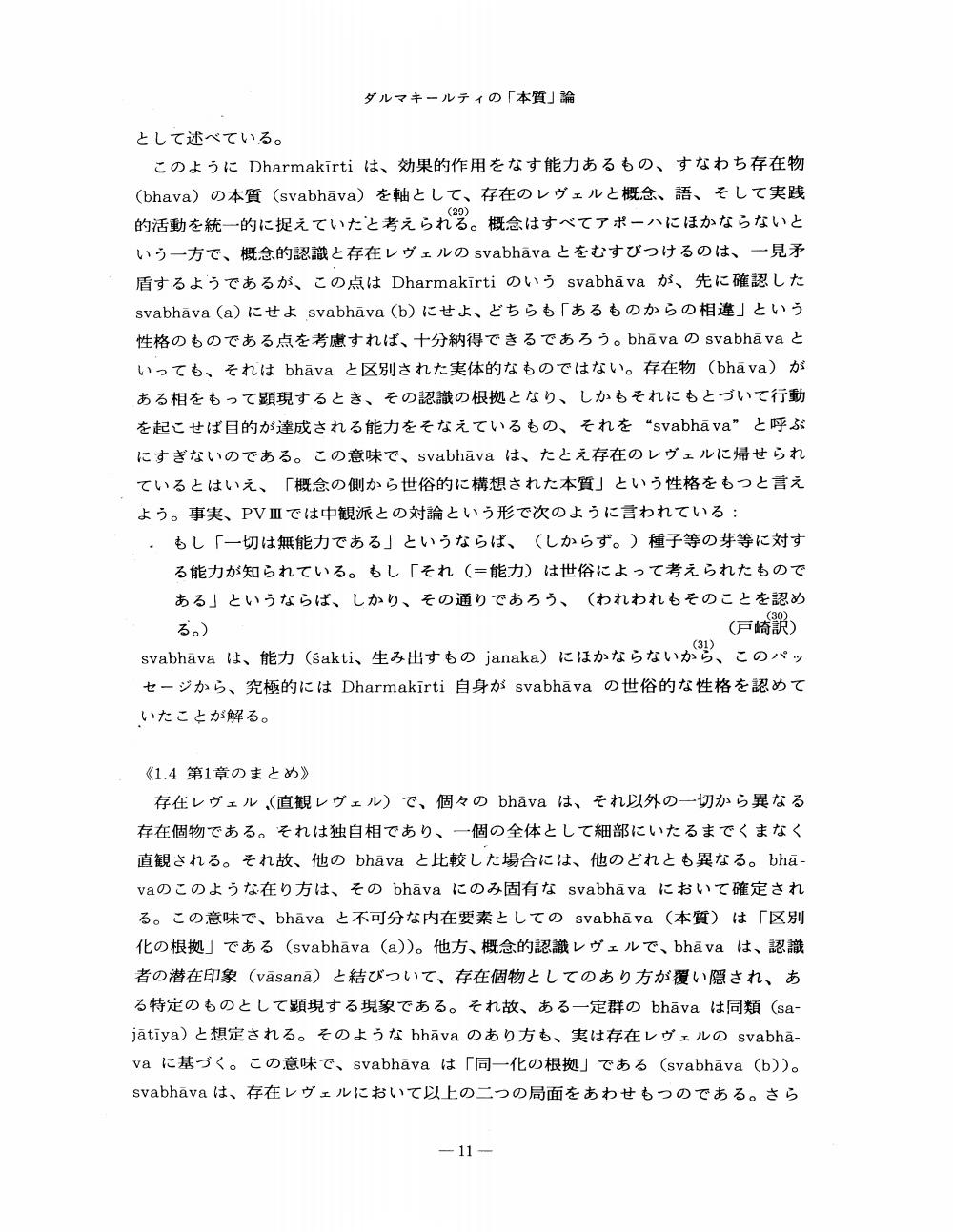
Page Navigation
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44