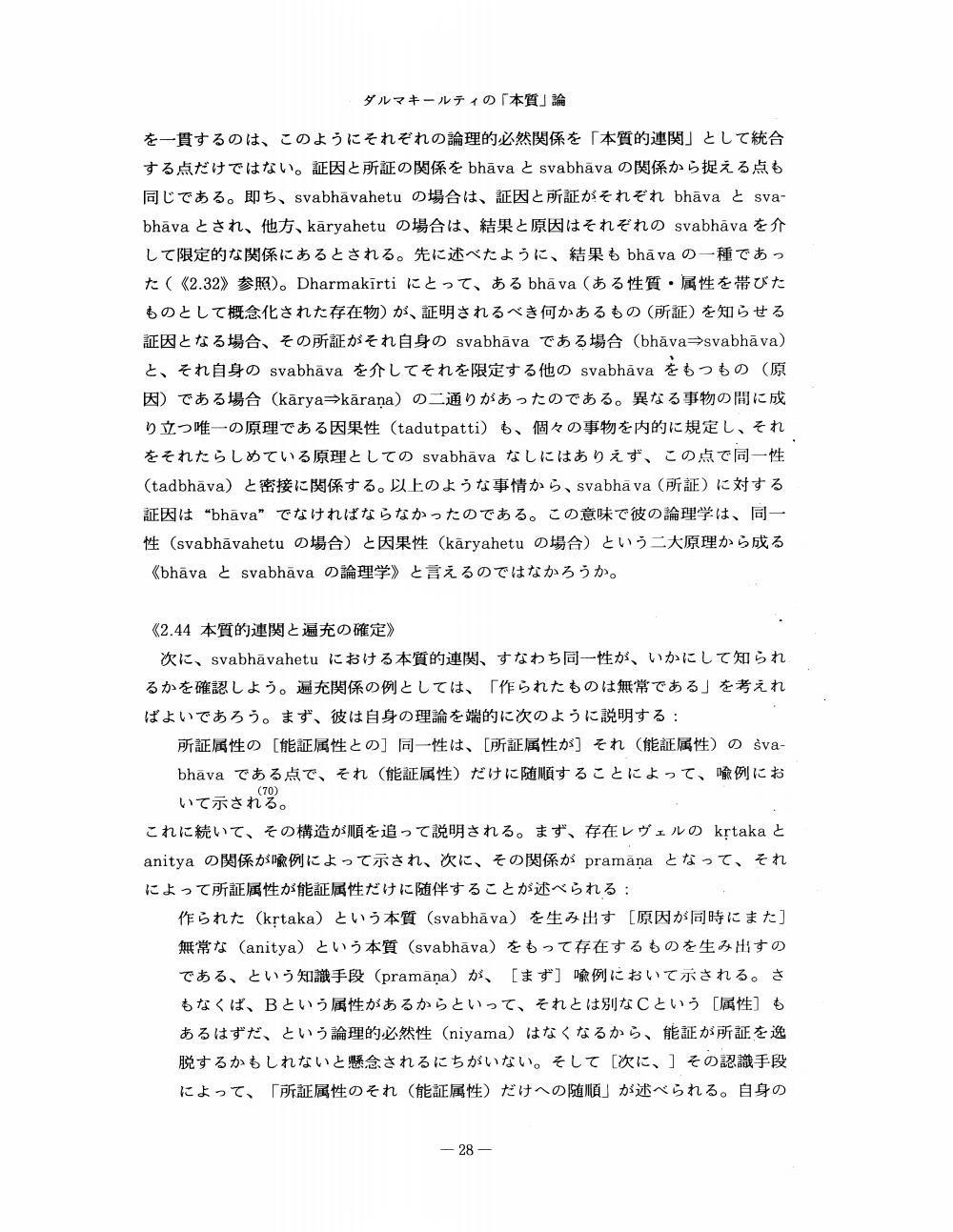Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 を一貫するのは、このようにそれぞれの論理的必然関係を「本質的連関」として統合 する点だけではない。証因と所証の関係を bhava と svabhava の関係から捉える点も 同じである。即ち、svabhavahetu の場合は、証因と所証がそれぞれ bhava と svabhava とされ、他方、karyahetu の場合は、結果と原因はそれぞれの svabhava を介 して限定的な関係にあるとされる。先に述べたように、結果も bhava の一種であっ た(《2.32》 参照)。Dharmakirti にとって、ある bhava(ある性質・属性を帯びた ものとして概念化された存在物)が、証明されるべき何かあるもの(所証)を知らせる 証因となる場合、その所証がそれ自身の svabhava である場合(bhava→svabháva) と、それ自身の svabhava を介してそれを限定する他の svabhava をもつもの(原 因)である場合 (karya-karana) の二通りがあったのである。異なる事物の間に成 り立つ唯一の原理である因果性 (tadutpatti)も、個々の事物を内的に規定し、それ をそれたらしめている原理としての svabhava なしにはありえず、この点で同一性 (tadbhava)と密接に関係する。以上のような事情から、svabhava(所証)に対する 証因は“bhava” でなければならなかったのである。この意味で彼の論理学は、同一 性(svabhavahetu の場合)と因果性 (karyahetu の場合)という二大原理から成る <<bhava と svabhava の論理学》と言えるのではなかろうか。 <<2.44 本質的連関と遍充の確定》 次に、svabhavahetu における本質的連関、すなわち同一性が、いかにして知られ るかを確認しよう。遍充関係の例としては、「作られたものは無常である」を考えれ ばよいであろう。まず、彼は自身の理論を端的に次のように説明する: 所証属性の[能証属性との]同一性は、[所証属性が]それ(能証属性) の svabhava である点で、それ(能証属性)だけに随順することによって、陰例にお いて示される。 これに続いて、その構造が順を追って説明される。まず、存在レヴェルの krtaka と anitya の関係が喩例によって示され、次に、その関係が pramana となって、それ によって所証属性が能証属性だけに随伴することが述べられる: 作られた(krtaka)という本質(svabhava) を生み出す[原因が同時にまた] 無常な(anitya)という本質 (svabhava) をもって存在するものを生み出すの である、という知識手段(pramana)が、「まず] 喩例において示される。さ もなくば、Bという属性があるからといって、それとは別なCという [属性]も あるはずだ、という論理的必然性(niyama)はなくなるから、能証が所証を逸 脱するかもしれないと懸念されるにちがいない。そして[次に、] その認識手段 によって、「所証属性のそれ(能証属性)だけへの随順」が述べられる。自身の - 28
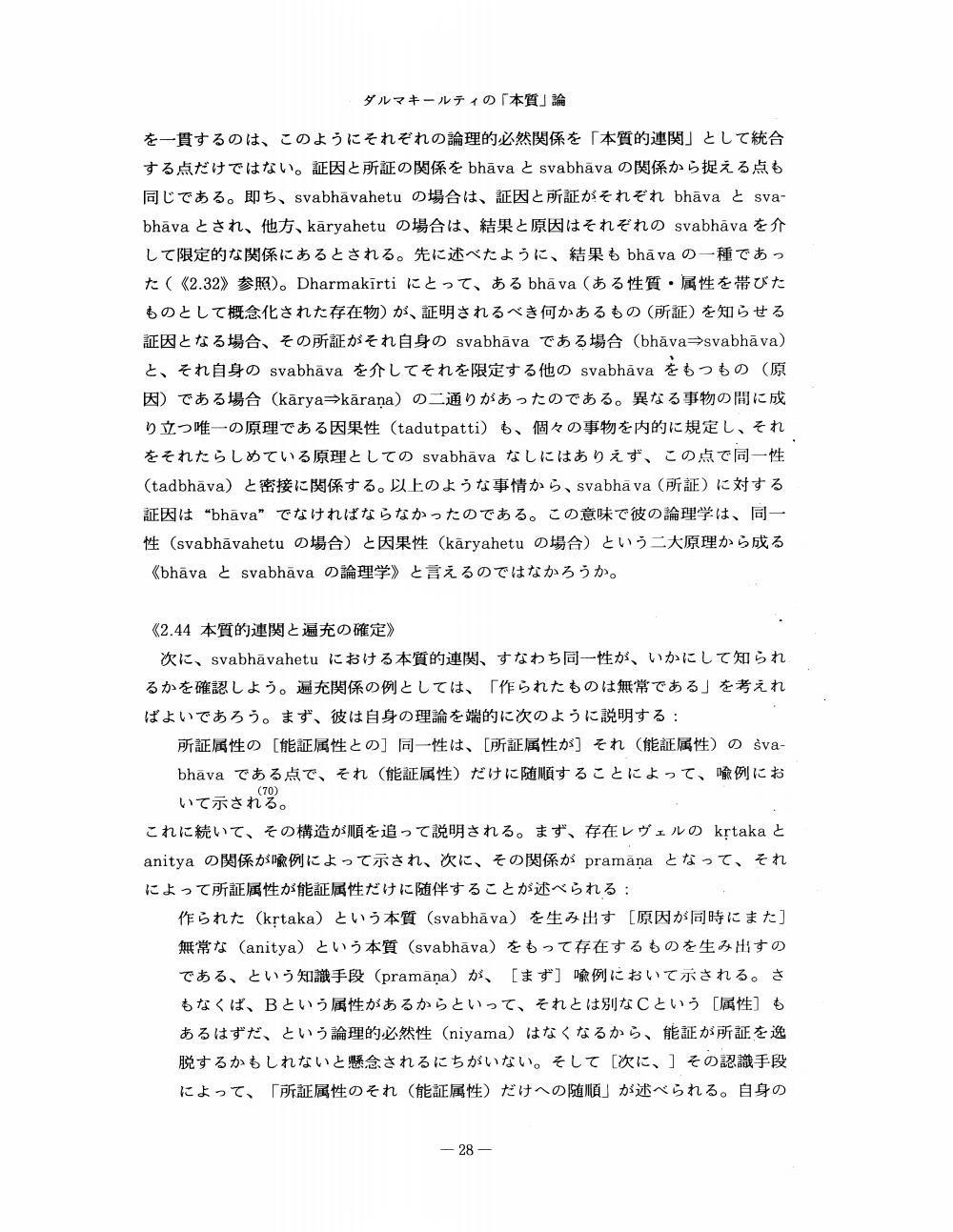
Page Navigation
1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44