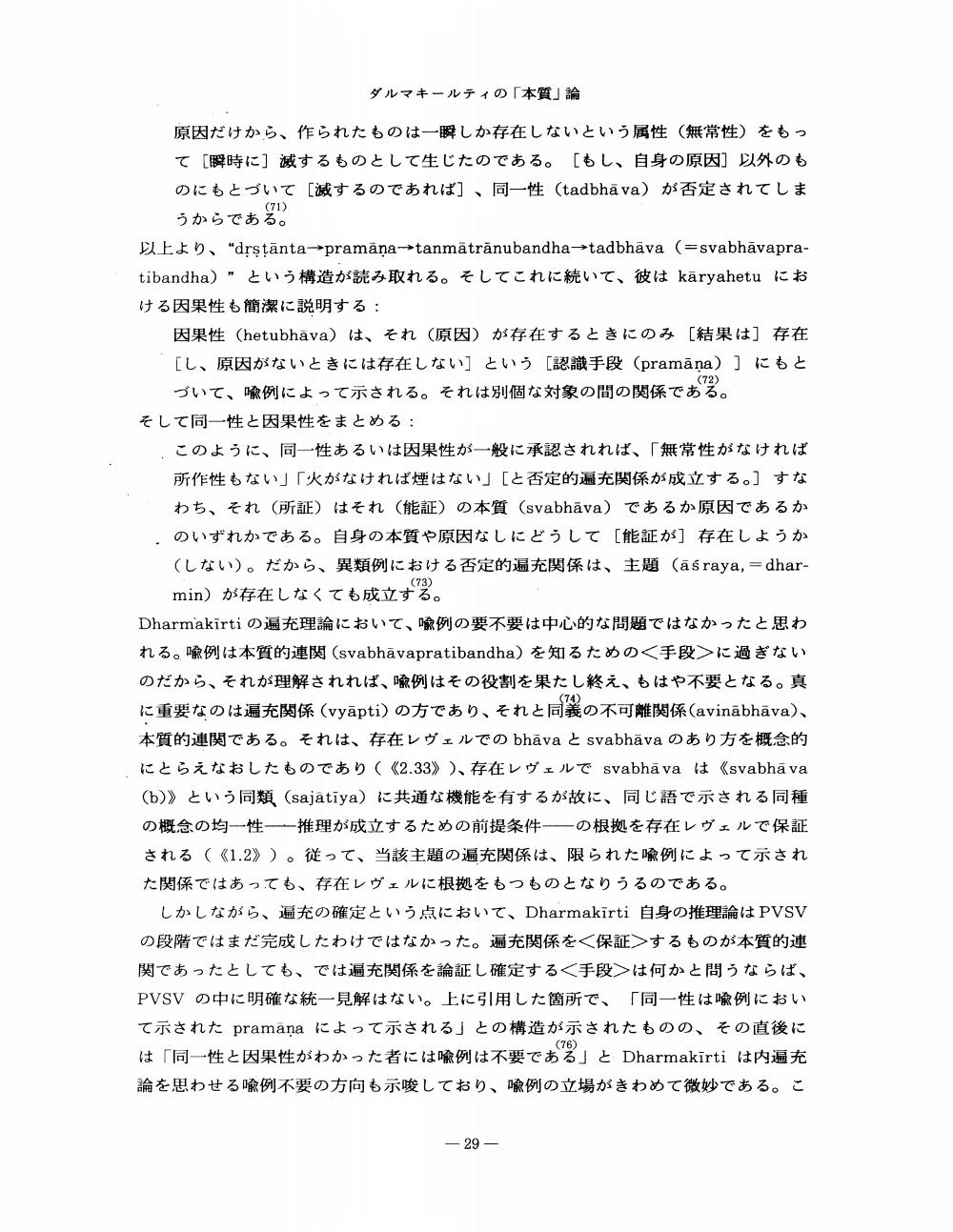Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 原因だけから、作られたものは一瞬しか存在しないという属性(無常性)をもっ て[瞬時に]滅するものとして生じたのである。[もし、自身の原因]以外のも のにもとづいて[滅するのであれば、同一性 (tadbhava) が否定されてしま うからである。 以上より、“drstanta→pramana→tanmātranubandha→tadbhava (=svabhavapratibandha) という構造が読み取れる。そしてこれに続いて、彼は karyahetu にお ける因果性も簡潔に説明する: 因果性 (hetubhava)は、それ(原因)が存在するときにのみ「結果は]存在 [し、原因がないときには存在しない」という [認識手段(pramana)] にもと づいて、喩例によって示される。それは別個な対象の間の関係である。 そして同一性と因果性をまとめる: 1.このように、同一性あるいは因果性が一般に承認されれば、「無常性がなければ 所作性もない」「火がなければ煙はない」 [と否定的遍充関係が成立する。]すな わち、それ(所証)はそれ(能証)の本質 (svabhava)であるか原因であるか のいずれかである。自身の本質や原因なしにどうして[能証が]存在しようか (しない)。だから、異類例における否定的遍充関係は、主題(ášraya, = dhar min) が存在しなくても成立する。 Dharmakirti の遍充理論において、喩例の要不要は中心的な問題ではなかったと思わ れる。喩例は本質的連関 (svabhavapratibandha) を知るための<手段>に過ぎない のだから、それが理解されれば、喩例はその役割を果たし終え、もはや不要となる。真 に重要なのは遍充関係 (vyapti) の方であり、それと同義の不可離関係(avinábhāva)、 本質的連関である。それは、存在レヴェルでの bhava と svabhava のあり方を概念的 にとらえなおしたものであり(《2.33》 )、存在レヴェルで svabhava は《svabhava (b)》という同類(sajatiya) に共通な機能を有するが故に、同じ語で示される同種 の概念の均一性―推理が成立するための前提条件の根拠を存在レヴェルで保証 される(《1.2》)。従って、当該主題の遍充関係は、限られた喩例によって示され た関係ではあっても、存在レヴェルに根拠をもつものとなりうるのである。 しかしながら、遍充の確定という点において、Dharmakirti 自身の推理論は PVSV の段階ではまだ完成したわけではなかった。遍充関係を<保証>するものが本質的連 関であったとしても、では遍充関係を論証し確定する<手段>は何かと問うならば、 PVSV の中に明確な統一見解はない。上に引用した箇所で、「同一性は喩例におい て示された pramana によって示される」との構造が示されたものの、その直後に は「同一性と因果性がわかった者には喩例は不要である」と Dharmakirti は内遍充 論を思わせる喩例不要の方向も示唆しており、喩例の立場がきわめて微妙である。こ -29
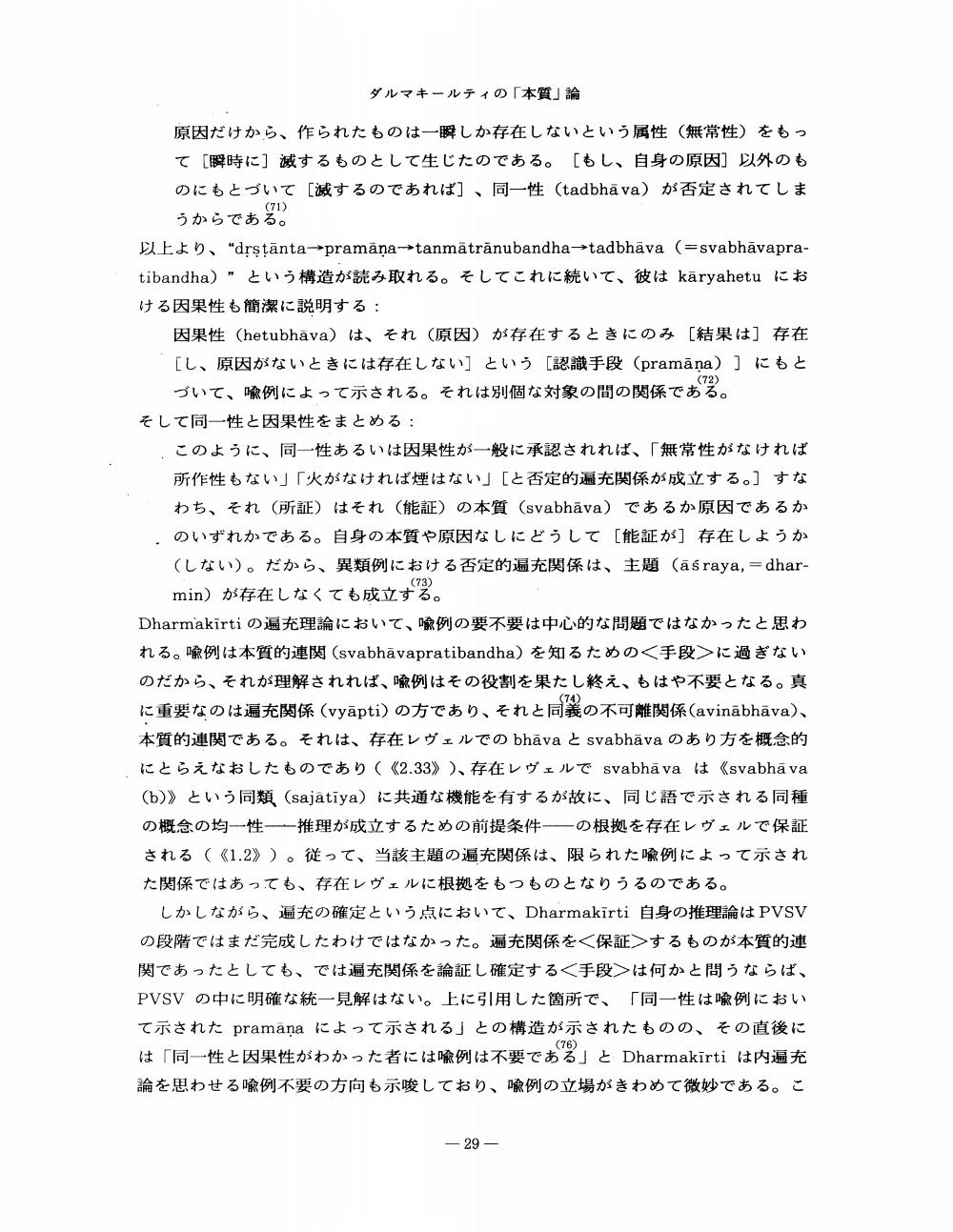
Page Navigation
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44