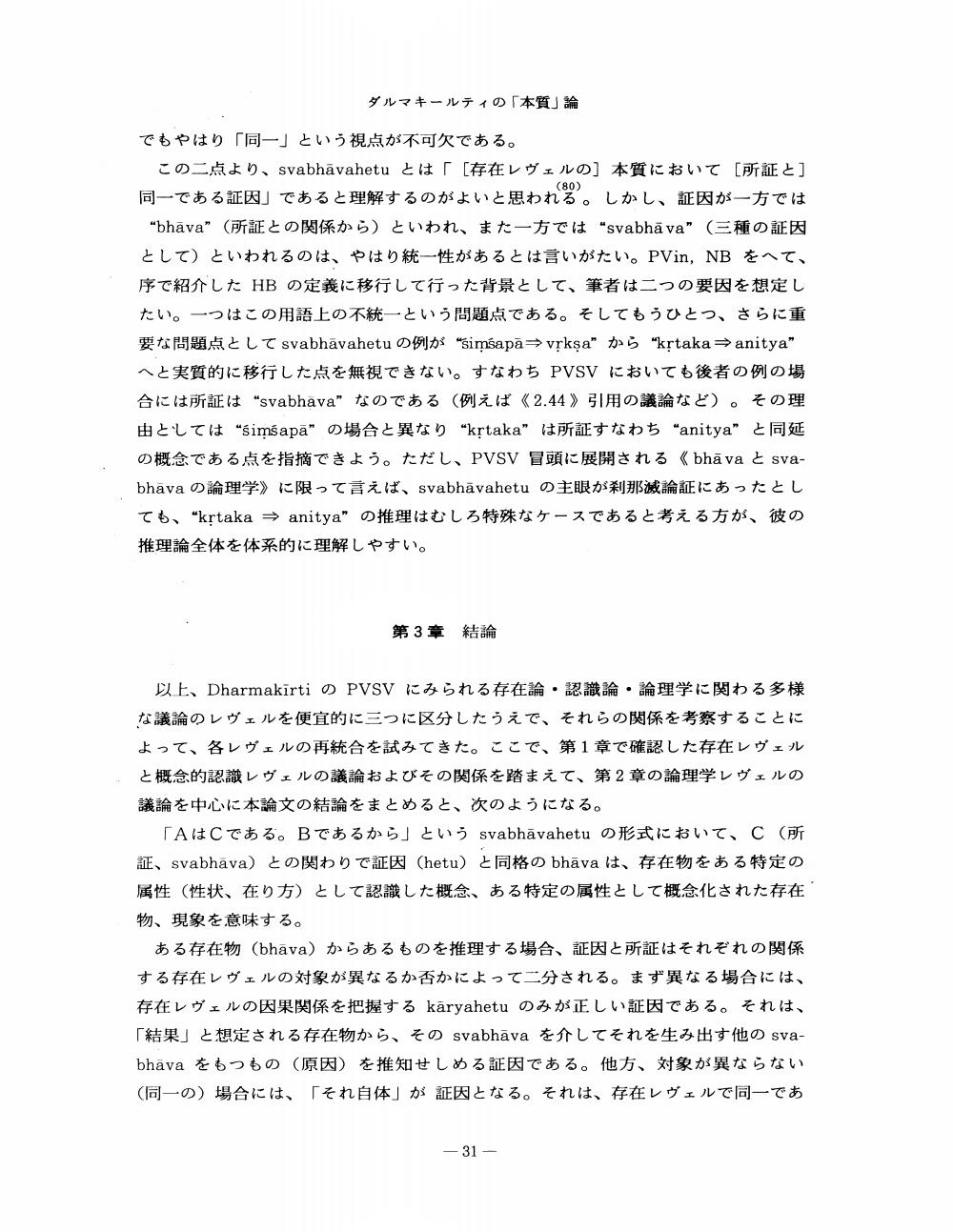Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 (80) でもやはり「同一」という視点が不可欠である。 この二点より、svabhavahetu とは「[存在レヴェルの]本質において[所証と] 同一である証因」であると理解するのがよいと思われる。しかし、証因が一方では "bhava" (所証との関係から)といわれ、また一方では "svabhava" (三種の証因 として)といわれるのは、やはり統一性があるとは言いがたい。PVin, NB をへて、 序で紹介した HB の定義に移行して行った背景として、筆者は二つの要因を想定し たい。一つはこの用語上の不統一という問題点である。そしてもうひとつ、さらに重 要な問題点として svabhavahetu の例が“simsapa⇒ vrksa"から"krtaka = anitya" へと実質的に移行した点を無視できない。すなわち PVSV においても後者の例の場 合には所証は“svabhava” なのである(例えば《2.44》引用の議論など)。その理 由としては“simsapa" の場合と異なり“krtaka" は所証すなわち“anitya" と同延 の概念である点を指摘できよう。ただし、PVSV 冒頭に展開される《 bhava と svabhava の論理学》に限って言えば、syabhavahetu の主眼が刹那滅論証にあったとし ても、“krtaka = anitya" の推理はむしろ特殊なケースであると考える方が、彼の 推理論全体を体系的に理解しやすい。 第3章 結論 以上、Dharmakirti の PVSV にみられる存在論・認識論・論理学に関わる多様 な議論のレヴェルを便宜的に三つに区分したうえで、それらの関係を考察することに よって、各レヴェルの再統合を試みてきた。ここで、第1章で確認した存在レヴェル と概念的認識レヴェルの議論およびその関係を踏まえて、第2章の論理学レヴェルの 議論を中心に本論文の結論をまとめると、次のようになる。 「AはCである。Bであるから」という svabhavahetu の形式において、C(所 証、svabhava)との関わりで証因 (hetu)と同格の bhava は、存在物をある特定の 属性(性状、在り方)として認識した概念、ある特定の属性として概念化された存在 物、現象を意味する。 ある存在物(bhava)からあるものを推理する場合、証因と所証はそれぞれの関係 する存在レヴェルの対象が異なるか否かによって二分される。まず異なる場合には、 存在レヴェルの因果関係を把握する karyahetu のみが正しい証因である。それは、 「結果」と想定される存在物から、その svabhava を介してそれを生み出す他の svabhava をもつもの(原因)を推知せしめる証因である。他方、対象が異ならない (同一の)場合には、「それ自体」が 証因となる。それは、存在レヴェルで同一であ -31
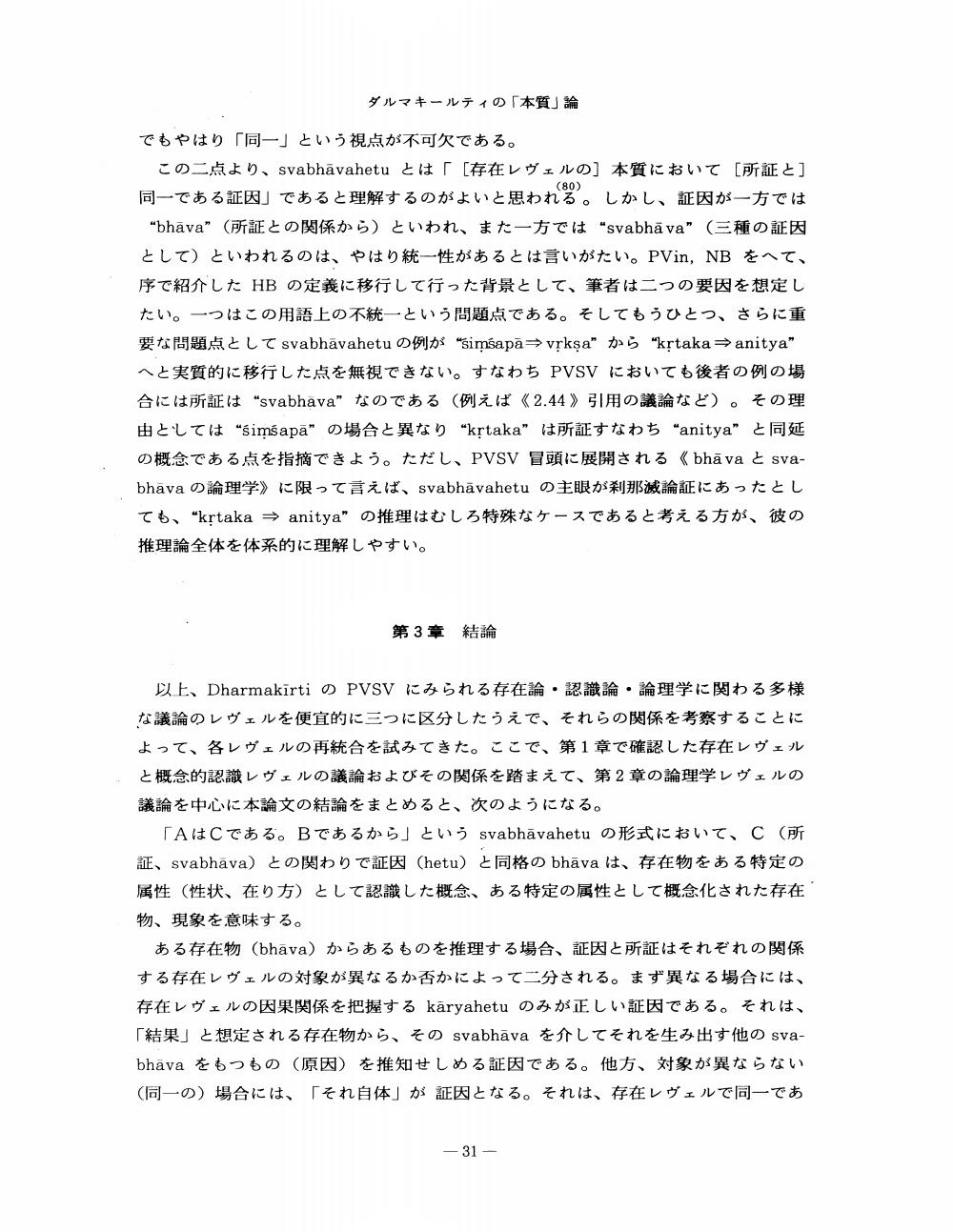
Page Navigation
1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44