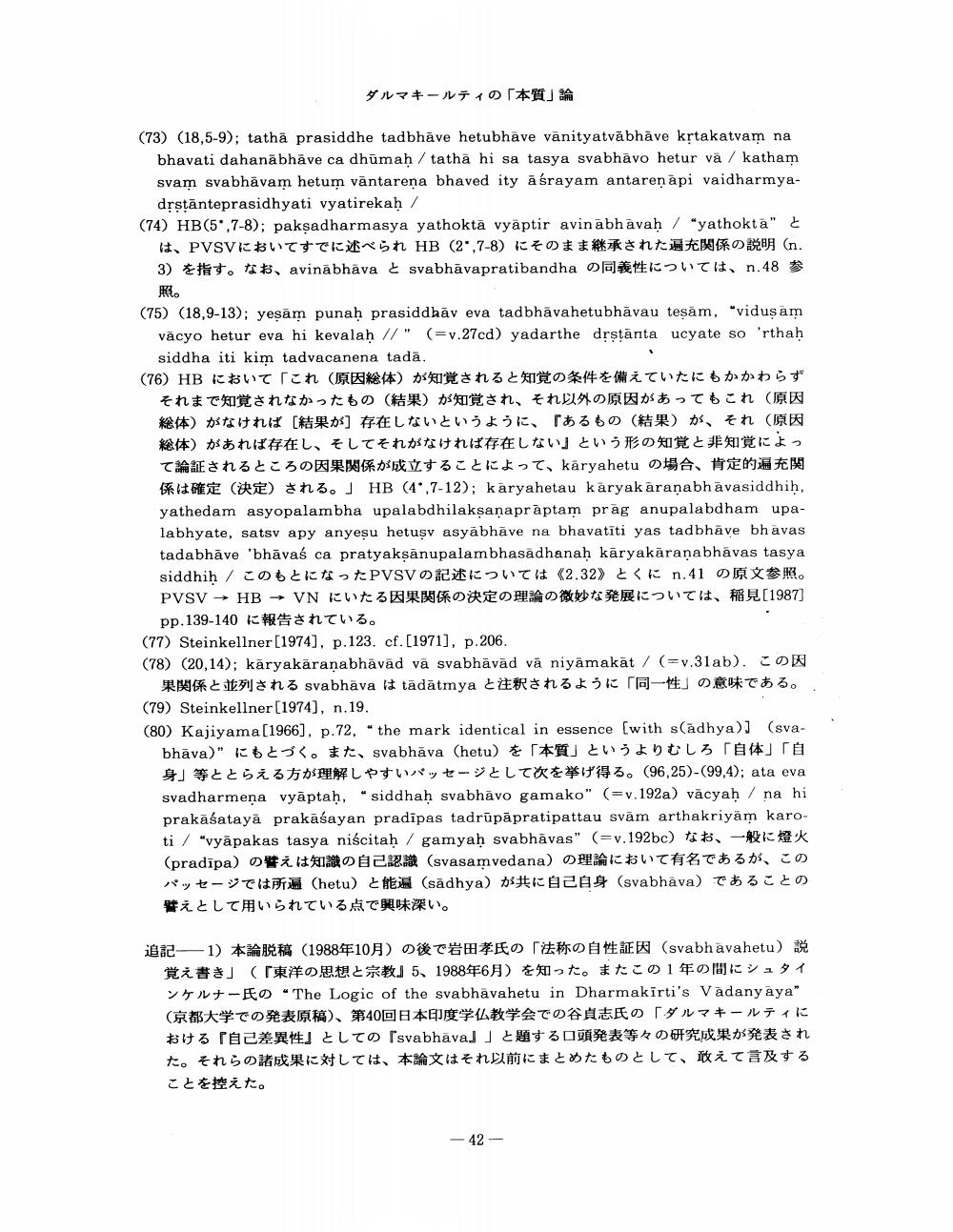Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 (73) (18,5-9); tatha prasiddhe tadbhave hetubhave vanityatvabhave krtakatvam na bhavati dahanabhave ca dhumah / tatha hi sa tasya svabhavo hetur va / katham svam svabhavam hetum vantarena bhaved ity asrayam antarenapi vaidharmya drstanteprasidhyati vyatirekah / (74) HB(5*,7-8); paksadharmasya yathokta vyaptir avinabhavah / "yathokta" Z は、PVSVにおいてすでに述べられ HB (2*,7-8)にそのまま継承された遍充関係の説明(n. 3) を指す。なお、avinabhava と svabhavapratibandha の同義性については、n.48 参 照。 (75) (18,9-13); yesam punah prasiddhav eva tadbhavahetubhavau tesam, "vidusam vacyo hetur eva hi kevalah // " (=v.27cd) yadarthe drstanta ucyate so 'rthah siddha iti kim tadvacanena tada. (76) HB において「これ(原因総体)が知覚されると知覚の条件を備えていたにもかかわらず それまで知覚されなかったもの(結果)が知覚され、それ以外の原因があってもこれ(原因 総体)がなければ[結果が]存在しないというように、『あるもの(結果)が、それ(原因 総体)があれば存在し、そしてそれがなければ存在しない」という形の知覚と非知覚によっ て論証されるところの因果関係が成立することによって、karyahetu の場合、肯定的遍充関 係は確定(決定)される。」 HB (4',7-12); karyahetau karyakaranabh avasiddhih, yathedam asyopalambha upalabdhilaksanapraptam prag anupalabdham upalabhyate, satsv apy anyesu hetusv asyabhave na bhavatiti yas tadbhave bhavas tadabhave 'bhavas ca pratyaksanupalambhasadhanah karyakaranabhavas tasya siddhih / このもとになったPVSVの記述については《2.32》とくに n.41 の原文参照。 PVSV - HB - VN にいたる因果関係の決定の理論の微妙な発展については、稲見[1987] pp.139-140 に報告されている。 (77) Steinkellner [1974], p.123. cf. [1971], p.206. (78) (20,14); karyakaranabhavad va svabhavad va niyamakat / (=v.3lab). この因 果関係と並列される svabhava は tadatmya と注釈されるように「同一性」の意味である。 . (79) Steinkellner[1974], n.19. (80) Kajiyama [1966], p.72, "the mark identical in essence (with s(adhya)] (svabhava)”にもとづく。また、syabhava (hetu)を「本質」というよりむしろ「自体」「自 身」等ととらえる方が理解しやすいパッセージとして次を挙げ得る。(96,25)-(99,4); ata eva svadharmena vyaptah, "siddhah svabhavo gamako" (=v.192a) vacyah / na hi prakasataya prakasayan pradipas tadrupapratipattau svam arthakriyam karoti / "vyapakas tasya niscitah / gamyah svabhavas" (=v.192bc) なお、一般に燈火 (pradipa)の誓えは知識の自己認識(svasamvedana)の理論において有名であるが、この パッセージでは所遍(hetu)と能遍(sadhya)が共に自己自身(svabhava)であることの 譬えとして用いられている点で興味深い。 追記――1) 本論脱稿 (1988年10月)の後で岩田孝氏の「法称の自性証因(svabhavahetu)説 覚え書き」(「東洋の思想と宗教』5、1988年6月)を知った。またこの1年の間にシュタイ ンケルナー氏の“The Logic of the svabhavahetu in Dharmakirti's Vadanyaya" (京都大学での発表原稿)、第40回日本印度学仏教学会での谷貞志氏の「ダルマキールティに おける「自己差異性』としての「svabhava』」と題する口頭発表等々の研究成果が発表され た。それらの諸成果に対しては、本論文はそれ以前にまとめたものとして、敢えて言及する ことを控えた。 -42
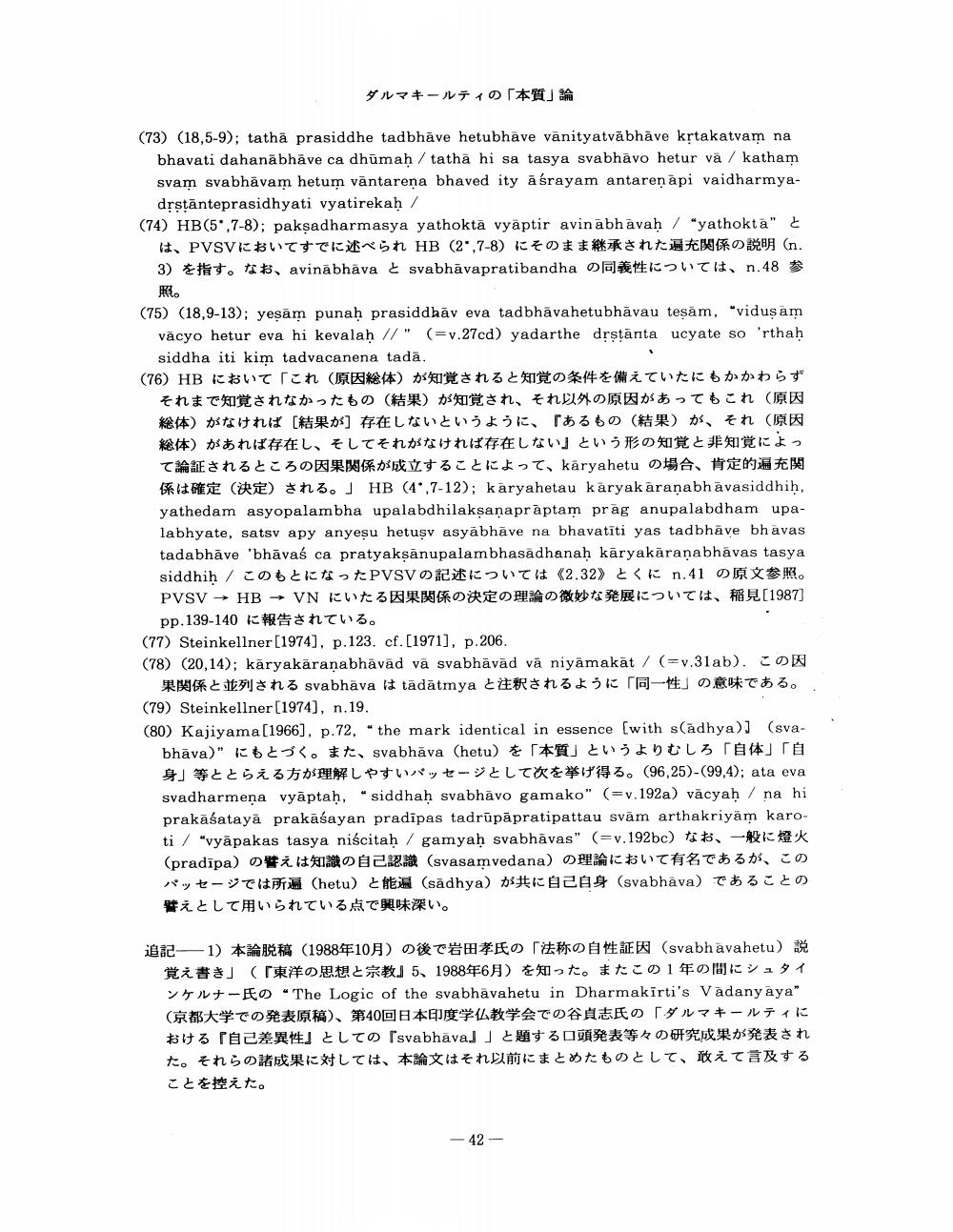
Page Navigation
1 ... 41 42 43 44