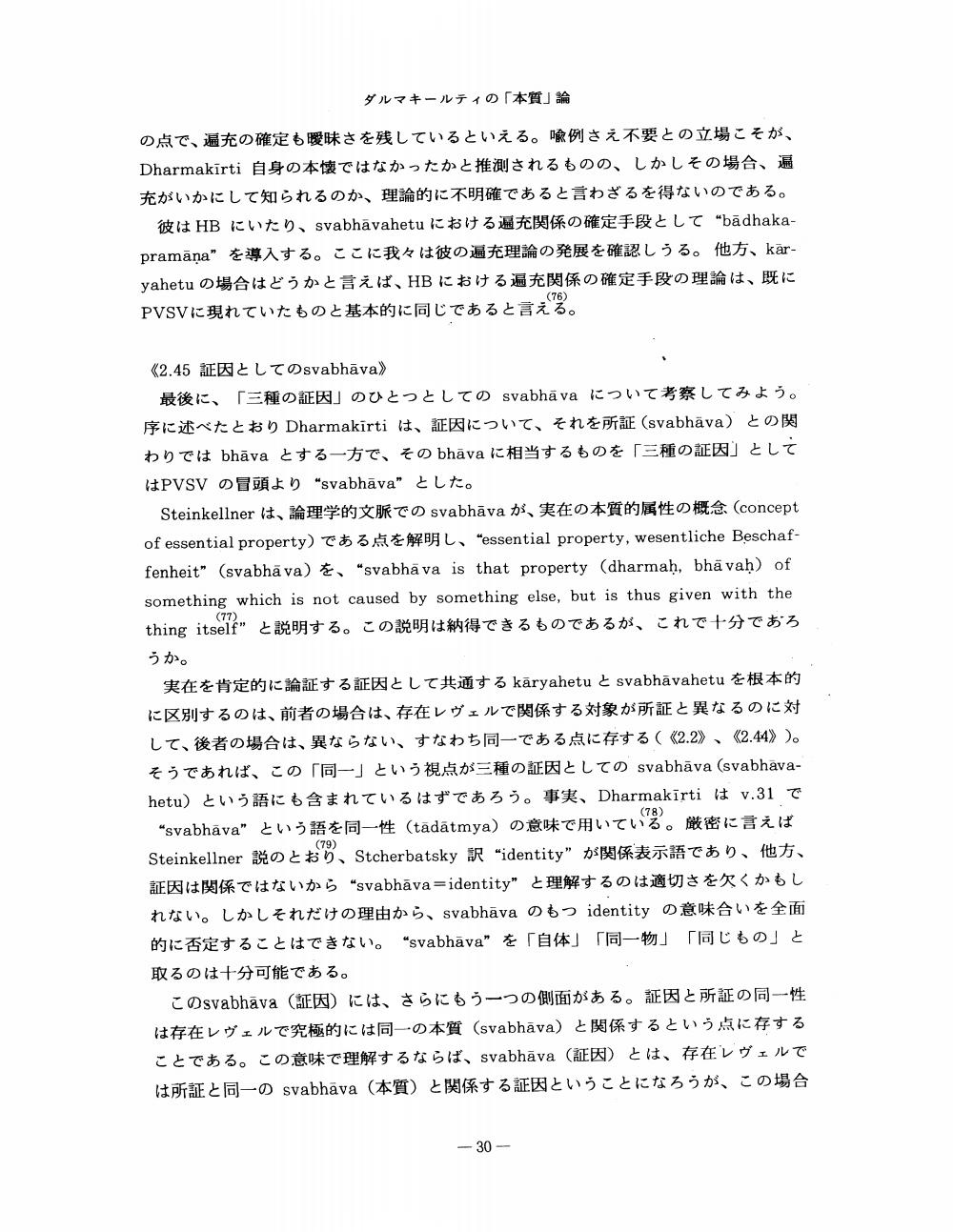Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 の点で、遍充の確定も曖昧さを残しているといえる。喩例さえ不要との立場こそが、 Dharmakirti 自身の本懐ではなかったかと推測されるものの、しかしその場合、遍 充がいかにして知られるのか、理論的に不明確であると言わざるを得ないのである。 彼は HB にいたり、svabhavahetu における過充関係の確定手段として "badhakapramana" を導入する。ここに我々は彼の遍充理論の発展を確認しうる。 他方、karyahetu の場合はどうかと言えば、HB における遍充関係の確定手段の理論は、既に PVSVに現れていたものと基本的に同じであると言える。 (77) <<2.45 証因としてのsvabhava》 最後に、「三種の証因」のひとつとしての svabhava について考察してみよう。 序に述べたとおり Dharmakirti は、証因について、それを所証 (svabhava)との関 わりでは bhava とする一方で、その bhava に相当するものを「三種の証因」として はPVSV の冒頭より "svabhava" とした。 Steinkellner は、論理学的文脈での svabhava が、実在の本質的属性の概念 (concept of essential property)である点を解明し、“essential property, wesentliche Beschaffenheit" (svabhava) & "svabhava is that property (dharmah, bhavah) of something which is not caused by something else, but is thus given with the thing itself"と説明する。この説明は納得できるものであるが、これで十分であろ うか。 実在を肯定的に論証する証因として共通する karyahetu と svabhavahetu を根本的 に区別するのは、前者の場合は、存在レヴェルで関係する対象が所証と異なるのに対 して、後者の場合は、異ならない、すなわち同一である点に存する(《2.2》、《2.44》)。 そうであれば、この「同一」という視点が三種の証因としての svabhava (svabhavahetu)という語にも含まれているはずであろう。事実、Dharmakirti は v.31 で "svabhava" という語を同一性 (tadátmya)の意味で用いている。厳密に言えば Steinkellner 説のとおり、Stcherbatsky 訳 "identity" が関係表示語であり、他方、 証因は関係ではないから "svabhava=identity" と理解するのは適切さを欠くかもし れない。しかしそれだけの理由から、svabhava のもつ identity の意味合いを全面 的に否定することはできない。 "svabhava" を「自体」「同一物」「同じもの」と 取るのは十分可能である。 このsvabhava (証因)には、さらにもう一つの側面がある。証因と所証の同一性 は存在レヴェルで究極的には同一の本質 (svabhava)と関係するという点に存する ことである。この意味で理解するならば、svabhava(証因)とは、存在レヴェルで は所証と同一の svabhava(本質)と関係する証因ということになろうが、この場合 -30
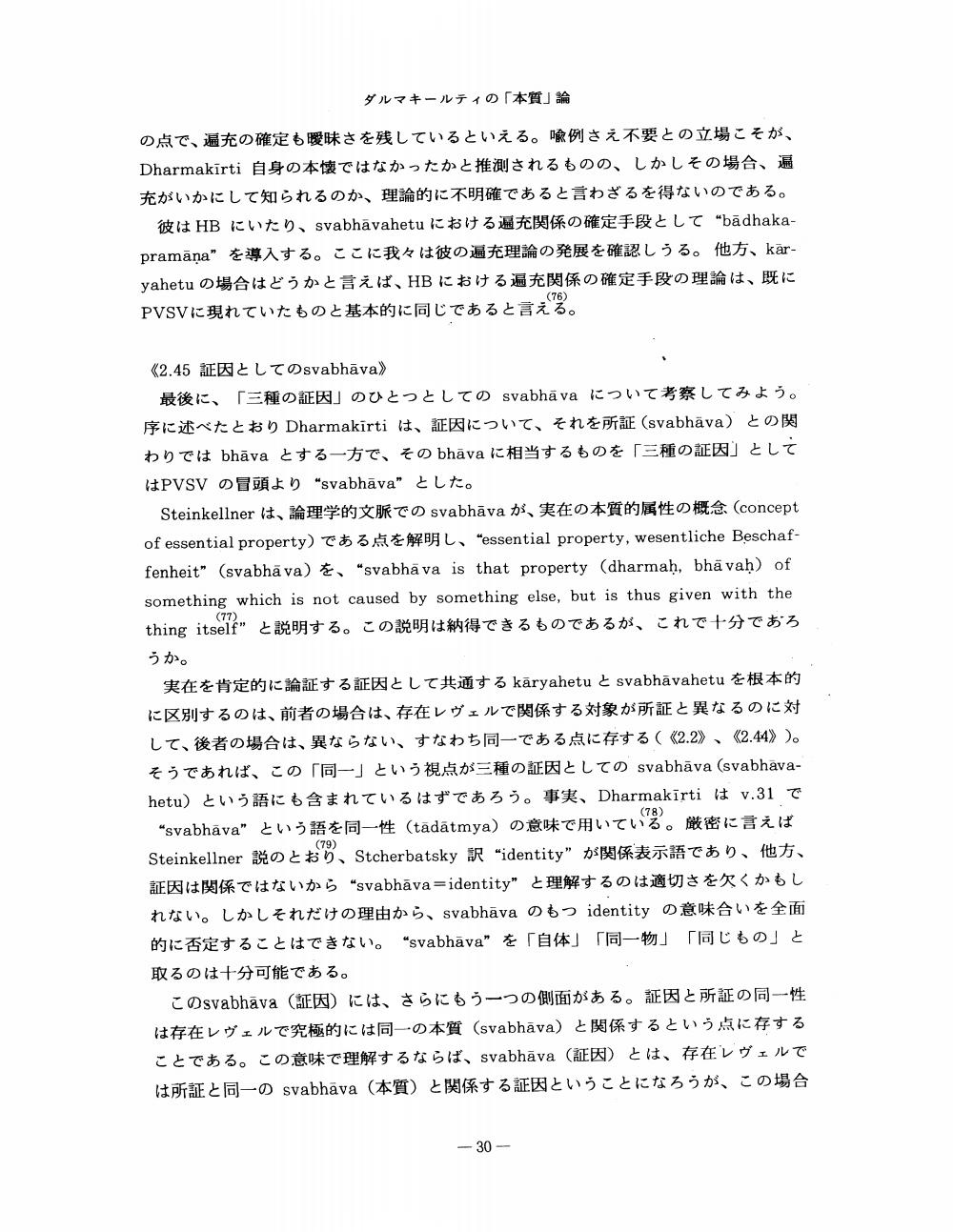
Page Navigation
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44