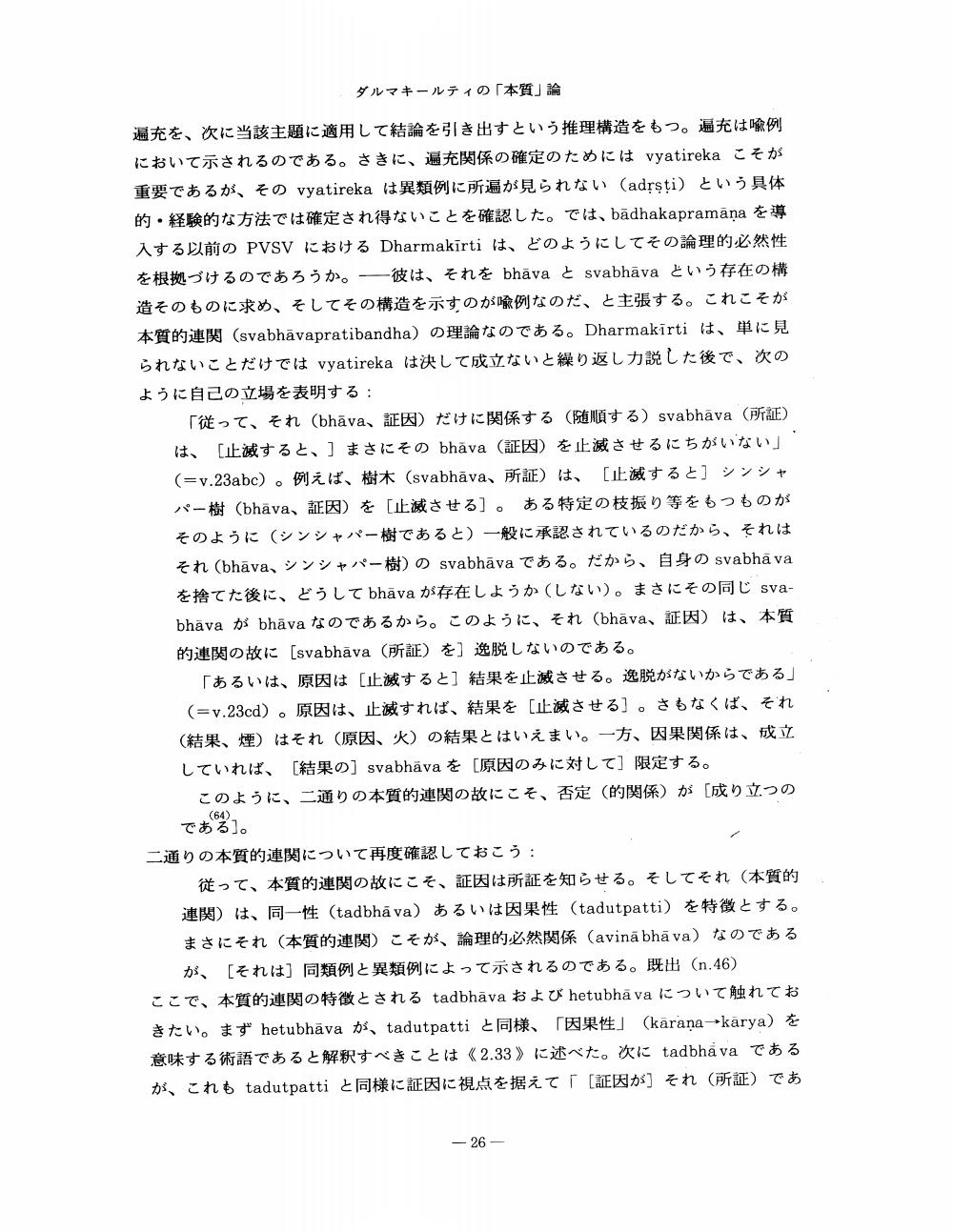Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 遍充を、次に当該主題に適用して結論を引き出すという推理構造をもつ。遍充は喩例 において示されるのである。さきに、遍充関係の確定のためには vyatireka こそが 重要であるが、その vyatireka は異類例に所遍が見られない(adrsti)という具体 的・経験的な方法では確定され得ないことを確認した。では、badhakapramana を導 入する以前の PVSV における Dharmakirti は、どのようにしてその論理的必然性 を根拠づけるのであろうか。 彼は、それを bhava と svabhava という存在の構 造そのものに求め、そしてその構造を示すのが喩例なのだ、と主張する。これこそが 本質的連関 (svabhavapratibandha)の理論なのである。Dharmakirti は、単に見 られないことだけでは vyatireka は決して成立ないと繰り返し力説した後で、次の ように自己の立場を表明する: 「従って、それ(bhava、証因)だけに関係する(随順する) svabhava(所証) は、止滅すると、] まさにその bhava (証因)を止滅させるにちがいない」 (=v.23abc)。例えば、樹木 (svabháva、所証)は、[止滅すると] シンシャ パー樹(bhava、証因)を「止滅させる]。 ある特定の枝振り等をもつものが そのように(シンシャパー樹であると) 一般に承認されているのだから、それは それ (bhava、シンシャパー樹)の svabhava である。だから、自身の svabhava を捨てた後に、どうして bhava が存在しようか(しない)。まさにその同じ svabhava が bhava なのであるから。このように、それ(bhava、証因)は、本質 的連関の故に [svabhava (所証)を]逸脱しないのである。 「あるいは、原因は[止滅すると]結果を止滅させる。逸脱がないからである」 (=v.23cd)。原因は、止滅すれば、結果を「止滅させる]。さもなくば、それ (結果、煙)はそれ(原因、火)の結果とはいえまい。一方、因果関係は、成立 していれば、「結果の] svabhava を[原因のみに対して]限定する。 このように、二通りの本質的連関の故にこそ、否定(的関係)が「成り立つの である」。 二通りの本質的連関について再度確認しておこう: 従って、本質的連関の故にこそ、証因は所証を知らせる。そしてそれ(本質的 連関)は、同一性 (tadbhava) あるいは因果性 (tadutpatti) を特徴とする。 まさにそれ(本質的連関)こそが、論理的必然関係 (avinabhava) なのである が、「それは] 同類例と異類例によって示されるのである。既出(n.46) ここで、本質的連関の特徴とされる tadbhava および hetubha va について触れてお きたい。まず hetubhava が、tadutpatti と同様、「因果性」(karana→karya) を 意味する術語であると解釈すべきことは《2.33 》に述べた。次に tadbhava である が、これも tadutpatti と同様に証因に視点を据えて 「[証因が]それ(所証)であ -26
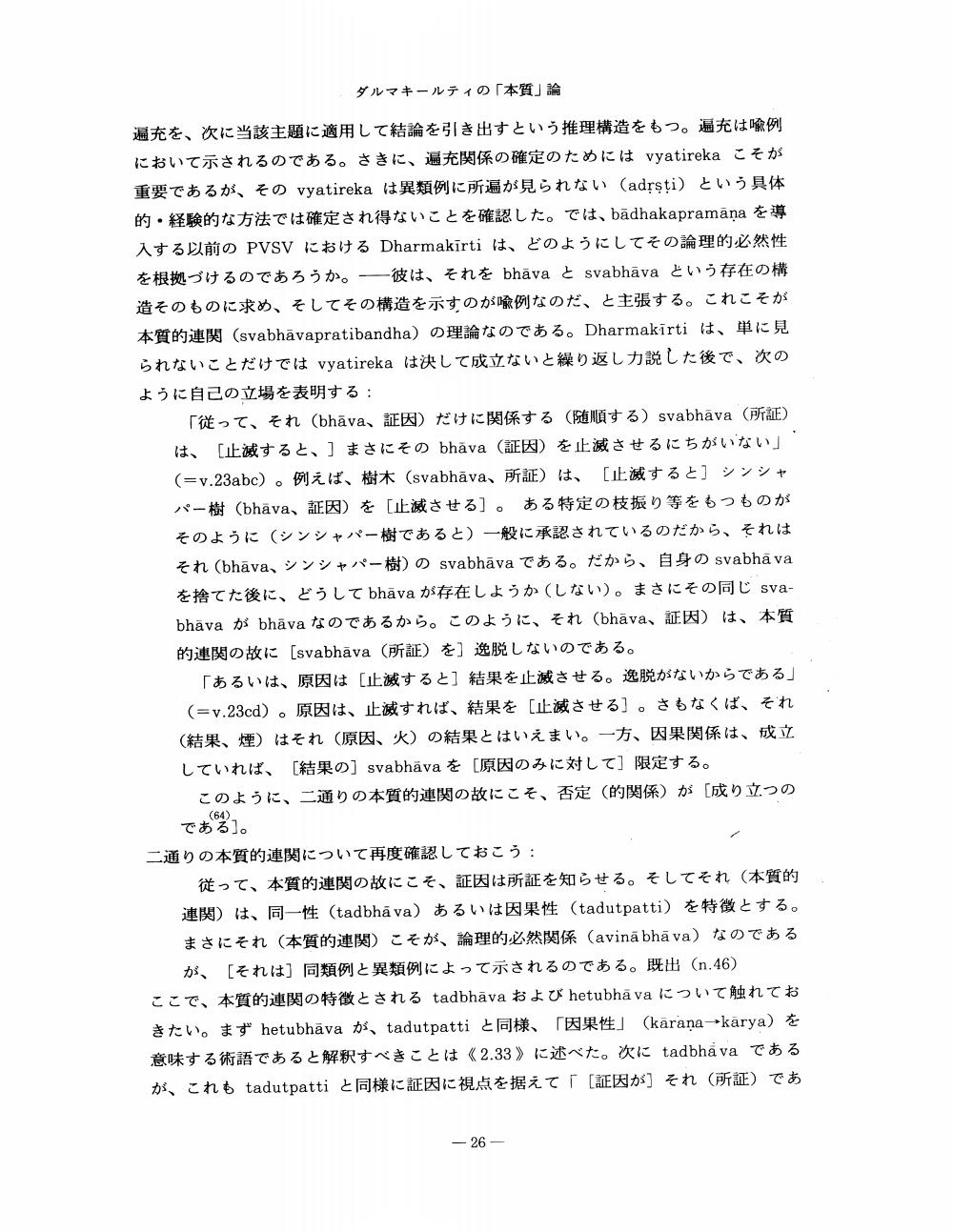
Page Navigation
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44