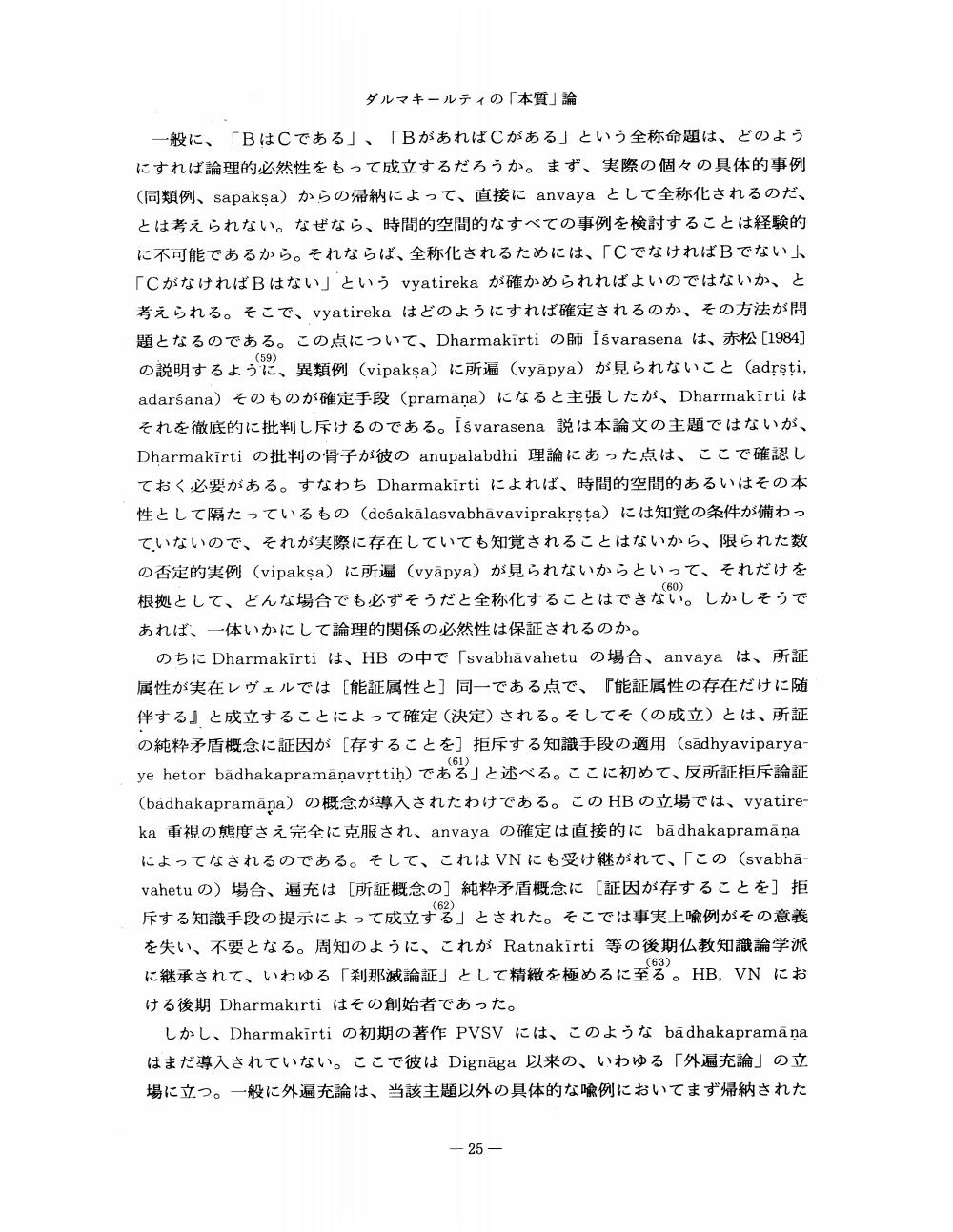Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 (59) (60) 一般に、「BはCである」、「BがあればCがある」という全称命題は、どのよう にすれば論理的必然性をもって成立するだろうか。まず、実際の個々の具体的事例 (同類例、sapaksa) からの帰納によって、直接に anvaya として全称化されるのだ、 とは考えられない。なぜなら、時間的空間的なすべての事例を検討することは経験的 に不可能であるから。それならば、全称化されるためには、「CでなければBでない」、 「CがなければBはない」という vyatireka が確かめられればよいのではないか、と 考えられる。そこで、vyatireka はどのようにすれば確定されるのか、その方法が問 題となるのである。この点について、Dharmakirti の師 ISvarasena は、赤松 [1984] の説明するように、異類例 (vipaksa)に所遍(vyapya)が見られないこと (adrsti, adarsana)そのものが確定手段 (pramana)になると主張したが、Dharmakirti は それを徹底的に批判し斥けるのである。IŠvarasena 説は本論文の主題ではないが、 Dharmakirti の批判の骨子が彼の anupalabdhi 理論にあった点は、ここで確認し ておく必要がある。すなわち Dharmakirti によれば、時間的空間的あるいはその本 性として隔たっているもの(desakalasvabhavaviprakrsta)には知覚の条件が備わっ ていないので、それが実際に存在していても知覚されることはないから、限られた数 の否定的実例 (vipaksa) に所遍 (vyapya) が見られないからといって、それだけを 根拠として、どんな場合でも必ずそうだと全称化することはできない。しかしそうで あれば、一体いかにして論理的関係の必然性は保証されるのか。 のちに Dharmakirti は、HB の中で「svabhavahetu の場合、anvaya は、所証 属性が実在レヴェルでは「能証属性と]同一である点で、『能証属性の存在だけに随 伴する』と成立することによって確定(決定)される。そしてそ(の成立)とは、所証 の純粋矛盾概念に証因が[存することを]拒斥する知識手段の適用(sadhyaviparyaye hetor badhakapramanavrttih) である」と述べる。ここに初めて、反所証拒斥論証 (badhakapramana) の概念が導入されたわけである。この HB の立場では、vyatireka 重視の態度さえ完全に克服され、anvaya の確定は直接的に badhakapramana によってなされるのである。そして、これは VN にも受け継がれて、「この(svabhavahetu の)場合、遍充は[所証概念の]純粋矛盾概念に[証因が存することを]拒 斥する知識手段の提示によって成立する」とされた。そこでは事実上喩例がその意義 を失い、不要となる。周知のように、これが Ratnakirti 等の後期仏教知識論学派 に継承されて、いわゆる「刹那滅論証」として精緻を極めるに至る。HB, VN にお ける後期 Dharmakirti はその創始者であった。 しかし、Dharmakirti の初期の著作 PVSV には、このような badhakapramana はまだ導入されていない。ここで彼は Dignaga 以来の、いわゆる「外遍充論」の立 場に立つ。一般に外遍充論は、当該主題以外の具体的な喩例においてまず帰納された (61) (63) - 25 -
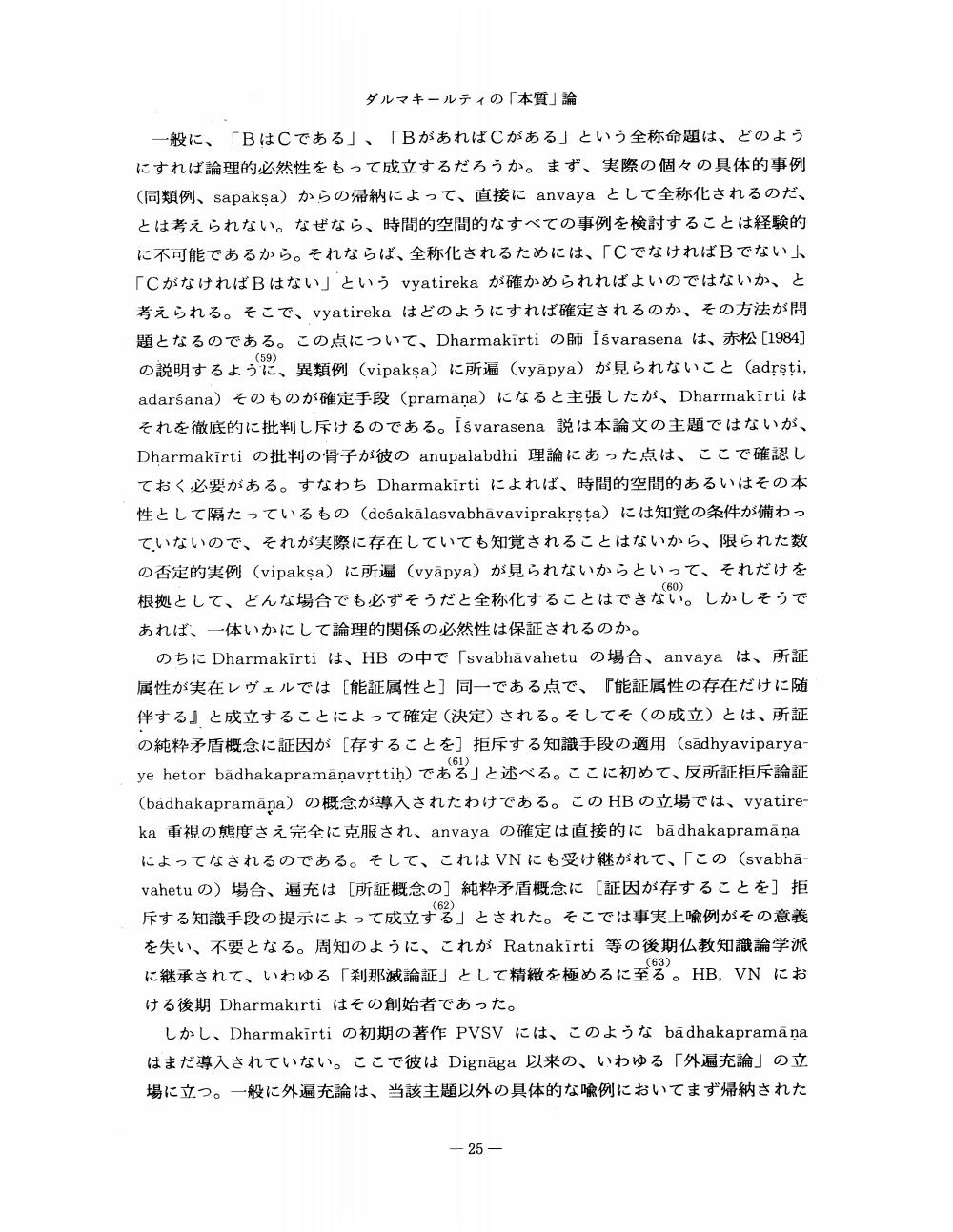
Page Navigation
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44