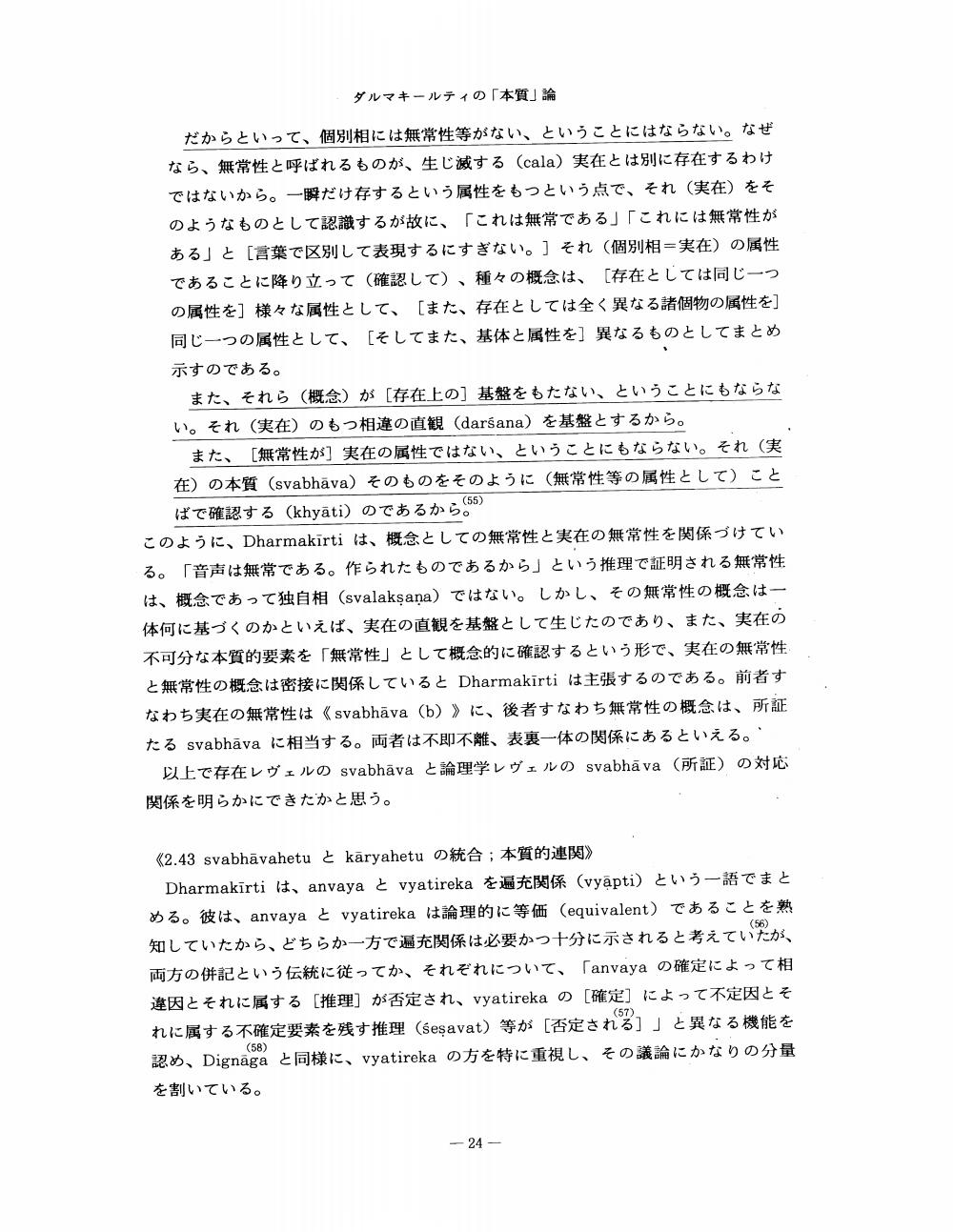Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 だからといって、個別相には無常性等がない、ということにはならない。なぜ なら、無常性と呼ばれるものが、生じ滅する (cala) 実在とは別に存在するわけ ではないから。一瞬だけ存するという属性をもっという点で、それ(実在)をそ のようなものとして認識するが故に、「これは無常である」「これには無常性が ある」と「言葉で区別して表現するにすぎない。] それ(個別相=実在)の属性 であることに降り立って(確認して)、種々の概念は、「存在としては同じ一つ の属性を]様々な属性として、[また、存在としては全く異なる諸個物の属性を] 同じ一つの属性として、[そしてまた、基体と属性を]異なるものとしてまとめ 示すのである。 また、それら(概念)が[存在上の] 基盤をもたない、ということにもならな い。それ(実在)のもつ相違の直観 (darsana) を基盤とするから。 また、「無常性が]実在の属性ではない、ということにもならない。それ(実 在)の本質 (svabhava) そのものをそのように(無常性等の属性として)こと ばで確認する (khyati) のであるから。 このように、Dharmakirti は、概念としての無常性と実在の無常性を関係づけてい る。「音声は無常である。作られたものであるから」という推理で証明される無常性 は、概念であって独自相(svalaksana) ではない。しかし、その無常性の概念は一 体何に基づくのかといえば、実在の直観を基盤として生じたのであり、また、実在の 不可分な本質的要素を「無常性」として概念的に確認するという形で、実在の無常性 と無常性の概念は密接に関係していると Dharmakirti は主張するのである。前者す なわち実在の無常性は《svabhava (b)》に、後者すなわち無常性の概念は、所証 たる svabhava に相当する。両者は不即不離、表裏一体の関係にあるといえる。 以上で存在レヴェルの svabhava と論理学レヴェルの svabhava (所証)の対応 関係を明らかにできたかと思う。 (56) <<2.43 svabhavahetu と karyahetu の統合; 本質的連関》 Dharmakirti は、anvaya と vyatireka を遍充関係 (vyapti)という一語でまと める。彼は、anvaya と vyatireka は論理的に等価 (equivalent)であることを熟 知していたから、どちらか一方で遍充関係は必要かつ十分に示されると考えていたが、 両方の併記という伝統に従ってか、それぞれについて、「anvaya の確定によって相 違因とそれに属する「推理]が否定され、vyatireka の[確定]によって不定因とそ れに属する不確定要素を残す推理 (sesavat) 等が「否定される]」と異なる機能を 認め、Dignaga と同様に、vyatireka の方を特に重視し、その議論にかなりの分量 を割いている。 (58) -24
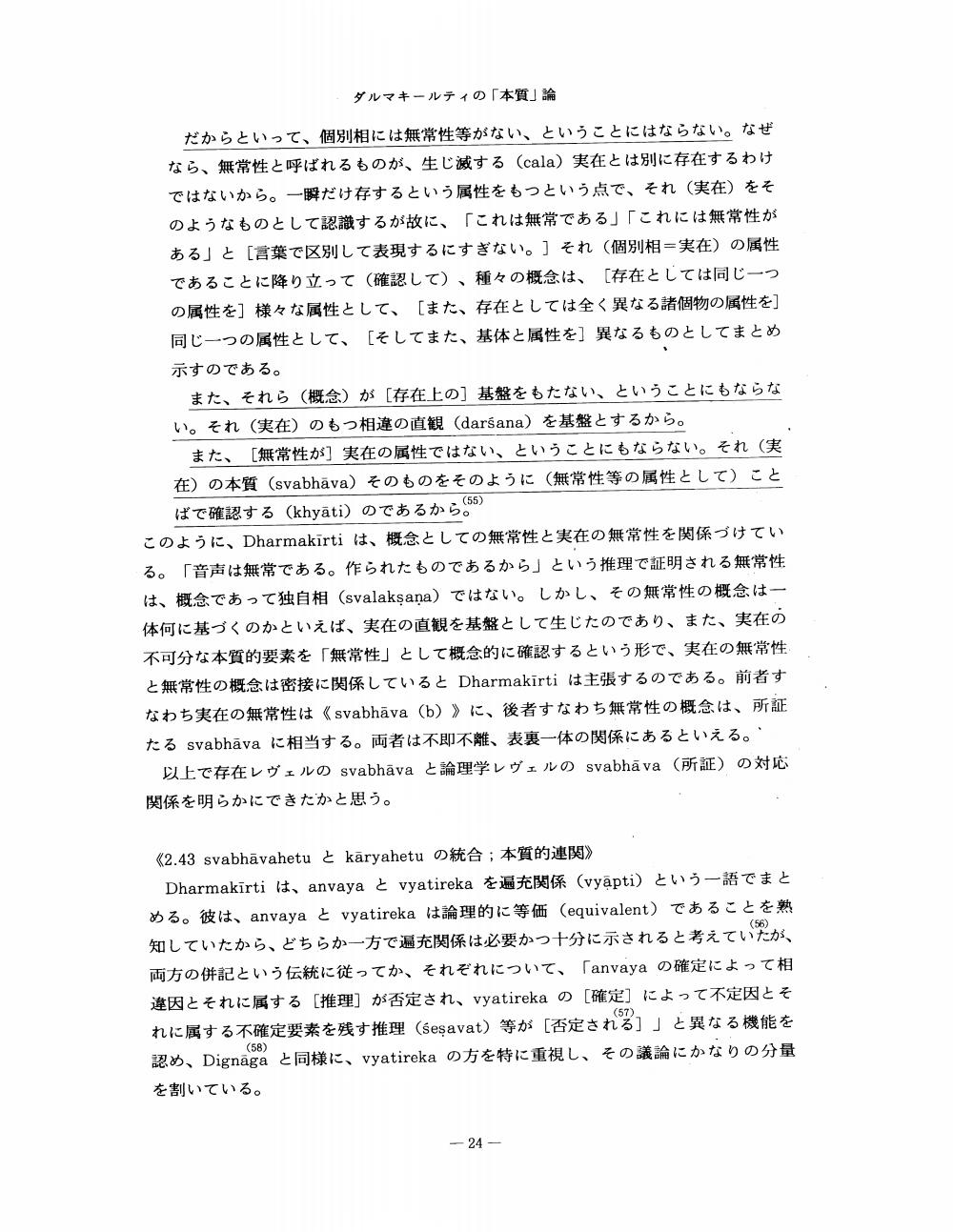
Page Navigation
1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44