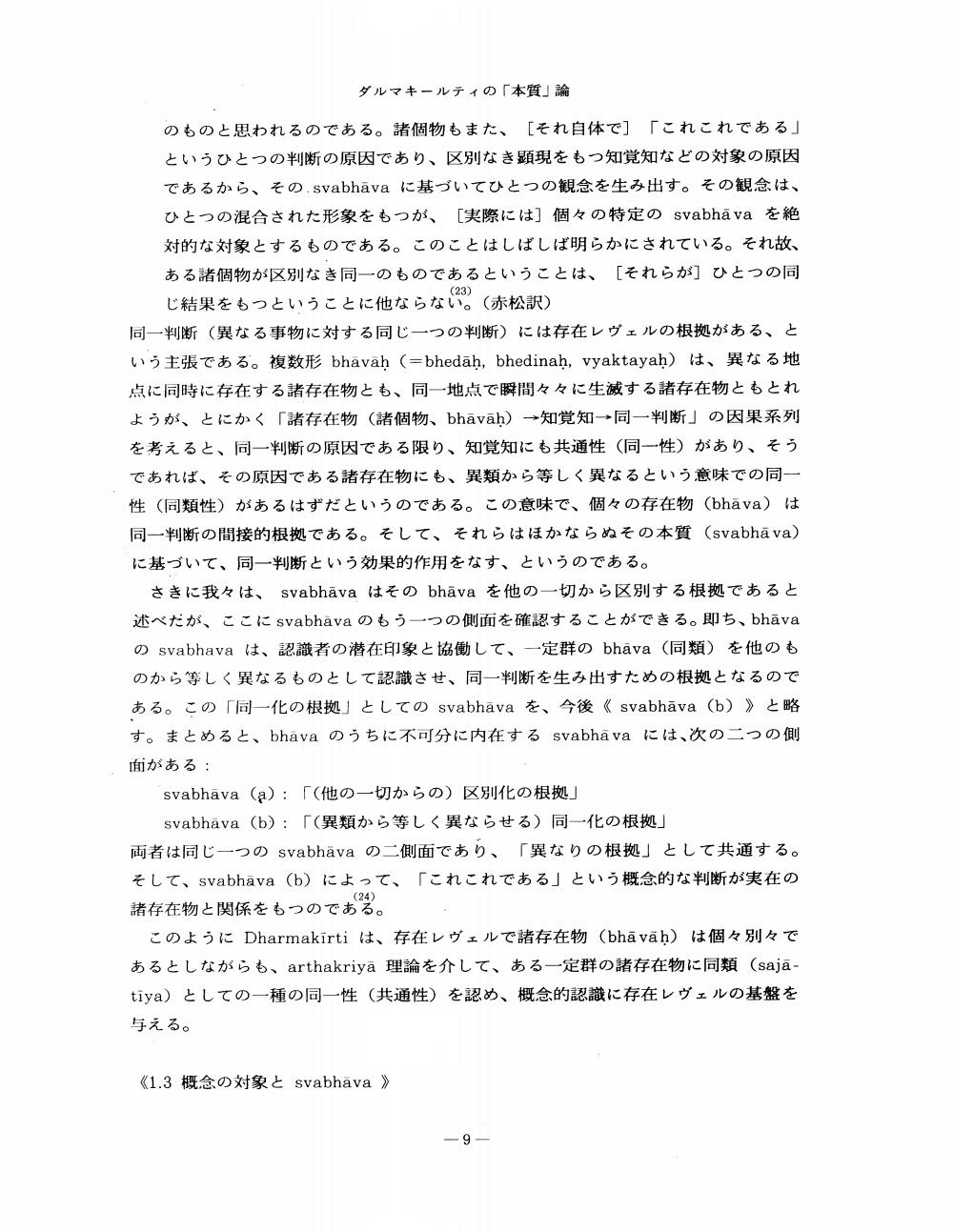Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 (23) のものと思われるのである。諸個物もまた、「それ自体で] 「これこれである」 というひとつの判断の原因であり、区別なき顕現をもつ知覚知などの対象の原因 であるから、その.svabhava に基づいてひとつの観念を生み出す。その観念は、 ひとつの混合された形象をもつが、実際には] 個々の特定の svabhava を絶 対的な対象とするものである。このことはしばしば明らかにされている。それ故、 ある諸個物が区別なき同一のものであるということは、「それらが]ひとつの同 じ結果をもつということに他ならない。(赤松訳) 同一判断(異なる事物に対する同じ一つの判断)には存在レヴェルの根拠がある、と いう主張である。複数形 bhavah (=bhedah, bhedinah, vyaktayah)は、異なる地 点に同時に存在する諸存在物とも、同一地点で瞬間々々に生滅する諸存在物ともとれ ようが、とにかく「諸存在物(諸個物、bháváh) →知覚知→同一判断」の因果系列 を考えると、同一判断の原因である限り、知覚知にも共通性(同一性)があり、そう であれば、その原因である諸存在物にも、異類から等しく異なるという意味での同一 性(同類性)があるはずだというのである。この意味で、個々の存在物(bhava) は 同一判断の間接的根拠である。そして、それらはほかならぬその本質 (svabhava) に基づいて、同一判断という効果的作用をなす、というのである。 さきに我々は、 svabhava はその bhava を他の一切から区別する根拠であると 述べたが、ここに svabhava のもう一つの側面を確認することができる。即ち、bháva の svabhava は、認識者の潜在印象と協働して、一定群の bhava (同類)を他のも のから等しく異なるものとして認識させ、同一判断を生み出すための根拠となるので ある。この「同一化の根拠」としての svabhava を、今後《 svabhava (b) 》と略 す。まとめると、bhava のうちに不可分に内在する svabhava には、次の二つの側 面がある: svabhava (a): 「(他の一切からの)区別化の根拠」 svabhava (b) : 「(異類から等しく異ならせる) 同一化の根拠」 両者は同じ一つの svabhava の二側面であり、「異なりの根拠」として共通する。 そして、svabhava (b)によって、「これこれである」という概念的な判断が実在の 諸存在物と関係をもつのである。 このように Dharmakirti は、存在レヴェルで諸存在物(bháváh)は個々別々で あるとしながらも、arthakriya 理論を介して、ある一定群の諸存在物に同類 (sajatiya)としての一種の同一性(共通性)を認め、概念的認識に存在レヴェルの基盤を 与える。 24) <<1.3 概念の対象と svabhava >> -9
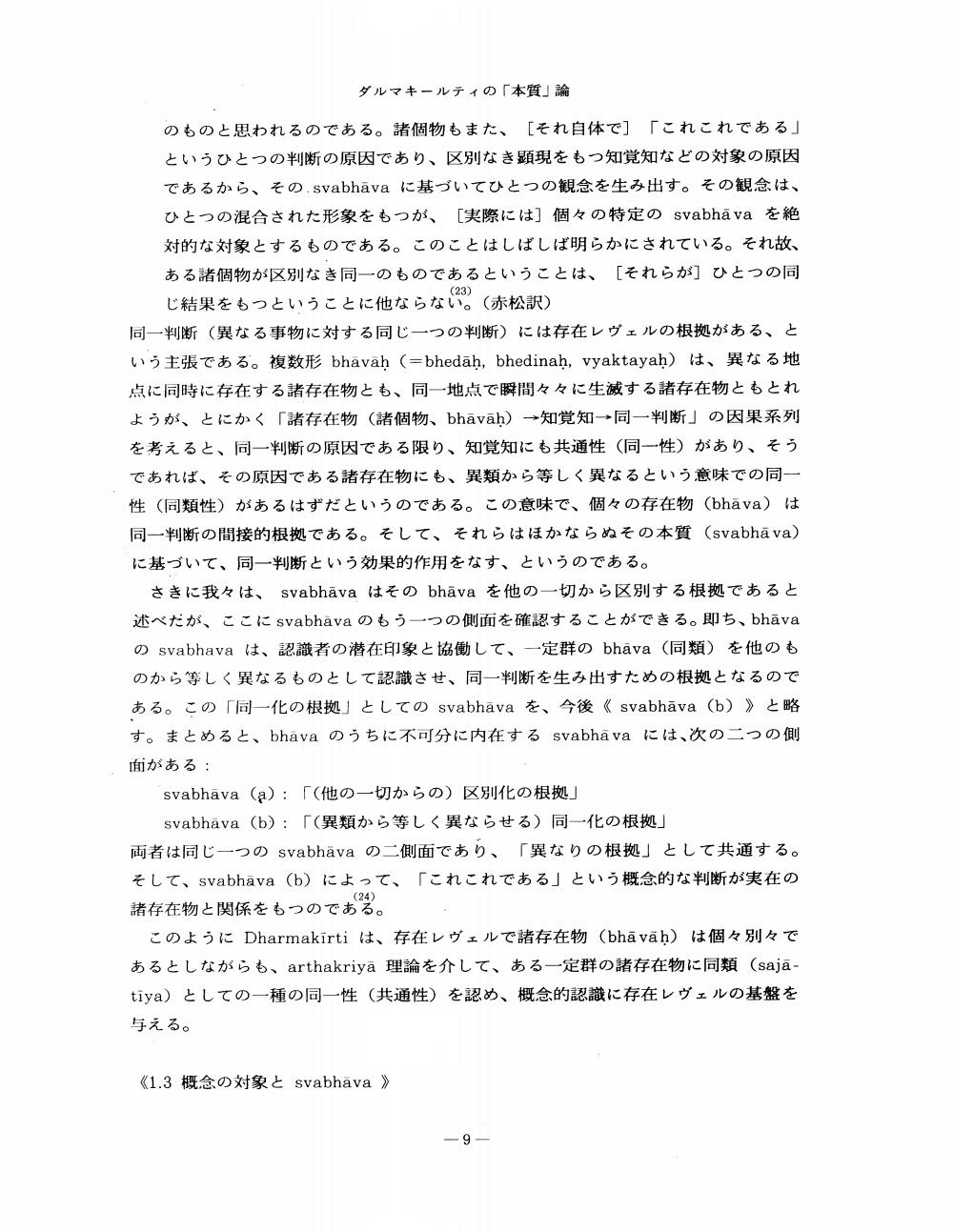
Page Navigation
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44