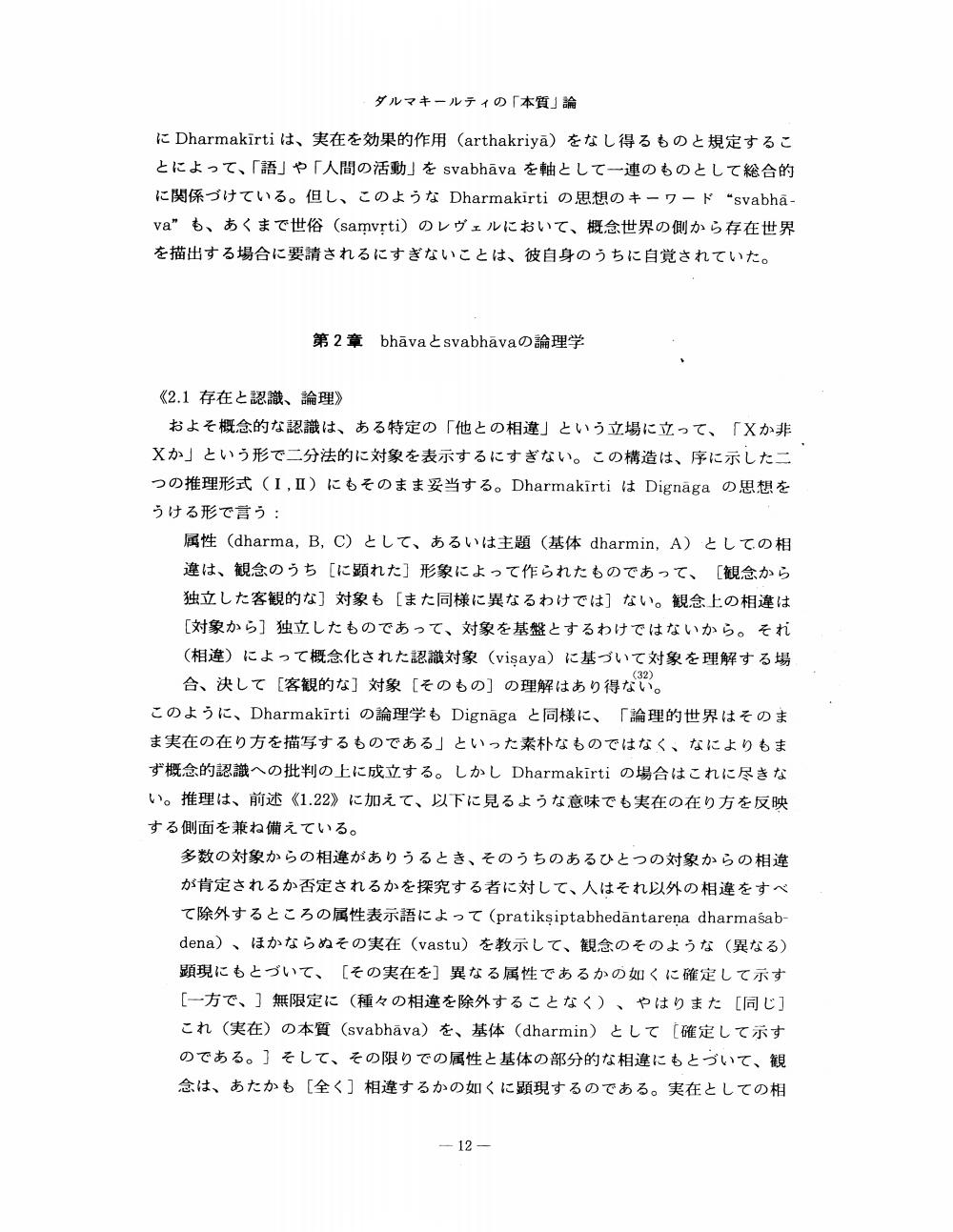Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 に Dharmakirti は、実在を効果的作用(arthakriyā)をなし得るものと規定するこ とによって、「語」や「人間の活動」を svabhava を軸として一連のものとして総合的 に関係づけている。但し、このような Dharmakirti の思想のキーワード "svabha - va" も、あくまで世俗(samvrti)のレヴェルにおいて、概念世界の側から存在世界 を描出する場合に要請されるにすぎないことは、彼自身のうちに自覚されていた。 第2章 bhāvaとsvabhavaの論理学 (32) <<2.1 存在と認識、論理》 およそ概念的な認識は、ある特定の「他との相違」という立場に立って、「Xか非 Xか」という形で二分法的に対象を表示するにすぎない。この構造は、序に示した二 つの推理形式 (I,)にもそのまま妥当する。Dharmakirti は Dignaga の思想を うける形で言う: 属性(dharma, B, C)として、あるいは主題(基体 dharmin, A)としての相 違は、観念のうち「に顕れた」形象によって作られたものであって、「観念から 独立した客観的な]対象も[また同様に異なるわけでは)ない。観念上の相違は [対象から] 独立したものであって、対象を基盤とするわけではないから。それ (相違)によって概念化された認識対象 (visaya) に基づいて対象を理解する場 合、決して客観的な]対象[そのもの]の理解はあり得ない。 このように、Dharmakirti の論理学も Dignaga と同様に、「論理的世界はそのま ま実在の在り方を描写するものである」といった素朴なものではなく、なによりもま ず概念的認識への批判の上に成立する。しかし Dharmakirti の場合はこれに尽きな い。推理は、前述《1.22》に加えて、以下に見るような意味でも実在の在り方を反映 する側面を兼ね備えている。 多数の対象からの相違がありうるとき、そのうちのあるひとつの対象からの相違 が肯定されるか否定されるかを探究する者に対して、人はそれ以外の相違をすべ て除外するところの属性表示語によって (pratiksiptabhedantarena dharmasabdena)、ほかならぬその実在 (vastu) を教示して、観念のそのような(異なる) 顕現にもとづいて、[その実在を]異なる属性であるかの如くに確定して示す [一方で、] 無限定に(種々の相違を除外することなく)、やはりまた「同じ] これ(実在)の本質 (svabhava) を、基体(dharmin)として「確定して示す のである。」そして、その限りでの属性と基体の部分的な相違にもとづいて、観 念は、あたかも[全く]相違するかの如くに顕現するのである。実在としての相 まま -12
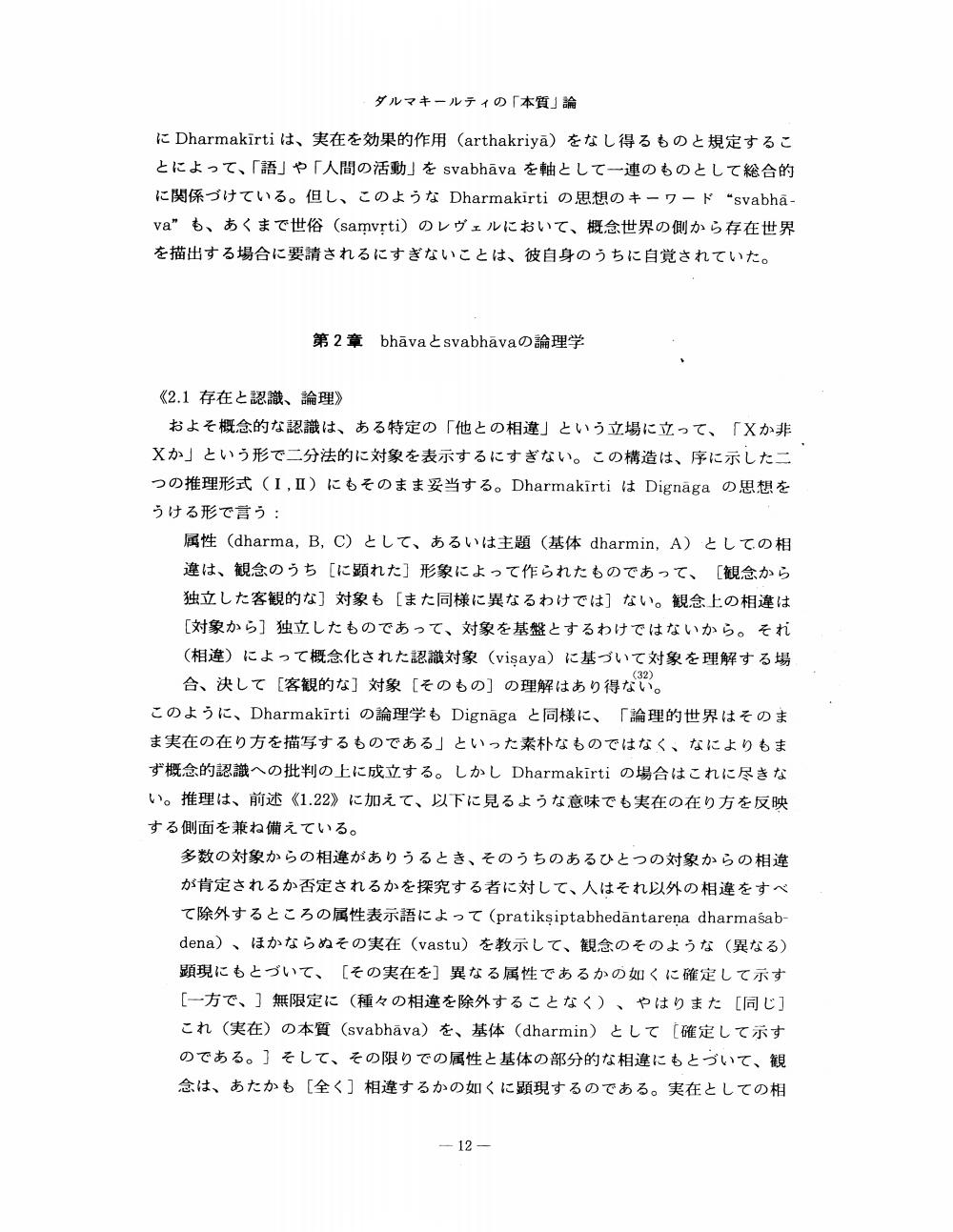
Page Navigation
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44