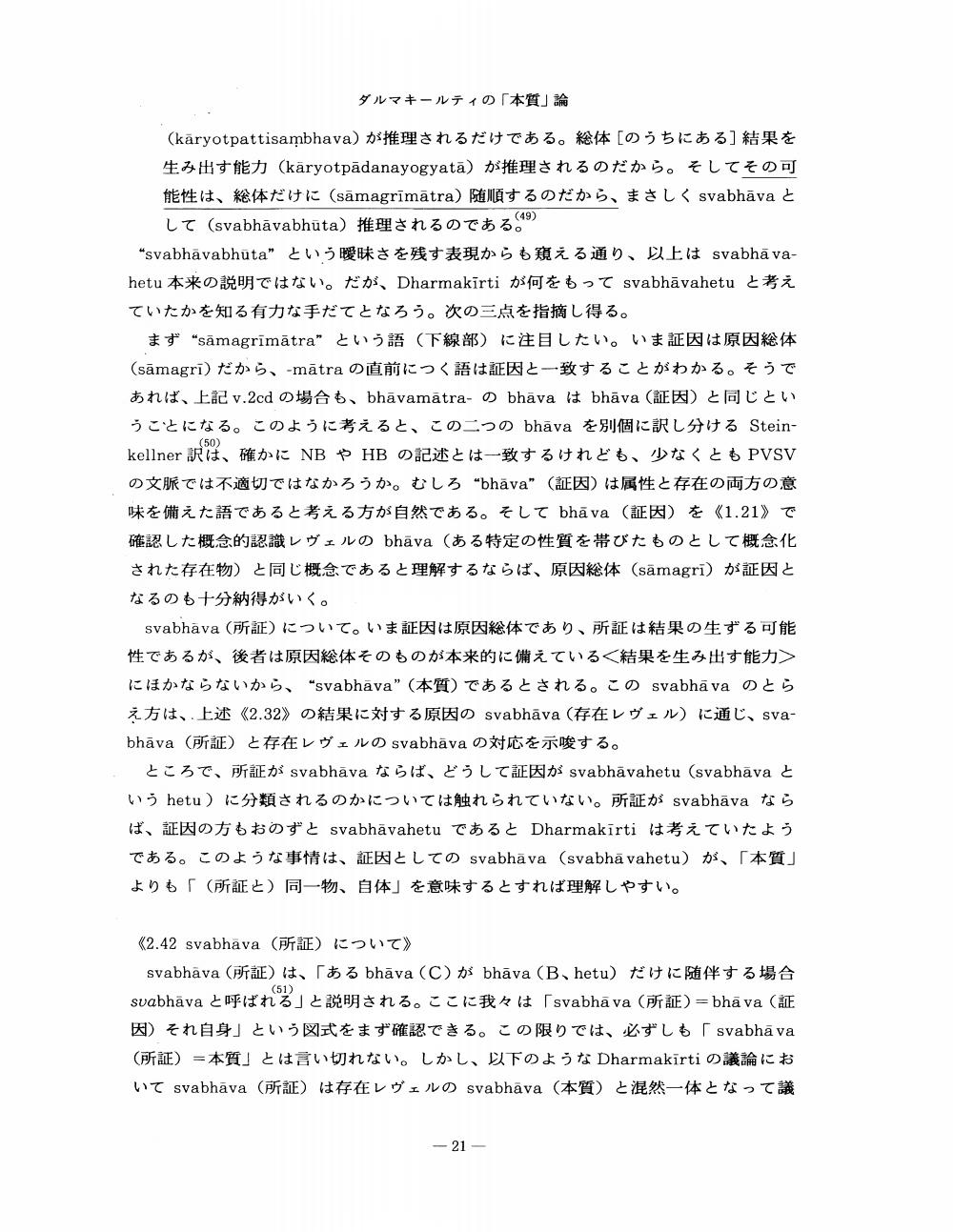Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 (50) (karyotpattisambhava) が推理されるだけである。総体「のうちにある] 結果を 生み出す能力 (karyotpadanayogyata) が推理されるのだから。そしてその可 能性は、総体だけに (samagrimatra) 随順するのだから、まさしく svabhava と して (svabhavabhuta) 推理されるのである。 "svabhavabhuta" という曖昧さを残す表現からも窺える通り、以上は svabhavahetu 本来の説明ではない。だが、Dharmakirti が何をもって svabhavahetu と考え ていたかを知る有力な手だてとなろう。次の三点を指摘し得る。 まず“samagrimatra" という語(下線部)に注目したい。いま証因は原因総体 (samagri) だから、-mātra の直前につく語は証因と一致することがわかる。そうで あれば、上記 v.2cd の場合も、bhāvamātra- の bhava は bhava (証因)と同じとい うことになる。このように考えると、この二つの bhava を別個に訳し分ける Steinkellner 訳は、確かに NB や HB の記述とは一致するけれども、少なくとも PVSV の文脈では不適切ではなかろうか。むしろ“bhava”(証因)は属性と存在の両方の意 味を備えた語であると考える方が自然である。そして bhava (証因)を《1.21》で 確認した概念的認識レヴェルの bhava (ある特定の性質を帯びたものとして概念化 された存在物)と同じ概念であると理解するならば、原因総体(samagri) が証因と なるのも十分納得がいく。 svabhava (所証)について。いま証因は原因総体であり、所証は結果の生ずる可能 性であるが、後者は原因総体そのものが本来的に備えている<結果を生み出す能力> にほかならないから、“svabhava”(本質)であるとされる。この svabhava のとら え方は、上述《2.32》の結果に対する原因の svabhava (存在レヴェル)に通じ、svabhava(所証)と存在レヴェルの svabhava の対応を示唆する。 * ところで、所証が svabhava ならば、どうして証因が svabhavahetu (svabhava と いう hetu)に分類されるのかについては触れられていない。所証が svabhava なら ば、証因の方もおのずと svabhavahetu であると Dharmakirti は考えていたよう である。このような事情は、証因としての svabhava (svabhavahetu)が、「本質」 よりも「(所証と)同一物、自体」を意味するとすれば理解しやすい。 (51) <<2.42 svabhava (所証)について》 svabhava(所証)は、「ある bhava(C) が bháva(B、hetu)だけに随伴する場合 suabhava と呼ばれる」と説明される。ここに我々は「svabhava (所証) = bhava(証 因)それ自身」という図式をまず確認できる。この限りでは、必ずしも「 svabhava (所証)=本質」とは言い切れない。しかし、以下のような Dharmakirti の議論にお いて svabhava (所証)は存在レヴェルの svabhava(本質)と混然一体となって議 - 21 -
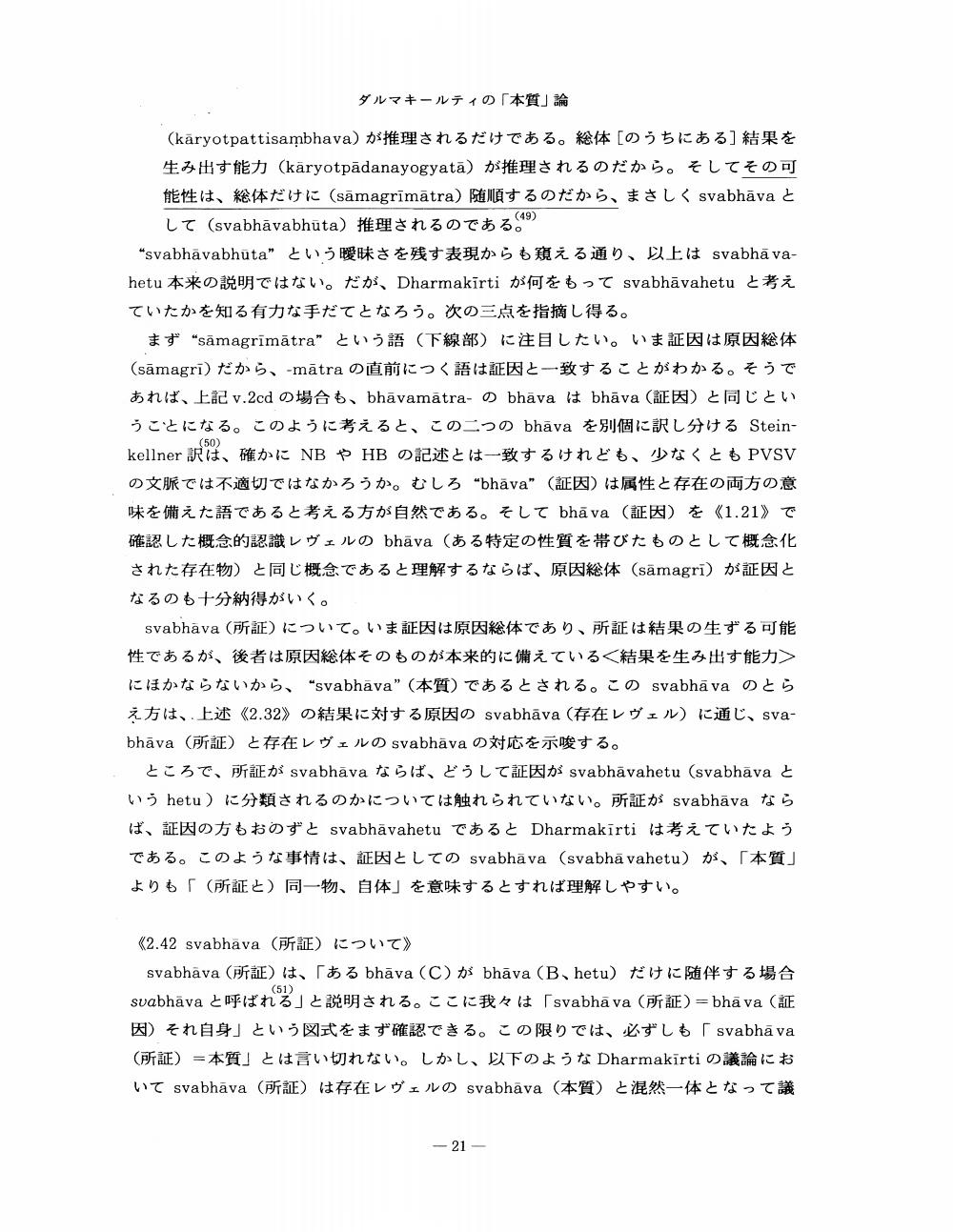
Page Navigation
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44