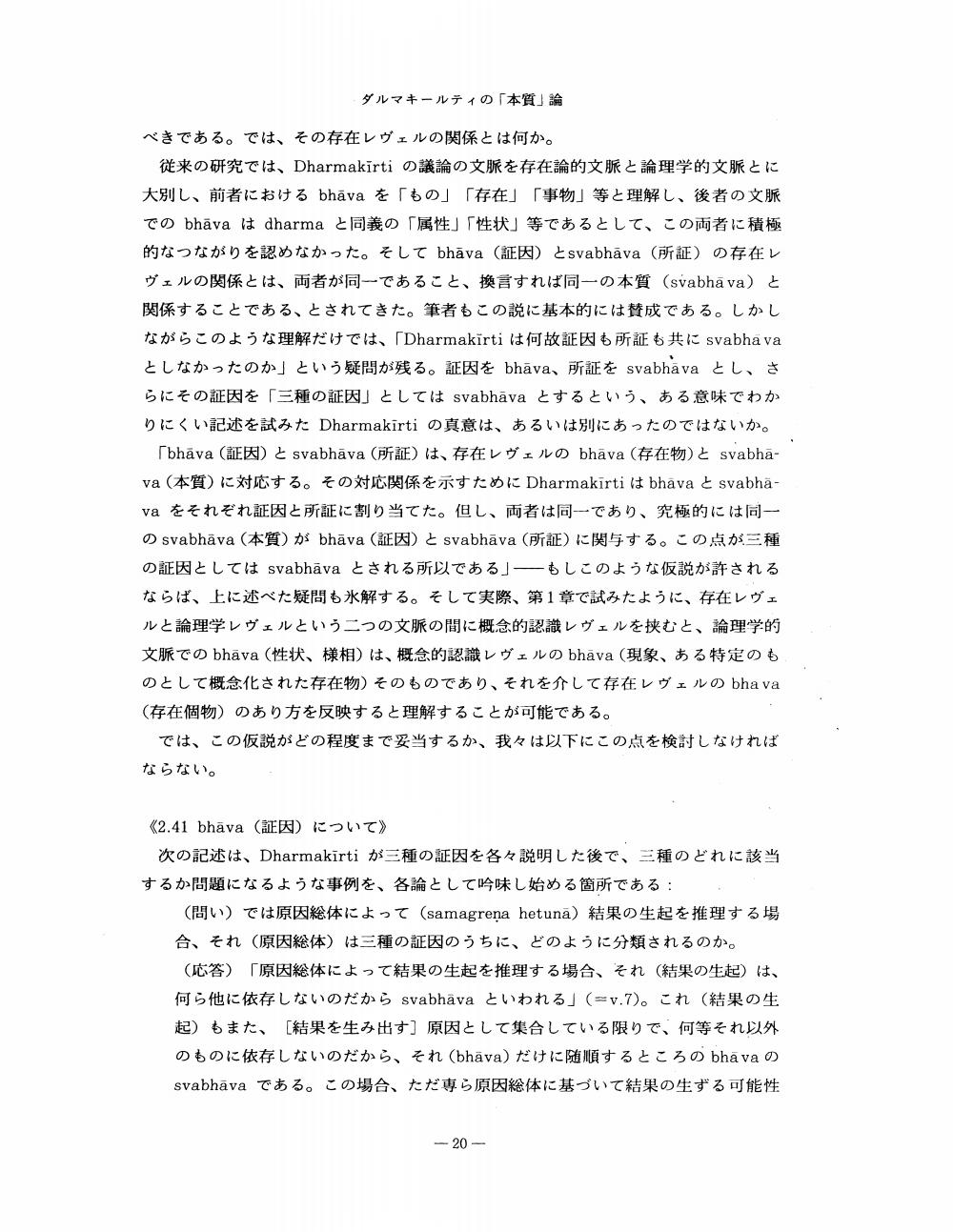Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 べきである。では、その存在レヴェルの関係とは何か。 従来の研究では、Dharmakirti の議論の文脈を存在論的文脈と論理学的文脈とに 大別し、前者における bhava を「もの」「存在」「事物」等と理解し、後者の文脈 での bhava は dharma と同義の「属性」「性状」等であるとして、この両者に積極 的なつながりを認めなかった。そして bhava(証因)とsvabhava(所証)の存在レ ヴェルの関係とは、両者が同一であること、換言すれば同一の本質 (svabha va) と 関係することである、とされてきた。筆者もこの説に基本的には賛成である。しかし ながらこのような理解だけでは、「Dharmakirti は何故証因も所証も共に svabhava としなかったのか」という疑問が残る。証因を bhava、所証を svabhava とし、さ らにその証因を「三種の証因」としては svabhava とするという、ある意味でわか りにくい記述を試みた Dharmakirti の真意は、あるいは別にあったのではないか。 [bhava (証因) と svabhava (所証)は、存在レヴェルの bhava(存在物)と svabhava (本質)に対応する。その対応関係を示すために Dharmakirti は bhava と svabhava をそれぞれ証因と所証に割り当てた。但し、両者は同一であり、究極的には同一 の svabhava (本質)が bhava(証因) と svabhava (所証)に関与する。この点が三種 の証因としては svabhava とされる所以である」――もしこのような仮説が許される ならば、上に述べた疑問も氷解する。そして実際、第1章で試みたように、存在レヴェ ルと論理学レヴェルという二つの文脈の間に概念的認識レヴェルを挟むと、論理学的 文脈での bhava (性状、様相)は、概念的認識レヴェルの bhava (現象、ある特定のも。 のとして概念化された存在物)そのものであり、それを介して存在レヴェルの bhava (存在個物)のあり方を反映すると理解することが可能である。 では、この仮説がどの程度まで妥当するか、我々は以下にこの点を検討しなければ ならない。 <<2.41 bhava(証因)について》 次の記述は、Dharmakirti が三種の証因を各々説明した後で、三種のどれに該当 するか問題になるような事例を、各論として吟味し始める箇所である: (問い)では原因総体によって(samagrena hetuna) 結果の生起を推理する場 合、それ(原因総体)は三種の証因のうちに、どのように分類されるのか。 (応答)「原因総体によって結果の生起を推理する場合、それ(結果の生起)は、 何ら他に依存しないのだから svabhava といわれる」(=v.7)。これ(結果の生 起)もまた、「結果を生み出す]原因として集合している限りで、何等それ以外 のものに依存しないのだから、それ (bhava) だけに随順するところの bhava の svabhava である。この場合、ただ専ら原因総体に基づいて結果の生ずる可能性 -20
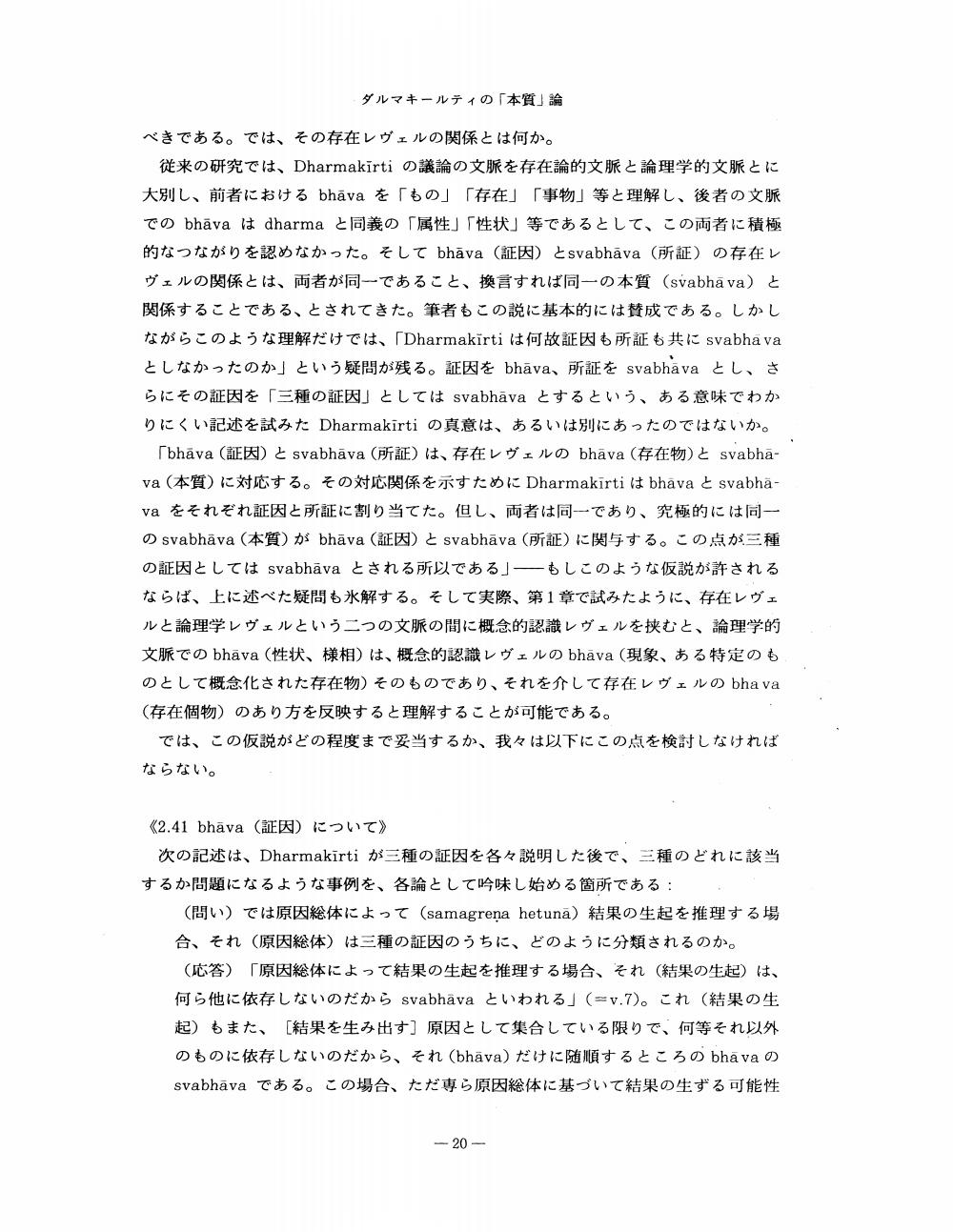
Page Navigation
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44