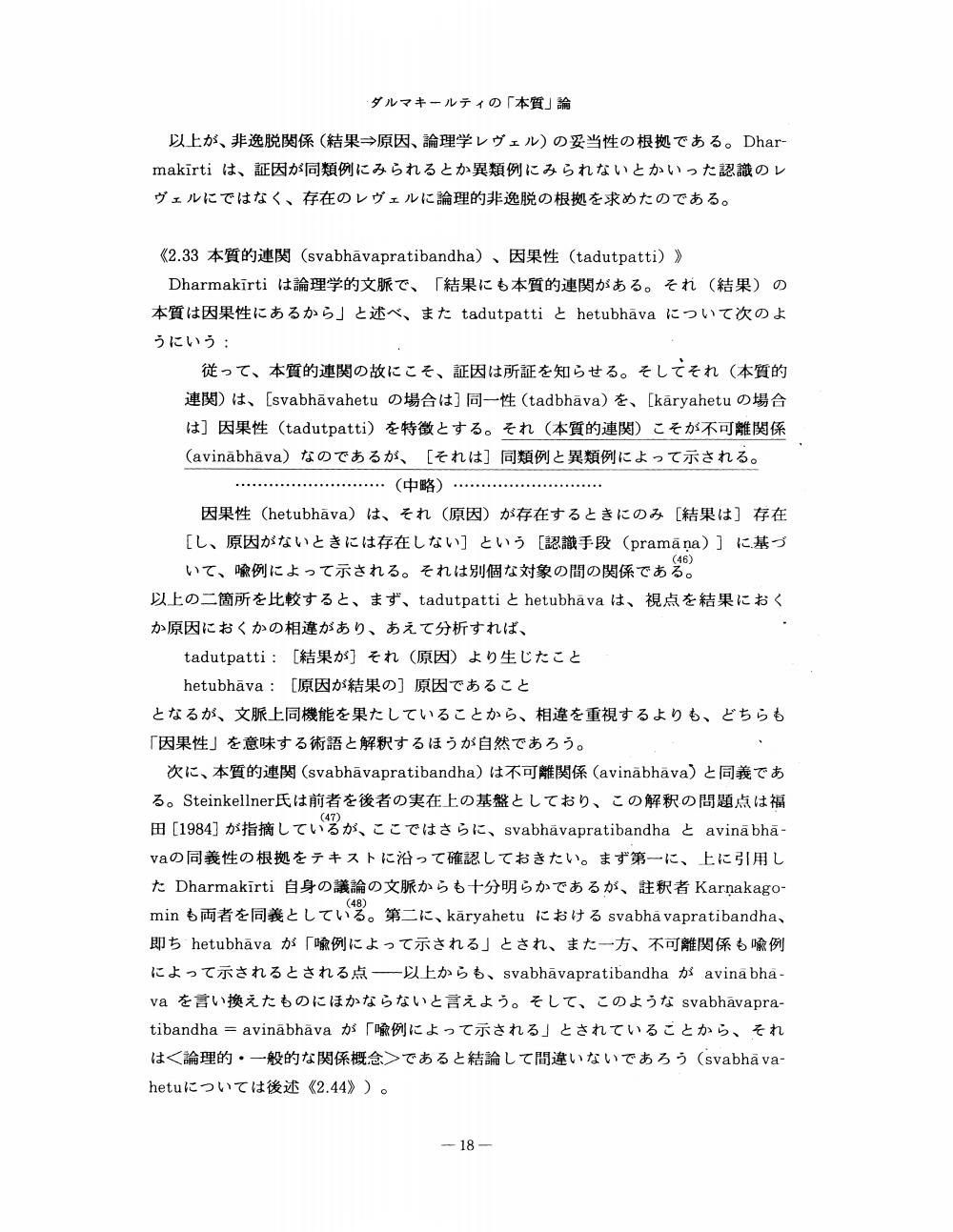Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 以上が、非逸脱関係(結果⇒原因、論理学レヴェル)の妥当性の根拠である。Dharmakirti は、証因が同類例にみられるとか異類例にみられないとかいった認識のレ ヴェルにではなく、存在のレヴェルに論理的非逸脱の根拠を求めたのである。 (46) <<2.33 本質的連関 (svabhavapratibandha)、因果性 (tadutpatti) >> Dharmakirti は論理学的文脈で、「結果にも本質的連関がある。それ(結果)の 本質は因果性にあるから」と述べ、また tadutpatti と hetubhava について次のよ うにいう: 従って、本質的連関の故にこそ、証因は所証を知らせる。そしてそれ(本質的 連関)は、 [svabhavahetu の場合は] 同一性 (tadbhava) を、[karyahetu の場合 は] 因果性 (tadutpatti) を特徴とする。それ(本質的連関)こそが不可離関係 (avinabhava) なのであるが、「それは]同類例と異類例によって示される。 ...(中略) ........... 因果性 (hetubhava)は、それ(原因)が存在するときにのみ「結果は]存在 [し、原因がないときには存在しない」という「認識手段(pramána)] に基づ いて、喩例によって示される。それは別個な対象の間の関係である。 以上の二箇所を比較すると、まず、tadutpatti と hetubhava は、視点を結果におく か原因におくかの相違があり、あえて分析すれば、 tadutpatti: [結果が]それ(原因)より生じたこと hetubhava: [原因が結果の]原因であること となるが、文脈上同機能を果たしていることから、相違を重視するよりも、どちらも 「因果性」を意味する術語と解釈するほうが自然であろう。 次に、本質的連関 (svabhavapratibandha) は不可離関係 (avinabhava) と同義であ る。Steinkellner氏は前者を後者の実在上の基盤としており、この解釈の問題点は福 田 [1984] が指摘しているが、ここではさらに、svabhavapratibandha と avina bhavaの同義性の根拠をテキストに沿って確認しておきたい。まず第一に、上に引用し た Dharmakirti 自身の議論の文脈からも十分明らかであるが、註釈者 Karnakagomin も両者を同義としている。第二に、karyahetu における svabha vapratibandha, 即ち hetubhava が「喩例によって示される」とされ、また一方、不可離関係も喩例 によって示されるとされる点一以上からも、svabhavapratibandha が avina bhava を言い換えたものにほかならないと言えよう。そして、このような svabhavapratibandha = avinabhava が「喩例によって示される」とされていることから、それ は<論理的・一般的な関係概念>であると結論して間違いないであろう (svabhávahetuについては後述《2.44》)。 -18
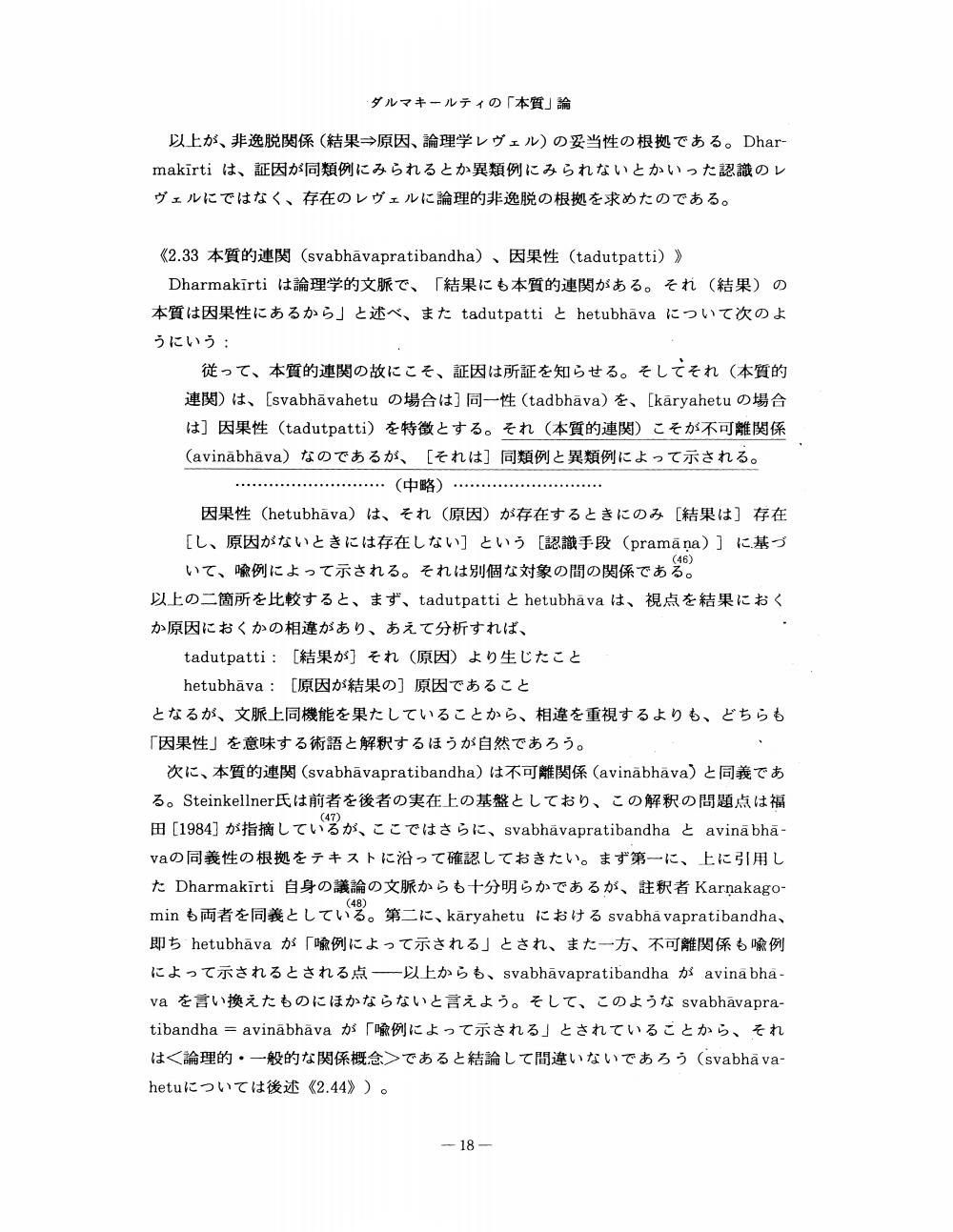
Page Navigation
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44