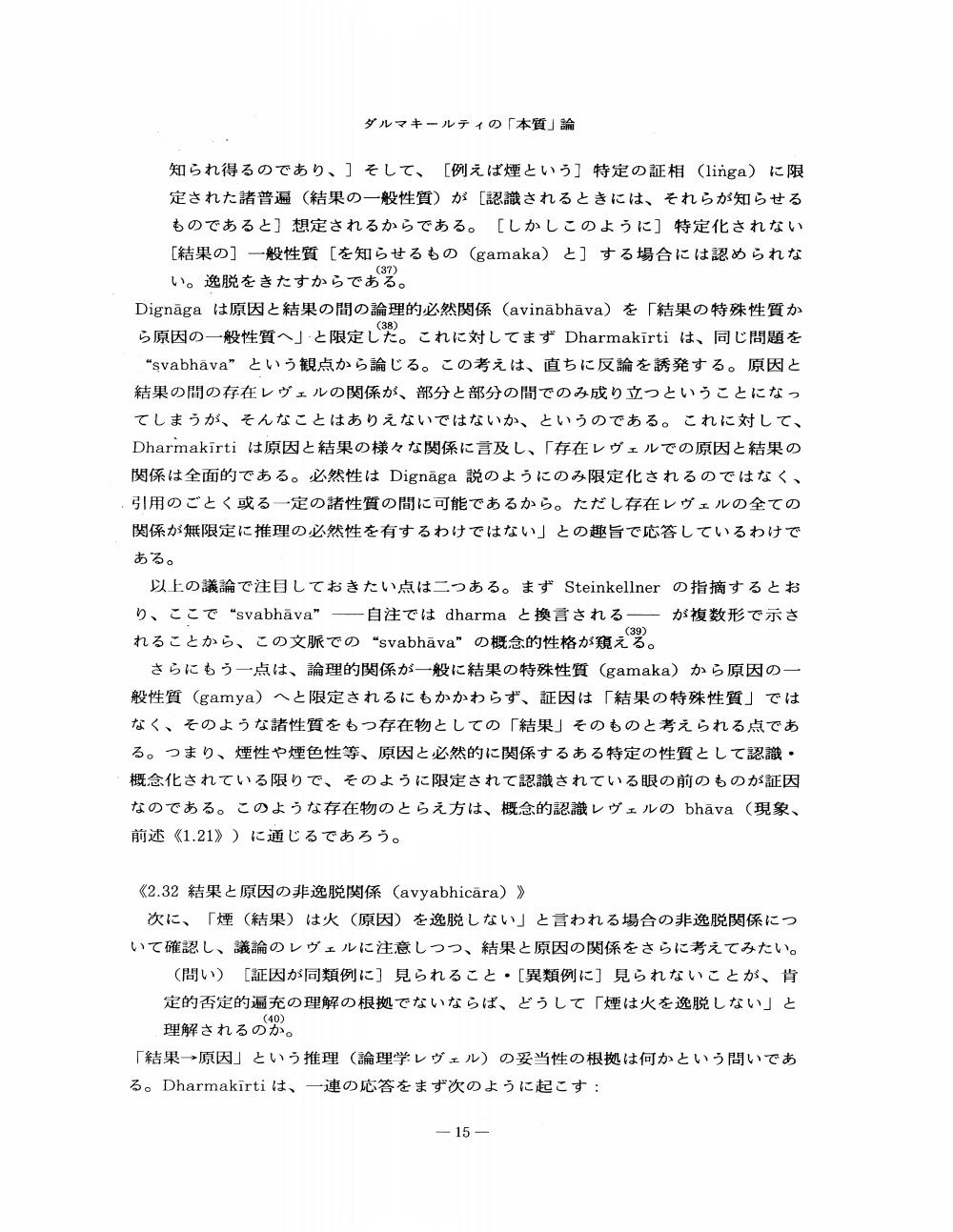Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 知られ得るのであり、] そして、「例えば煙という]特定の証相(linga) に限 定された諸普遍(結果の一般性質)が「認識されるときには、それらが知らせる ものであると] 想定されるからである。「しかしこのように] 特定化されない [結果の] 一般性質[を知らせるもの(gamaka)と]する場合には認められな い。逸脱をきたすからである。 Dignaga は原因と結果の間の論理的必然関係(avinabhava) を「結果の特殊性質か ら原因の一般性質へ」と限定した。これに対してまず Dharmakirti は、同じ問題を "svabhava" という観点から論じる。この考えは、直ちに反論を誘発する。原因と 結果の間の存在レヴェルの関係が、部分と部分の間でのみ成り立つということになっ てしまうが、そんなことはありえないではないか、というのである。これに対して、 Dharmakirti は原因と結果の様々な関係に言及し、「存在レヴェルでの原因と結果の 関係は全面的である。必然性は Dignaga 説のようにのみ限定化されるのではなく、 引用のごとく或る一定の諸性質の間に可能であるから。ただし存在レヴェルの全ての 関係が無限定に推理の必然性を有するわけではない」との趣旨で応答しているわけで ある。 以上の議論で注目しておきたい点は二つある。まず Steinkellner の指摘するとお り、ここで "svabhava" ——自注では dharma と換言される―― が複数形で示さ れることから、この文脈での“svabhava” の概念的性格が窺える。 さらにもう一点は、論理的関係が一般に結果の特殊性質(gamaka)から原因の一 般性質(gamya)へと限定されるにもかかわらず、証因は「結果の特殊性質」では なく、そのような諸性質をもつ存在物としての「結果」そのものと考えられる点であ る。つまり、煙性や煙色性等、原因と必然的に関係するある特定の性質として認識・ 概念化されている限りで、そのように限定されて認識されている眼の前のものが証因 なのである。このような存在物のとらえ方は、概念的認識レヴェルの bhava (現象、 前述《1.21》)に通じるであろう。 <<2.32 結果と原因の非逸脱関係 (avyabhicara)>> 次に、「煙(結果)は火(原因)を逸脱しない」と言われる場合の非逸脱関係につ いて確認し、議論のレヴェルに注意しつつ、結果と原因の関係をさらに考えてみたい。 (問い) [証因が同類例に]見られること・異類例に]見られないことが、肯 定的否定的遍充の理解の根拠でないならば、どうして「煙は火を逸脱しない」と 理解されるのか。 「結果→原因」という推理(論理学レヴェル)の妥当性の根拠は何かという問いであ る。Dharmakirti は、一連の応答をまず次のように起こす: (40) -15
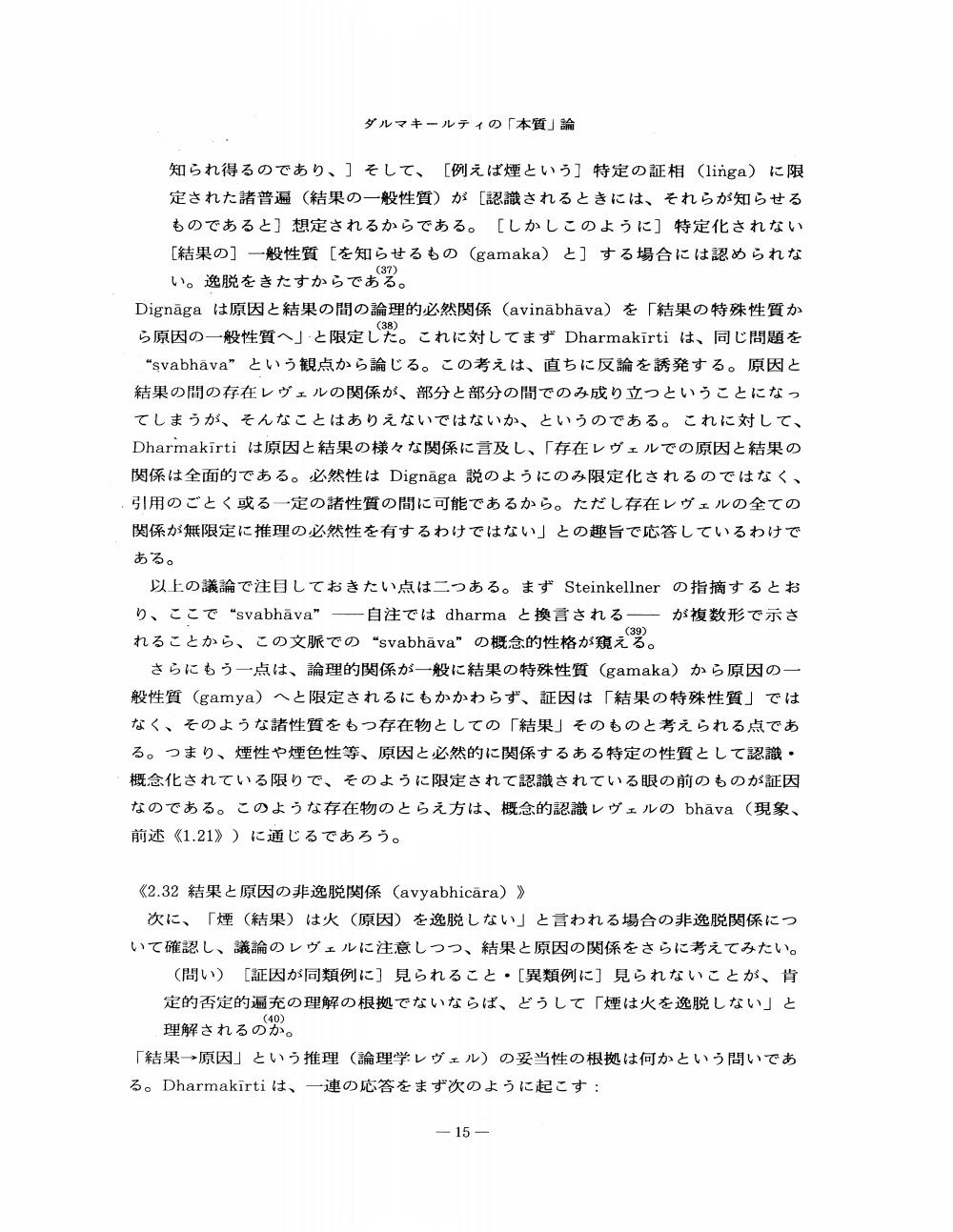
Page Navigation
1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44