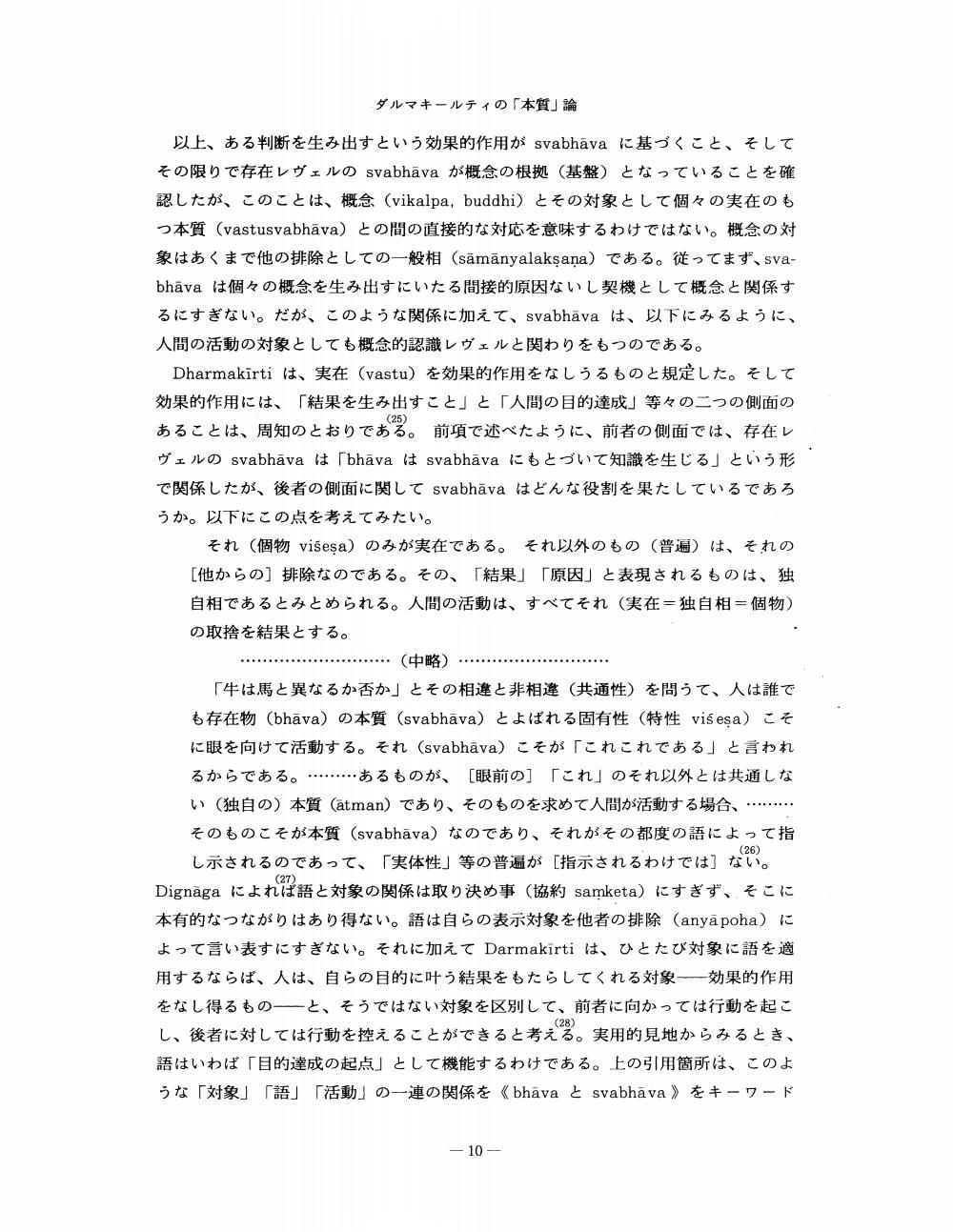Book Title: Bhava And Svabhava
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ダルマキールティの「本質」論 以上、ある判断を生み出すという効果的作用が svabhava に基づくこと、そして その限りで存在レヴェルの svabhava が概念の根拠(基盤)となっていることを確 認したが、このことは、概念 (vikalpa, buddhi)とその対象として個々の実在のも つ本質 (vastusvabhava)との間の直接的な対応を意味するわけではない。概念の対 象はあくまで他の排除としての一般相(samanyalaksana) である。従ってまず、svabhava は個々の概念を生み出すにいたる間接的原因ないし契機として概念と関係す るにすぎない。だが、このような関係に加えて、svabhava は、以下にみるように、 人間の活動の対象としても概念的認識レヴェルと関わりをもつのである。 Dharmakirti は、実在 (vastu) を効果的作用をなしうるものと規定した。そして 効果的作用には、「結果を生み出すこと」と「人間の目的達成」等々の二つの側面の あることは、周知のとおりである。 前項で述べたように、前者の側面では、存在し ヴェルの svabhava は「bhava は svabhava にもとづいて知識を生じる」という形 で関係したが、後者の側面に関して svabhava はどんな役割を果たしているであろ うか。以下にこの点を考えてみたい。 それ(個物 visesa) のみが実在である。 それ以外のもの(普遍)は、それの [他からの]排除なのである。その、「結果」「原因」と表現されるものは、独 自相であるとみとめられる。人間の活動は、すべてそれ(実在=独自相=個物) の取捨を結果とする。 .........(中略) ...... 「牛は馬と異なるか否か」とその相違と非相違(共通性)を問うて、人は誰で も存在物(bhava)の本質 (svabhāva)とよばれる固有性(特性 visesa)こそ に眼を向けて活動する。それ(svabhava)こそが「これこれである」と言われ るからである。 ......あるものが、「眼前の]「これ」のそれ以外とは共通しな い(独自の) 本質 (atman) であり、そのものを求めて人間が活動する場合、......... そのものこそが本質 (svabhava) なのであり、それがその都度の語によって指 し示されるのであって、「実体性」等の普遍が「指示されるわけでは」ない。 Dignaga によれば語と対象の関係は取り決め事(協約 samketa) にすぎず、そこに 本有的なつながりはあり得ない。語は自らの表示対象を他者の排除(anyapoha)に よって言い表すにすぎない。それに加えて Darmakirti は、ひとたび対象に語を適 用するならば、人は、自らの目的に叶う結果をもたらしてくれる対象——効果的作用 をなし得るものと、そうではない対象を区別して、前者に向かっては行動を起こ し、後者に対しては行動を控えることができると考える。実用的見地からみるとき、 語はいわば「目的達成の起点」として機能するわけである。上の引用箇所は、このよ うな「対象」「語」「活動」の一連の関係を《bhava と svabhava》をキーワード ( -10
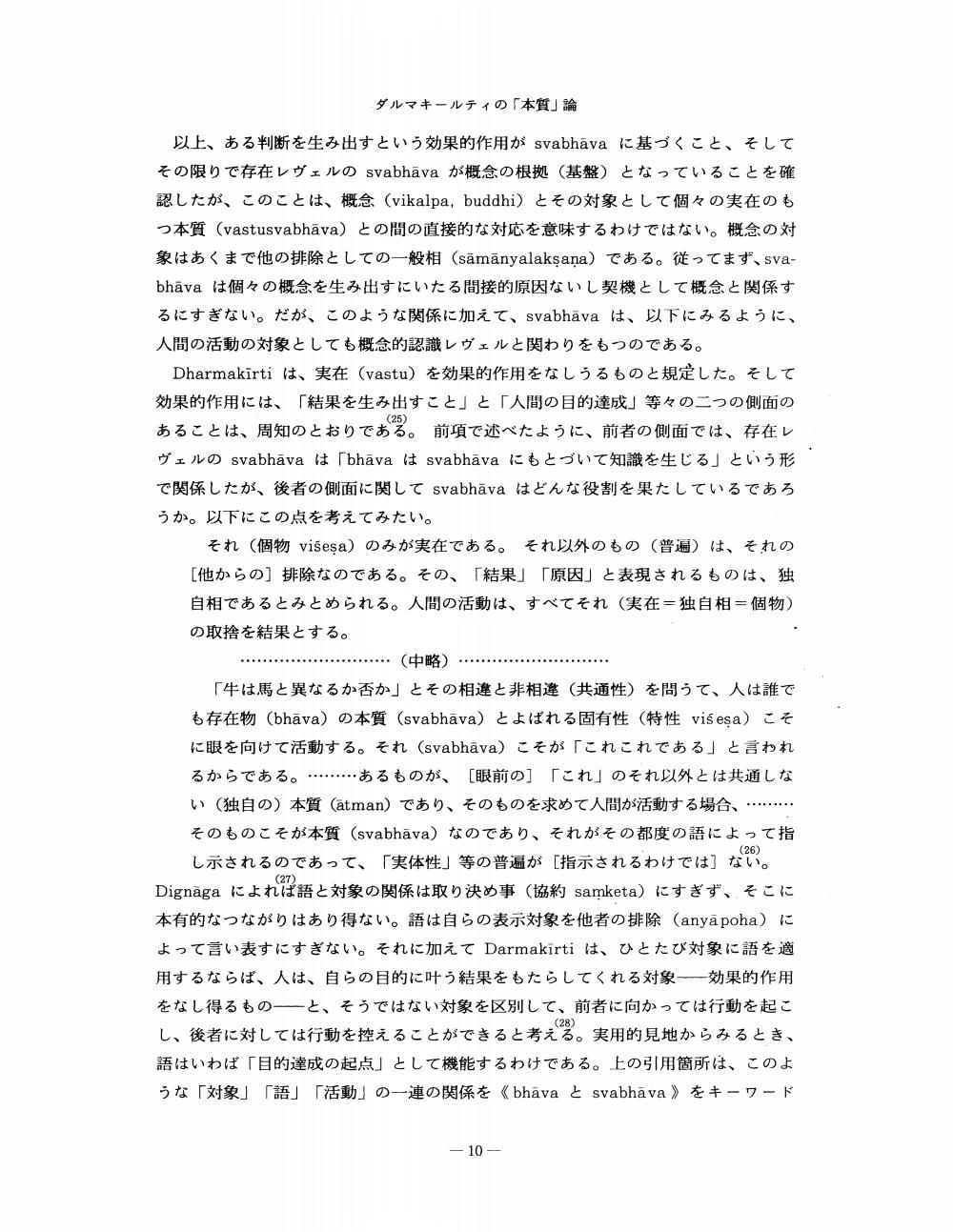
Page Navigation
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44