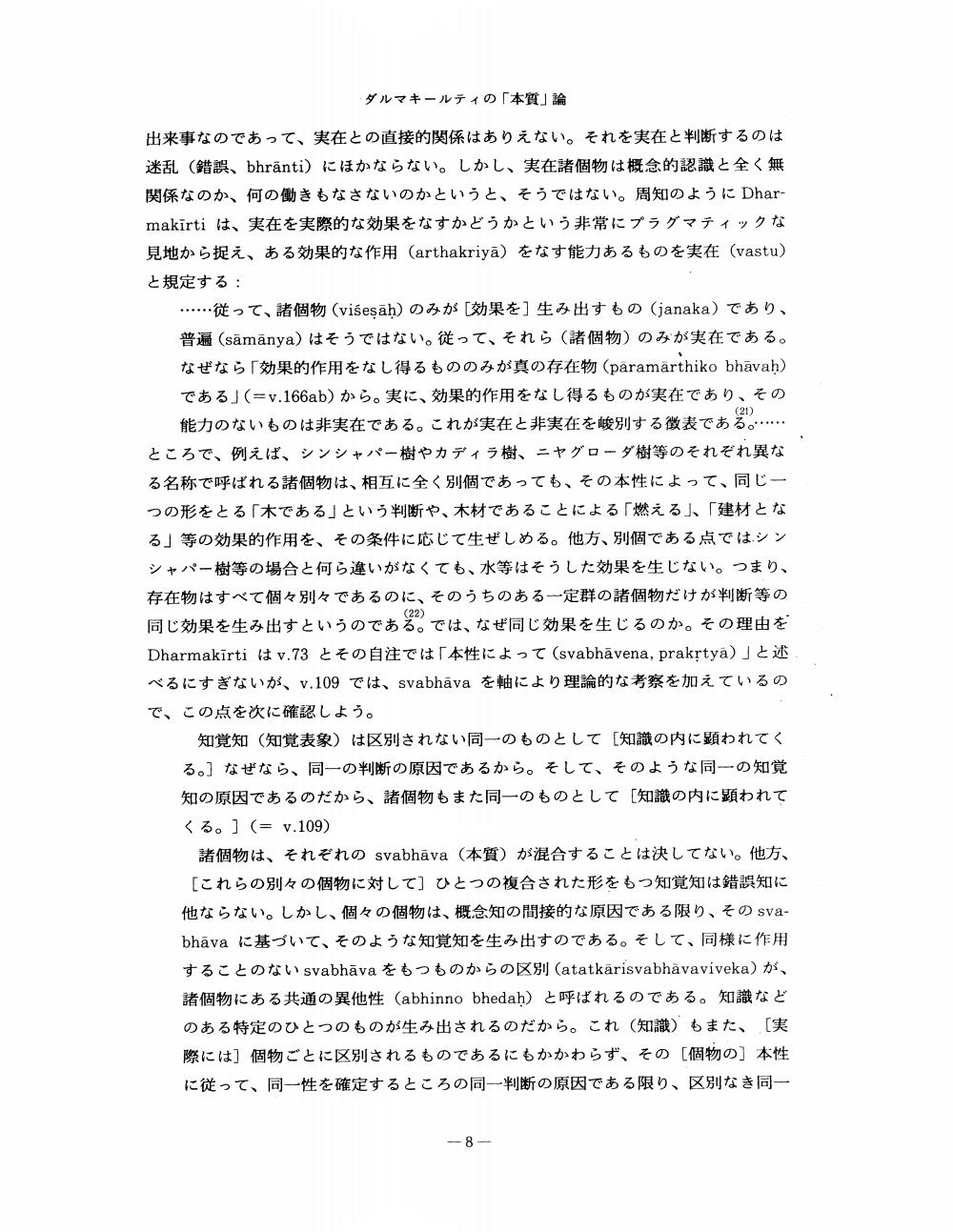Book Title: Bhava And Svabhava Author(s): Publisher: View full book textPage 9
________________ ダルマキールティの「本質」論 出来事なのであって、実在との直接的関係はありえない。それを実在と判断するのは 迷乱(錯誤、bhranti) にほかならない。しかし、実在諸個物は概念的認識と全く無 関係なのか、何の働きもなさないのかというと、そうではない。周知のように Dharmakirti は、実在を実際的な効果をなすかどうかという非常にプラグマティックな 見地から捉え、ある効果的な作用 (arthakriyā)をなす能力あるものを実在(vastu) と規定する: ......従って、諸個物(visesah) のみが「効果を]生み出すもの (janaka) であり、 普遍 (samanya) はそうではない。従って、それら(諸個物)のみが実在である。 なぜなら「効果的作用をなし得るもののみが真の存在物 (paramarthiko bhavah) である」(=v.166ab)から。実に、効果的作用をなし得るものが実在であり、その 能力のないものは非実在である。これが実在と非実在を峻別する徴表である。...... ところで、例えば、シンシャパー樹やカディラ樹、ニヤグローダ樹等のそれぞれ異な る名称で呼ばれる諸個物は、相互に全く別個であっても、その本性によって、同じ一 つの形をとる「木である」という判断や、木材であることによる「燃える」、「建材とな る」等の効果的作用を、その条件に応じて生ぜしめる。他方、別個である点では、シン シャパー樹等の場合と何ら違いがなくても、水等はそうした効果を生じない。つまり、 存在物はすべて個々別々であるのに、そのうちのある一定群の諸個物だけが判断等の 同じ効果を生み出すというのである。では、なぜ同じ効果を生じるのか。その理由を Dharmakirti は v.73 とその自注では「本性によって (svabhavena, prakrtya)」と述 べるにすぎないが、v.109 では、svabhava を軸により理論的な考察を加えているの で、この点を次に確認しよう。 知覚知(知覚表象)は区別されない同一のものとして「知識の内に顕われてく る。]なぜなら、同一の判断の原因であるから。そして、そのような同一の知覚 知の原因であるのだから、諸個物もまた同一のものとして「知識の内に顕われて くる。] (= v.109) 諸個物は、それぞれの svabhava(本質)が混合することは決してない。他方、 [これらの別々の個物に対して]ひとつの複合された形をもつ知覚知は錯誤知に 他ならない。しかし、個々の個物は、概念知の間接的な原因である限り、その svabhava に基づいて、そのような知覚知を生み出すのである。そして、同様に作用 することのない svabhava をもつものからの区別 (atatkarisvabhavaviveka) が、 諸個物にある共通の異他性(abhinno bhedah)と呼ばれるのである。知識など のある特定のひとつのものが生み出されるのだから。これ(知識)もまた、[実 際には]個物ごとに区別されるものであるにもかかわらず、その「個物の]本性 に従って、同一性を確定するところの同一判断の原因である限り、区別なき同一 -8Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44