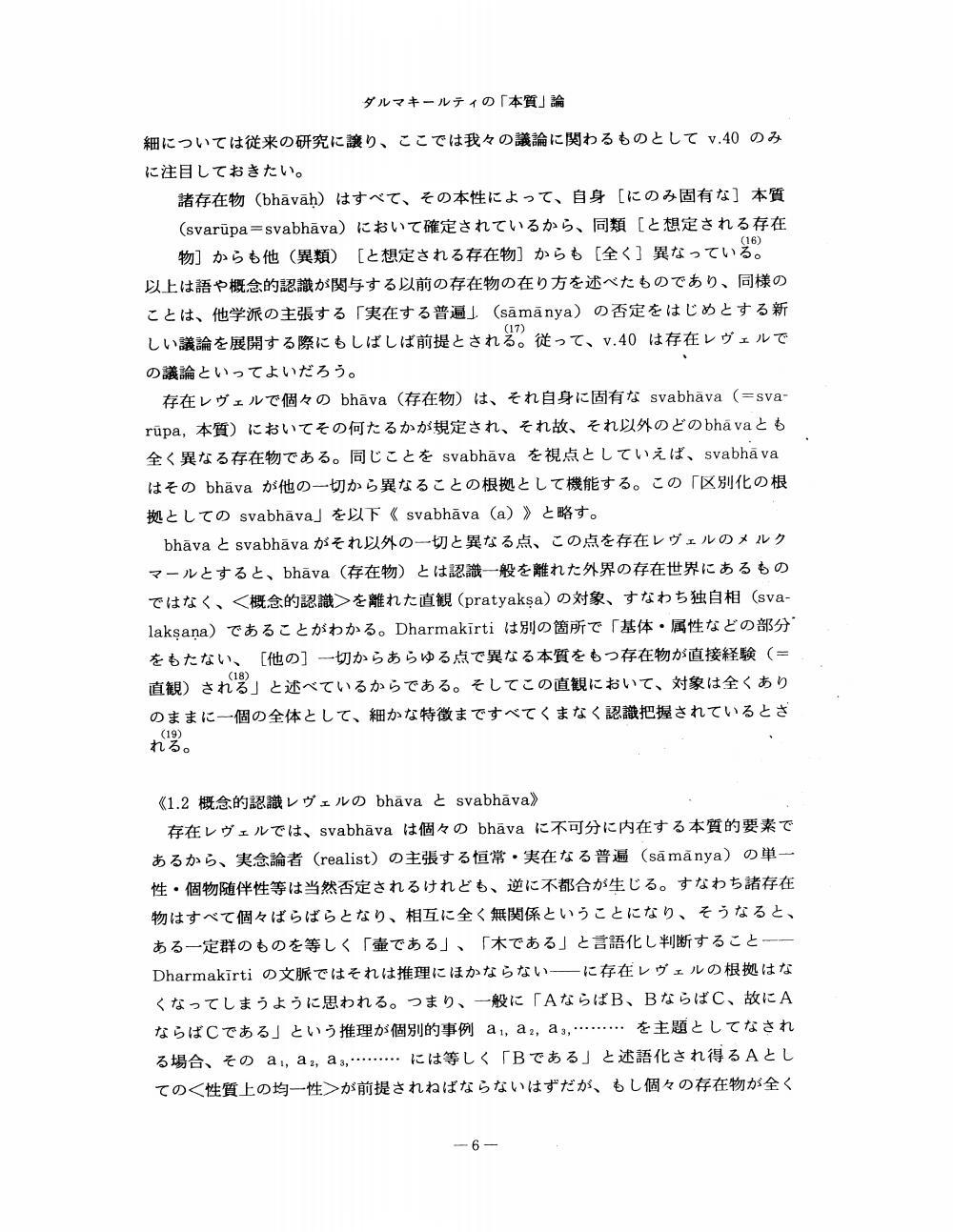Book Title: Bhava And Svabhava Author(s): Publisher: View full book textPage 7
________________ ダルマキールティの「本質」論 細については従来の研究に譲り、ここでは我々の議論に関わるものとして v.40 のみ に注目しておきたい。 諸存在物(bháváh)はすべて、その本性によって、自身[にのみ固有な]本質 (svarupa =svabhava)において確定されているから、同類 [と想定される存在 物]からも他(異類)[と想定される存在物]からも全く] 異なっている。 以上は語や概念的認識が関与する以前の存在物の在り方を述べたものであり、同様の ことは、他学派の主張する「実在する普遍」(samanya) の否定をはじめとする新 しい議論を展開する際にもしばしば前提とされる。従って、v.40 は存在レヴェルで の議論といってよいだろう。 存在レヴェルで個々の bhava (存在物)は、それ自身に固有な svabhava (=svarupa, 本質)においてその何たるかが規定され、それ故、それ以外のどのbhavaとも 全く異なる存在物である。同じことを svabhava を視点としていえば、syabha va はその bhava が他の一切から異なることの根拠として機能する。この「区別化の根 拠としての svabhava」を以下《 svabhava (a)》と略す。 bhava と svabhava がそれ以外の一切と異なる点、この点を存在レヴェルのメルク マールとすると、bhava(存在物)とは認識一般を離れた外界の存在世界にあるもの ではなく、<概念的認識>を離れた直観 (pratyaksa) の対象、すなわち独自相 (svalaksana) であることがわかる。Dharmakirti は別の箇所で「基体・属性などの部分 をもたない、[他の]一切からあらゆる点で異なる本質をもつ存在物が直接経験(= 直観)される」と述べているからである。そしてこの直観において、対象は全くあり のままに一個の全体として、細かな特徴まですべてくまなく認識把握されているとさ れる。 <<1.2 概念的認識レヴェルの bhava と syabhava>> 存在レヴェルでは、svabhava は個々の bhava に不可分に内在する本質的要素で あるから、実念論者 (realist) の主張する恒常・実在なる普遍(samanya) の単一 性・個物随伴性等は当然否定されるけれども、逆に不都合が生じる。すなわち諸存在 物はすべて個々ばらばらとなり、相互に全く無関係ということになり、そうなると、 ある一定群のものを等しく「壷である」、「木である」と言語化し判断すること一一 Dharmakirti の文脈ではそれは推理にほかならない一に存在レヴェルの根拠はな くなってしまうように思われる。つまり、一般に「AならばB、BならばC、故にA ならばCである」という推理が個別的事例 ai, az, as, ...... を主題としてなされ る場合、その a1, aa, as,......... には等しく「Bである」と述語化され得るAとし ての<性質上の均一性>が前提されねばならないはずだが、もし個々の存在物が全く -6Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44