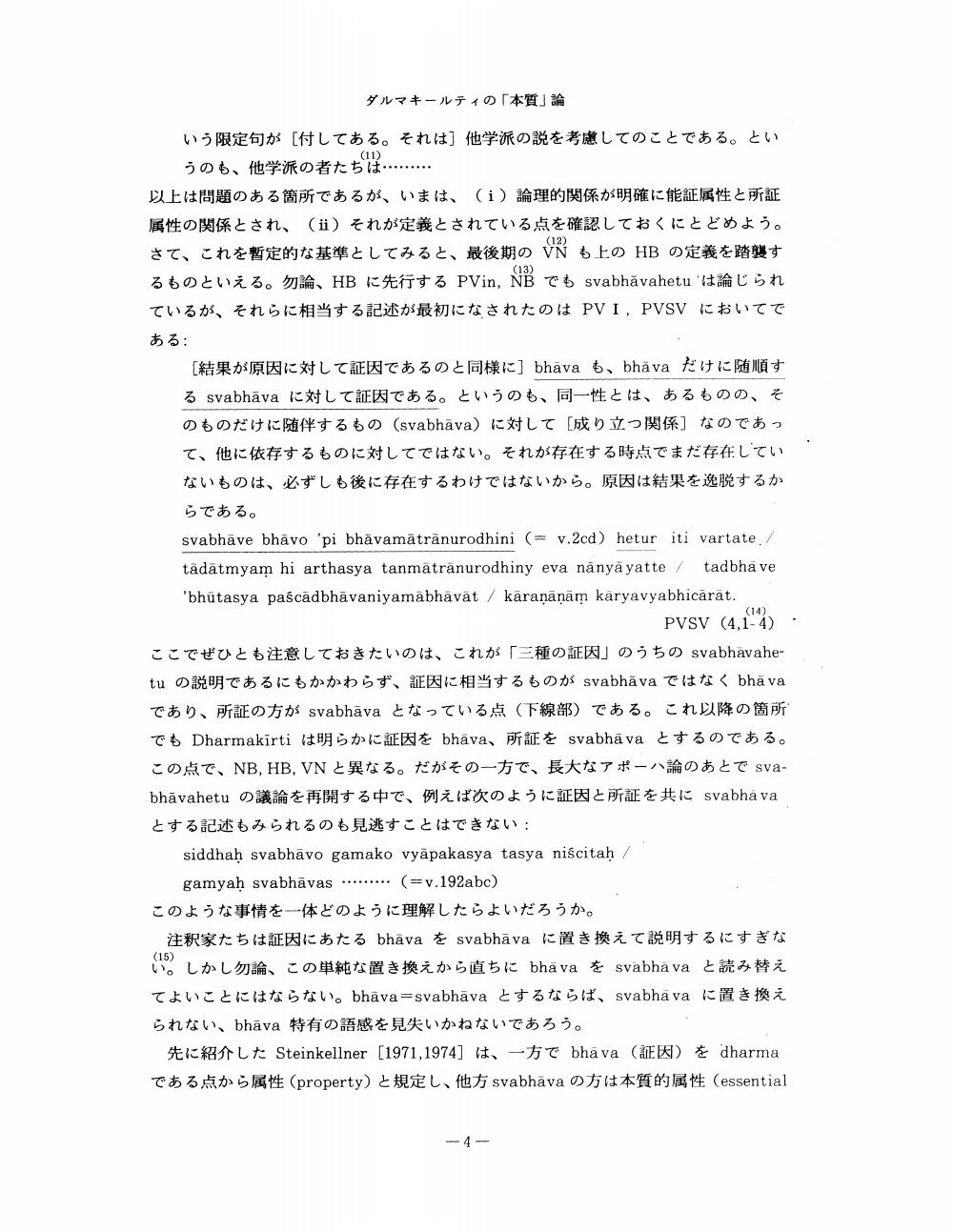Book Title: Bhava And Svabhava Author(s): Publisher: View full book textPage 5
________________ ダルマキールティの「本質」論 (12) いう限定句が「付してある。それは]他学派の説を考慮してのことである。とい うのも、他学派の者たちは...... 以上は問題のある箇所であるが、いまは、(i) 論理的関係が明確に能証属性と所証 属性の関係とされ、(i) それが定義とされている点を確認しておくにとどめよう。 さて、これを暫定的な基準としてみると、最後期の VN も上の HB の定義を踏襲す るものといえる。勿論、HB に先行する PVin, NB でも svabhavahetuは論じられ ているが、それらに相当する記述が最初になされたのは PV I, PVSV においてで ある: [結果が原因に対して証因であるのと同様に] bhava も、bháva だけに随順す る svabhava に対して証因である。というのも、同一性とは、あるものの、そ のものだけに随伴するもの (svabhava)に対して成り立つ関係]なのであっ て、他に依存するものに対してではない。それが存在する時点でまだ存在してい ないものは、必ずしも後に存在するわけではないから。原因は結果を逸脱するか らである。 svabhave bhavo 'pi bhavamatranurodhini (= v.2cd) hetur iti vartate / tadatmyam hi arthasya tanmatranurodhiny eva nanyayatte / tadbha ve 'bhutasya pascadbhavaniyamabhavat / karananam karyavyabhicarat. PVSV (4,1-4) ここでぜひとも注意しておきたいのは、これが「三種の証因」のうちの svabhavahetu の説明であるにもかかわらず、証因に相当するものが svabhava ではなく bhava であり、所証の方が svabhava となっている点(下線部)である。これ以降の箇所 でも Dharmakirti は明らかに証因を bhava、所証を svabhava とするのである。 この点で、NB, HB, VN と異なる。だがその一方で、長大なアポーハ論のあとで svabhavahetu の議論を再開する中で、例えば次のように証因と所証を共に svabhava とする記述もみられるのも見逃すことはできない: siddhah svabhavo gamako vyapakasya tasya niscitah / gamyah svabhavas ......... (=v.192abc) このような事情を一体どのように理解したらよいだろうか。 注釈家たちは証因にあたる bhava を svabhava に置き換えて説明するにすぎな (15) い。しかし勿論、この単純な置き換えから直ちに bhava を svabhava と読み替え てよいことにはならない。bháva=svabhava とするならば、svabhava に置き換え られない、bhava 特有の語感を見失いかねないであろう。 先に紹介した Steinkellner [1971,1974]は、一方で bhava (証因)を dharma である点から属性 (property) と規定し、他方 svabhava の方は本質的属性(essential -4Page Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44