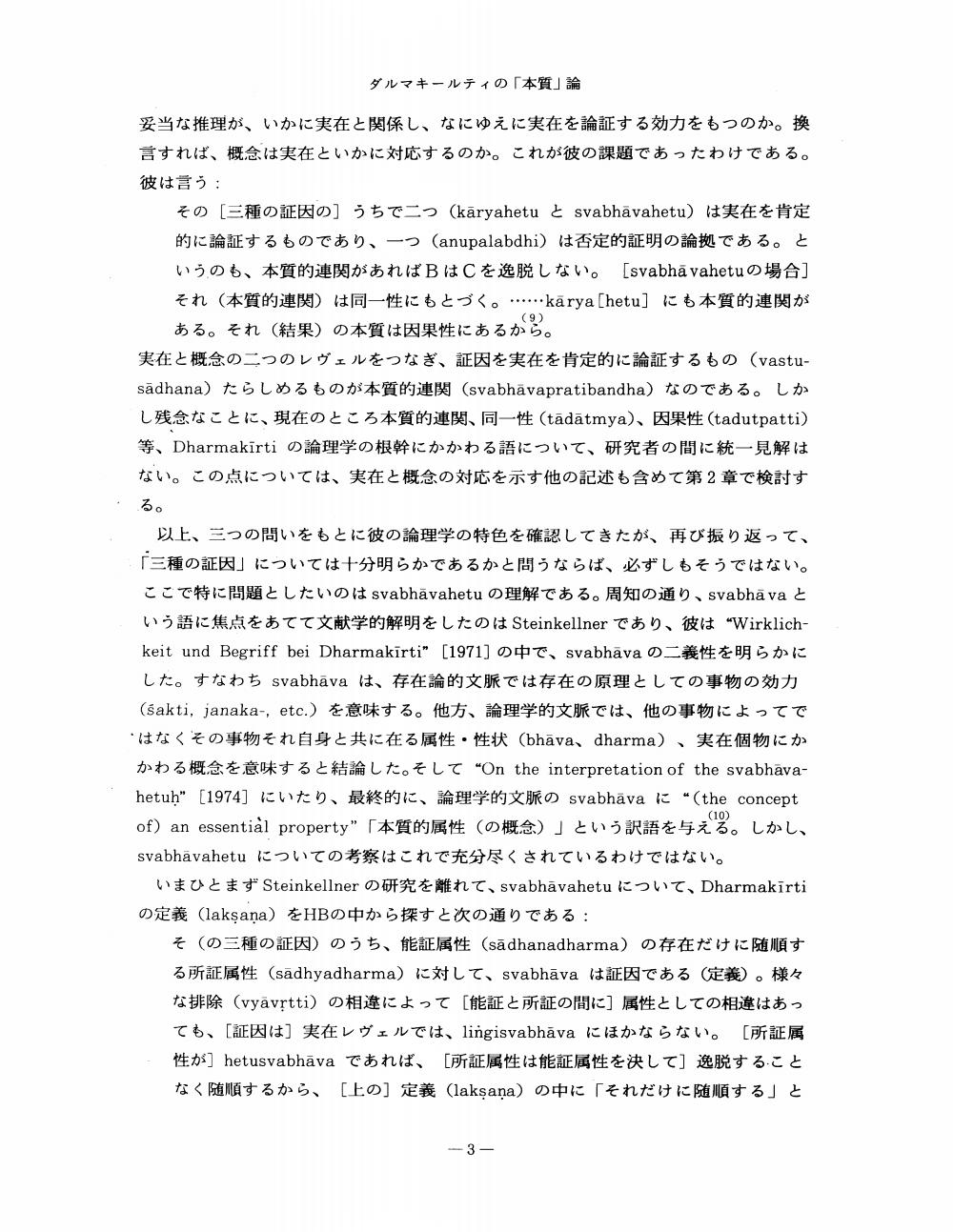Book Title: Bhava And Svabhava Author(s): Publisher: View full book textPage 4
________________ ダルマキールティの「本質」論 妥当な推理が、いかに実在と関係し、なにゆえに実在を論証する効力をもつのか。換 言すれば、概念は実在といかに対応するのか。これが彼の課題であったわけである。 彼は言う: その「三種の証因の] うちで二つ(karyahetu と svabhavahetu)は実在を肯定 的に論証するものであり、一つ (anupalabdhi)は否定的証明の論拠である。と いうのも、本質的連関があればBはCを逸脱しない。 [syabhavahetuの場合] それ(本質的連関)は同一性にもとづく。......karya [hetu] にも本質的連関が ある。それ(結果)の本質は因果性にあるから。 実在と概念の二つのレヴェルをつなぎ、証因を実在を肯定的に論証するもの (vastusadhana) たらしめるものが本質的連関 (svabhavapratibandha) なのである。しか し残念なことに、現在のところ本質的連関、同一性 (tadatmya)、因果性(tadutpatti) 等、Dharmakirti の論理学の根幹にかかわる語について、研究者の間に統一見解は ない。この点については、実在と概念の対応を示す他の記述も含めて第2章で検討す (9) る。 .. 以上、三つの問いをもとに彼の論理学の特色を確認してきたが、再び振り返って、 「三種の証因」については十分明らかであるかと問うならば、必ずしもそうではない。 ここで特に問題としたいのは svabhavahetu の理解である。周知の通り、syabhava と いう語に焦点をあてて文献学的解明をしたのは Steinkellner であり、彼は“Wirklichkeit und Begriff bei Dharmakirti" [1971] の中で、svabhava の二義性を明らかに した。すなわち svabhava は、存在論的文脈では存在の原理としての事物の効力 (sakti, janaka-, etc.) を意味する。他方、論理学的文脈では、他の事物によってで *はなくその事物それ自身と共に在る属性・性状(bhava、dharma)、実在個物にか かわる概念を意味すると結論した。そして "On the interpretation of the svabhavahetuh" [1974] にいたり、最終的に、論理学的文脈の svabhava に "(the concept of) an essential property"「本質的属性(の概念)」という訳語を与える。しかし、 svabhavahetu についての考察はこれで充分尽くされているわけではない。 いまひとまず Steinkellner の研究を離れて、svabhavahetu について、Dharmakirti の定義(laksana) をHBの中から探すと次の通りである: そ(の三種の証因)のうち、能証属性 (sadhanadharma)の存在だけに随順す る所証属性 (sadhyadharma)に対して、syabhava は証因である(定義)。様々 な排除(vyávrtti) の相違によって[能証と所証の間に] 属性としての相違はあっ ても、[証因は]実在レヴェルでは、lingisvabhāva にほかならない。[所証属 性が] hetusvabhava であれば、[所証属性は能証属性を決して]逸脱すること なく随順するから、[上の]定義(laksana) の中に「それだけに随順する」と -3Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 44