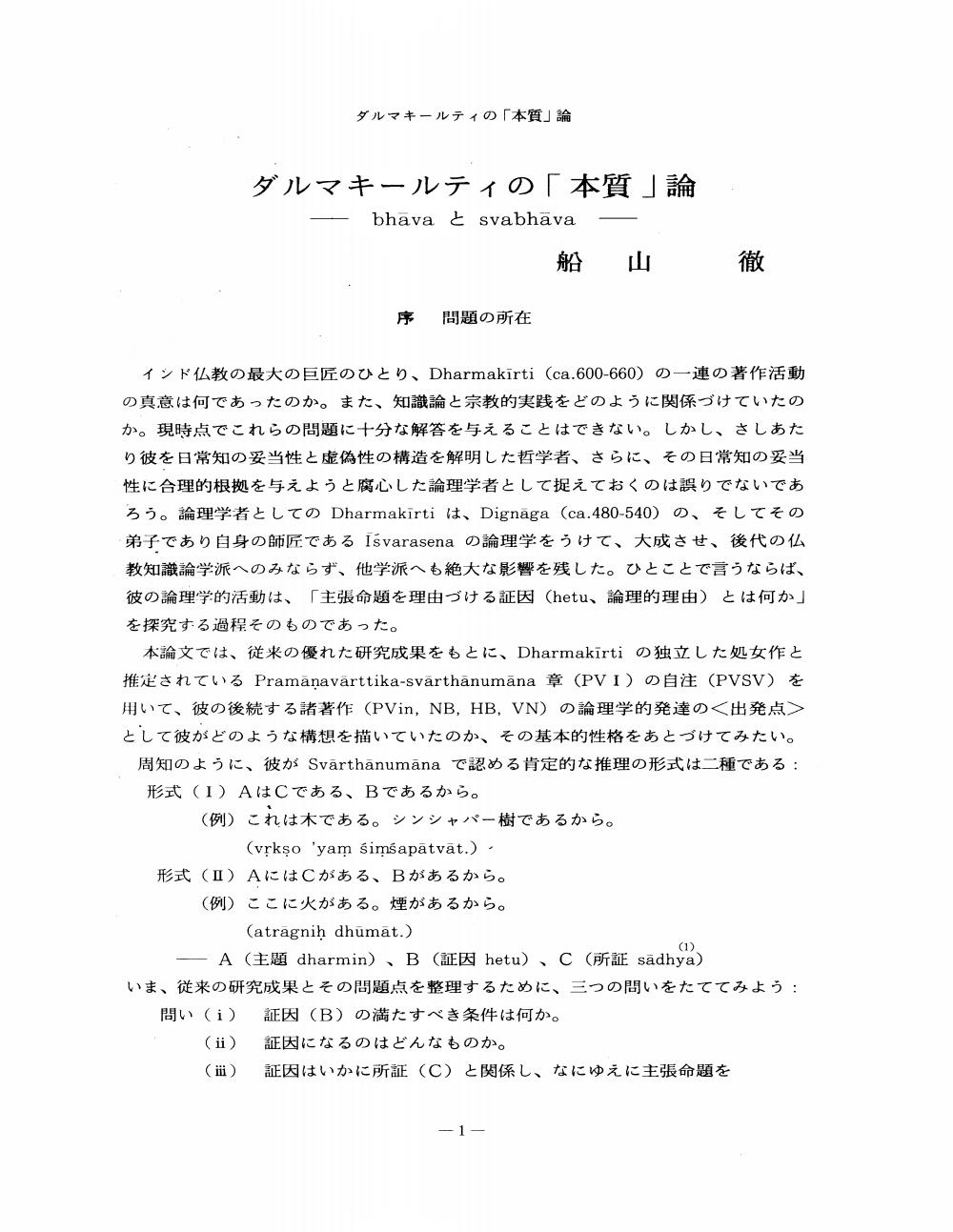Book Title: Bhava And Svabhava Author(s): Publisher: View full book textPage 2
________________ ダルマキールティの「本質」論 ダルマキールティの「本質」論 - -- bhava と svabhava - 船山徹 序問題の所在 インド仏教の最大の巨匠のひとり、Dharmakirti (ca.600-660)の一連の著作活動 の真意は何であったのか。また、知識論と宗教的実践をどのように関係づけていたの か。現時点でこれらの問題に十分な解答を与えることはできない。しかし、さしあた り彼を日常知の妥当性と虚偽性の構造を解明した哲学者、さらに、その日常知の妥当 性に合理的根拠を与えようと腐心した論理学者として捉えておくのは誤りでないであ ろう。論理学者としての Dharmakirti は、Dignaga (ca.480-540)の、そしてその 弟子であり自身の師匠である Isvarasena の論理学をうけて、大成させ、後代の仏 教知識論学派へのみならず、他学派へも絶大な影響を残した。ひとことで言うならば、 彼の論理学的活動は、「主張命題を理由づける証因 (hetu、論理的理由)とは何か」 を探究する過程そのものであった。 本論文では、従来の優れた研究成果をもとに、Dharmakirti の独立した処女作と 推定されている Pramanavarttika-svarthanumana 章 (PVI)の自注(PVSV)を 用いて、彼の後続する諸著作(PVin, NB, HB, VN) の論理学的発達の<出発点> として彼がどのような構想を描いていたのか、その基本的性格をあとづけてみたい。 周知のように、彼が Svarthanumana で認める肯定的な推理の形式は二種である: 形式(I) AはCである、Bであるから。 (例)これは木である。シンシャパー樹であるから。 (vekso 'yam simsapatvat.) 形式 (1) AにはCがある、Bがあるから。 (例)ここに火がある。煙があるから。 (atragnih dhumat.) - A (主題 dharmin)、B(証因 hetu)、C(所証 sadhya) いま、従来の研究成果とその問題点を整理するために、三つの問いをたててみよう: 問い (i) 証因(B) の満たすべき条件は何か。 (ii) 証因になるのはどんなものか。 () 証因はいかに所証(C)と関係し、なにゆえに主張命題を (1)Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 44