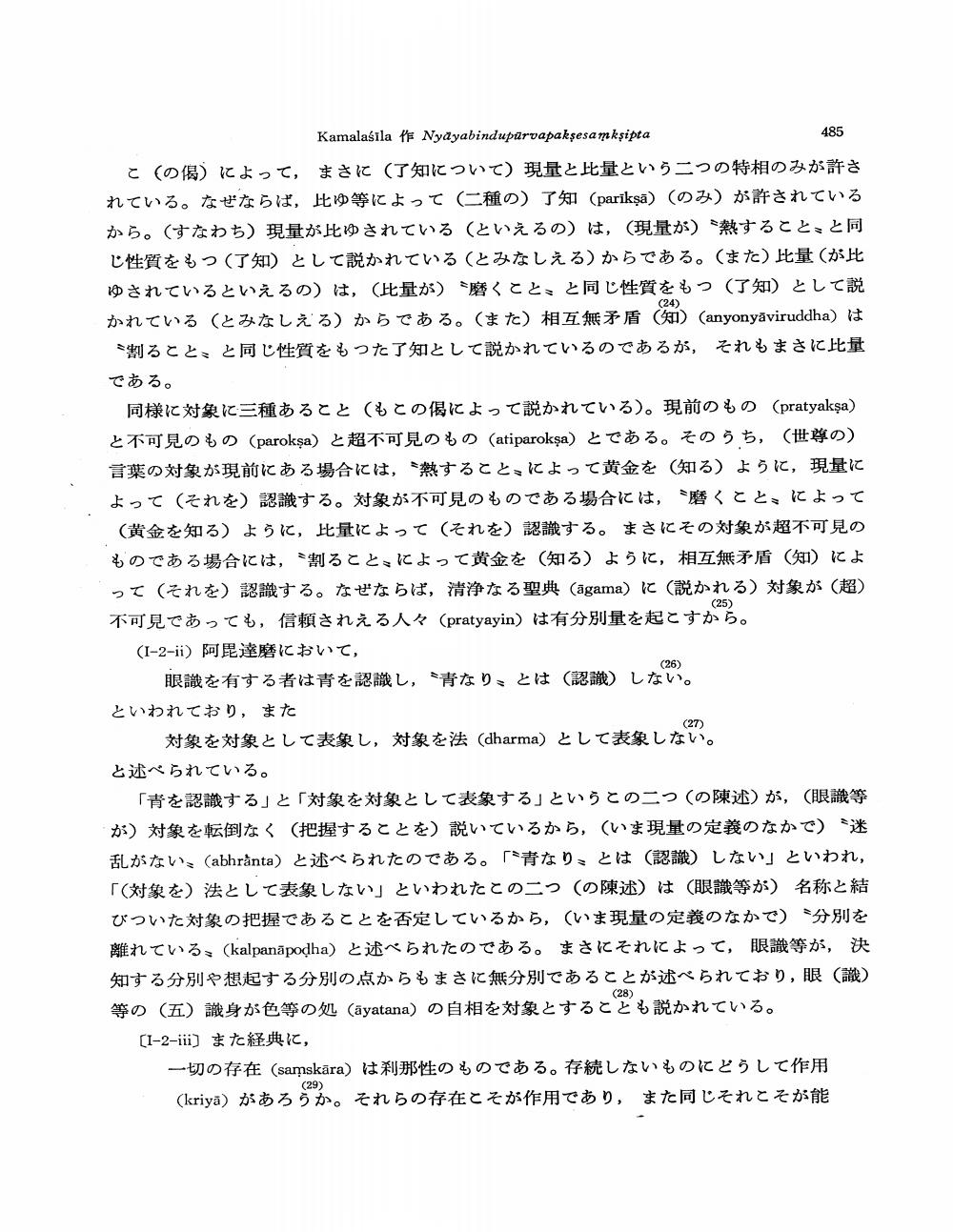Book Title: Kamalasila Nyayabindu Purvapaksesamksipta Author(s): Hiromasa Tosaki Publisher: Hiromasa Tosaki View full book textPage 9
________________ (25) Kamalasila PF Nyayabindupūrvapakşesamkşipta 485 この傷)によって、まさに(了知について)現量と比量という二つの特相のみが許さ れている。なぜならば,比ゆ等によって(二種の)了知 (pariksi) (のみ)が許されている から。(すなわち)現量が比ゆされている(といえるの)は、(現量が)熱することと同 じ性質をもつ(了知)として説かれている(とみなしえる)からである。(また)比量(が比 ゆされているといえるの)は,(比重が)一磨くこと、と同じ性質をもつ(了知)として説 かれている(とみなしえる)からである。(また) 相互無矛盾(知) (anyonyaviruddha) は ・割ること、と同じ性質をもつた了知として説かれているのであるが,それもまさに比量 である。 同様に対象に三種あること(もこの傷によって説かれている)。現前のもの(pratyaksa) と不可見のもの(paroksa) と超不可見のもの(atiparoksa) とである。そのうち,(世尊の) 言葉の対象が現前にある場合には,熱すること、によって黄金を(知る)ように,現量に よって(それを)認識する。対象が不可見のものである場合には,一磨くことによって (黄金を知る)ように、比量によって(それを)認識する。まさにその対象が超不可見の ものである場合には,割ることによって黄金を(知る)ように,相互無矛盾(知)によ って(それを)認識する。なぜならば、清浄なる聖典(agama) に(説かれる)対象が(超) 不可見であっても、信頼されえる人々(pratyayin) は有分別量を起こすから。 (I-2-ii) 阿毘達磨において, 眼識を有する者は青を認識し,青なり、とは(認識)しない。 といわれており,また - 対象を対象として表象し、対象を法 (dharma) として表象しない。 と述べられている。 「青を認識する」と「対象を対象として表象する」というこの二つ(の陳述)が,(眼識等 が)対象を転倒なく(把握することを)説いているから(いま現量の定義のなかで)、迷 乱がない、(abhranta) と述べられたのである。「青なり、とは(認識)しない」といわれ、 「(対象を)法として表象しない」といわれたこの二つ(の陳述)は(眼識等が) 名称と結 びついた対象の把握であることを否定しているから、(いま現量の定義のなかで)分別を 離れている、(kalpanipodha) と述べられたのである。 まさにそれによって,眼識等が,決 知する分別や想起する分別の点からもまさに無分別であることが述べられており,眼(識) 等の(五)識身が色等の処(ayatana) の自相を対象とすることも説かれている。 [1-2-iii) また経典に, 一切の存在 (samskara) は刹那性のものである。存続しないものにどうして作用 (kriya) があろうか。それらの存在こそが作用であり,また同じそれこそが能 (26) (27) (28) (29)Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18