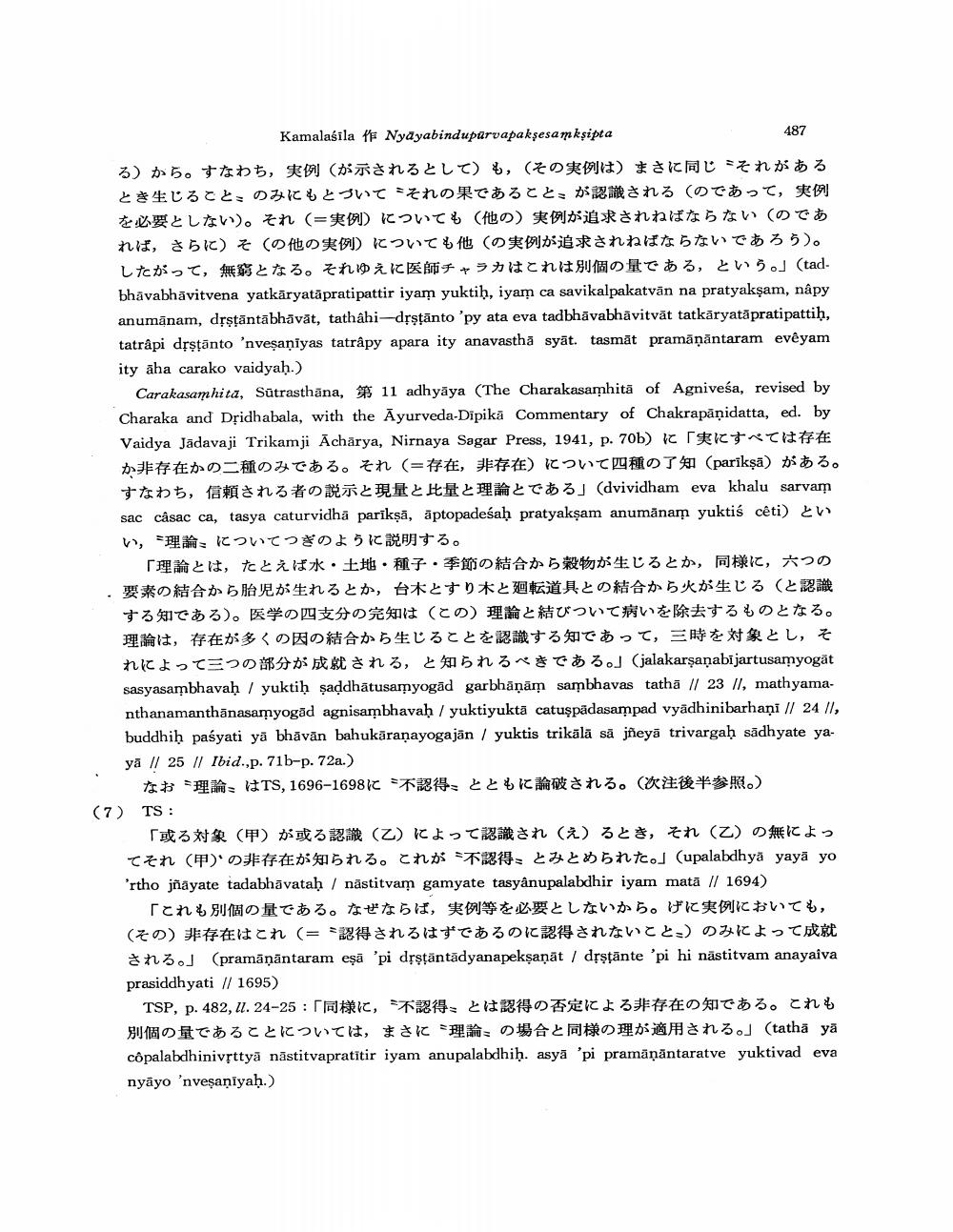Book Title: Kamalasila Nyayabindu Purvapaksesamksipta
Author(s): Hiromasa Tosaki
Publisher: Hiromasa Tosaki
View full book text
________________
487
Kamalasila Nyayabindupurvapaksesamkṣipta
る)から。 すなわち, 実例が示されるとして) も, (その実例は) まさに同じ それがある とき生じることのみにもとづいてそれの果であることが認識される (のであって, 実例 を必要としない)。 それ (=実例) についても (他の) 実例が追求されねばならないのであ れば,さらに) その他の実例) についても他 (の実例が追求されねばならないであろう)。 したがって, 無窮となる。 それゆえに医師チャラカはこれは別個の量である, という。」 (tadbhāvabhāvitvena yatkāryatāpratipattir iyam yuktiḥ, iyam ca savikalpakatvān na pratyakṣam, nâpy anumānam, drstäntābhävat, tathâhi-drstänto 'py ata eva tadbhavabhävitvāt tatkāryatapratipattih, tatrâpi dṛṣṭānto 'nveṣaniyas tatrâpy apara ity anavasthā syāt. tasmāt pramāņāntaram evêyam ity aha carako vaidyaḥ.)
Carakasamhita, Sūtrasthāna, 第 11 adhyaya (The Charakasamhita of Agniveśa, revised by Charaka and Dridhabala, with the Ayurveda-Dipika Commentary of Chakrapaṇidatta, ed. by Vaidya Jādavaji Trikamji Acharya, Nirnaya Sagar Press, 1941, p. 70b) に 「実にすべては存在 か非存在かの二種のみである。 それ (=存在, 非存在) について四種の了知 (pariksā) がある。 すなわち, 信頼される者の説示と現量と比量と理論とである」 (dvividham eva khalu sarvam sac câsac ca, tasya caturvidha parīkṣā, āptopadeśaḥ pratyakşam anumanam yuktiś cêti) 2 い 理論についてつぎのように説明する。
「理論とは,たとえば水・土地 種子 季節の結合から穀物が生じるとか、同様に,六つの 要素の結合から胎児が生れるとか, 台木とすり木と廻転道具との結合から火が生じる (と認識 する知である)。 医学の四支分の完知は (この) 理論と結びついて病いを除去するものとなる。 理論は, 存在が多くの因の結合から生じることを認識する知であって, 三時を対象とし, そ れによって三つの部分が成就される, と知られるべきである。」 (jalakarsanabijartusamyogät sasyasambhavah / yuktih saddhātusamyogād garbhänām sambhavas tathā // 23 //, mathyamanthanamanthanasamyogad agnisambhavab / yuktiyukta catuspädasampad vyadhinibarhant // 24 1, buddhiḥ paśyati ya bhāvān bahukaraṇayogajän / yuktis trikālā să jñeya trivargaḥ sadhyate yaya || 25 || Ibid.p.71b-p.72a.)
なお 理論はTS, 1696-1698に "不認得とともに論破される。 (次注後半参照。 )
(7) TS:
「或る対象 (甲) が或る認識 (乙) によって認識され (え) るとき, それ (乙) の無によっ てそれ (甲) の非存在が知られる。 これが 〝不認得とみとめられた。」 (upalabdhya yaya yo 'rtho jñayate tadabhāvatah / nästitvam gamyate tasyânupalabdhir iyam matā // 1694)
「これも別個の量である。 なぜならば、 実例等を必要としないから。 げに実例においても (その) 非存在はこれ (=認得されるはずであるのに認得されないこと) のみによって成就 される。」(pramānāntaram esā 'pi drstäntādyanapeksanat / drstānte 'pi hi nästitvam anayaiva prasiddhyati //1695)
TSP, p. 482, 1. 24-25 「同様に, "不認得とは認得の否定による非存在の知である。 これも 別個の量であることについては、 まさに 理論の場合と同様の理が適用される。」 (tathā ya côpalabdhinivṛttyä nästitvapratitir iyam anupalabdhiḥ. asya 'pi pramāṇāntaratve yuktivad eva nyayo 'nvesaniyah.)
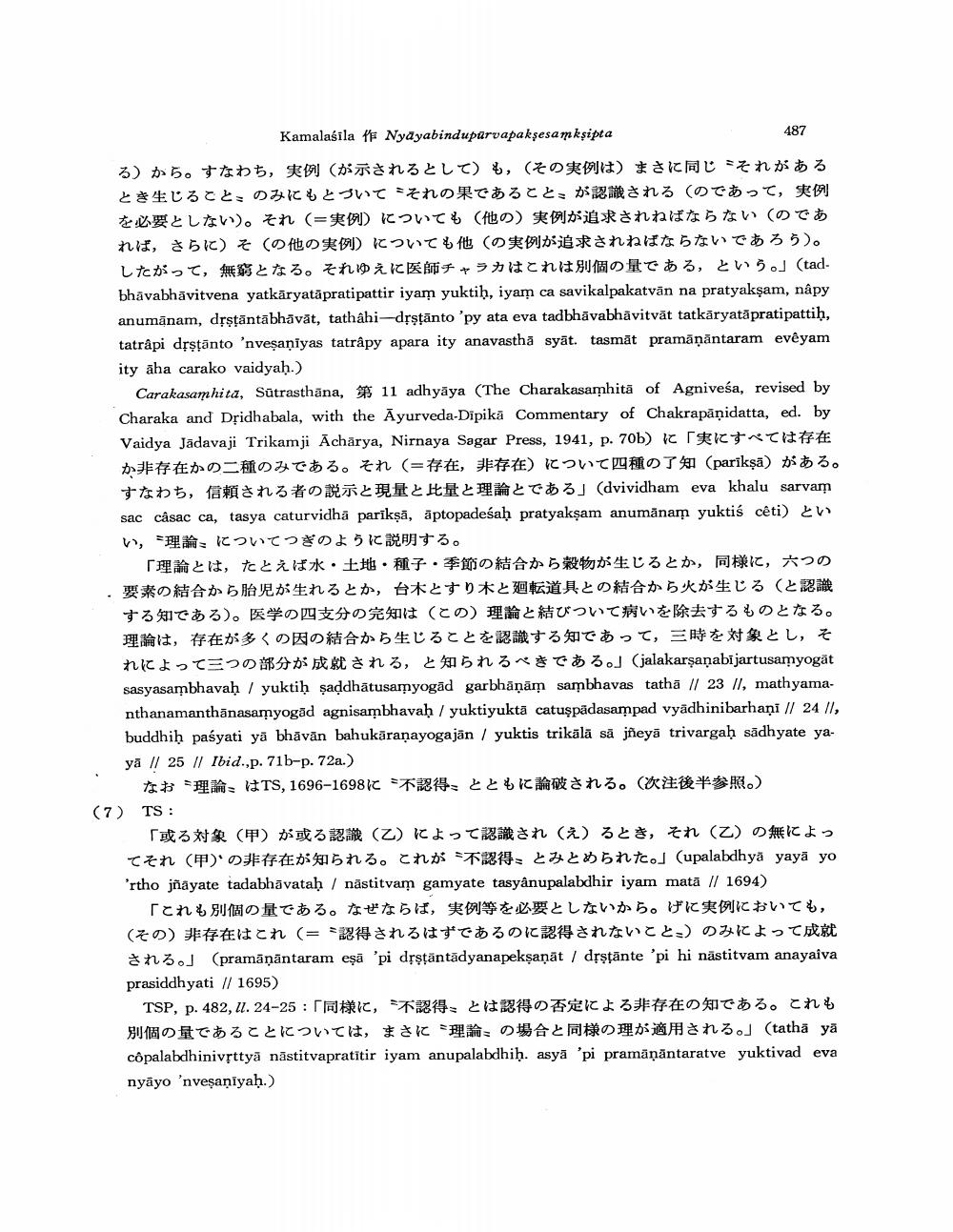
Page Navigation
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18