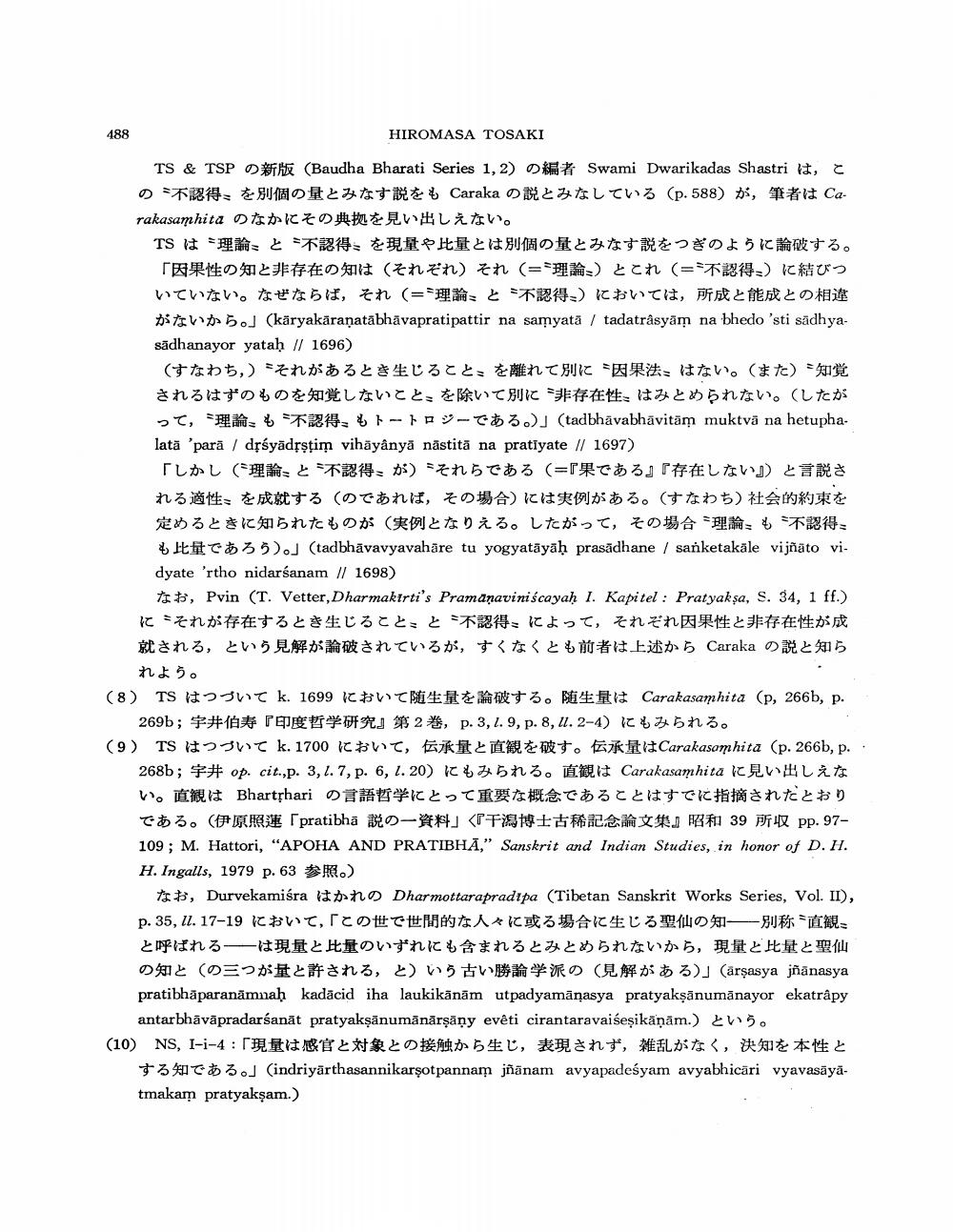Book Title: Kamalasila Nyayabindu Purvapaksesamksipta
Author(s): Hiromasa Tosaki
Publisher: Hiromasa Tosaki
View full book text
________________
488
HIROMASA TOSAKI
TS & TSP の新版 (Baudha Bharati Series 1, 2) の編者 Swami Dwarikadas Shastri は,こ
不認得を別個の量とみなす説をも Caraka の説とみなしている (p.588) が, 筆者は Carakasamhita のなかにその典拠を見い出しえない。
TS は理論〟と〝不認得を現量や比量とは別個の量とみなす説をつぎのように論破する。 「因果性の知と非存在の知は (それぞれ) それ (="理論 ) とこれ (="不認得) に結びつ いていない。 なぜならば,それ (="理論" と "不認得) においては, 所成と能成との相違 がないから。」 (kāryakaranatābhävapratipattir na samyata / tadatrâsyäm na bhedo 'sti sädhyasādhanayor yatah // 1696)
(すなわち,) それがあるとき生じることを離れて別に因果法はない。 (また) 知覚 されるはずのものを知覚しないことを除いて別に非存在性はみとめられない。(したが って、理論も“不認得もトートロジーである。)」 (tadbhävabhävitām muktyā na hetuphalata 'para / drśyādrstim vihãyânyā nāstitā na pratiyate // 1697)
「しかし (〝理論と不認得 が それらである ( = 『果である』 『存在しない』)と言説さ れる適性 を成就する (のであれば、 その場合) には実例がある。 (すなわち) 社会的約束を 定めるときに知られたものが (実例となりえる。 したがって, その場合 理論も不認得 も比量であろう)。」 (tadbhävavyavahäre tu yogyatāyāh prasādhane / sańketakale vijnato vidyate 'rtho nidarśanam // 1698)
なお,Pvin (T. Vetter, Dharmakirti's Pramanaviniścayah I. Kapitel: Pratyaksa, S. 34, 1 ff.) にそれが存在するとき生じること〟と〝不認得〟によって,それぞれ因果性と非存在性が成 就される, という見解が論破されているが, すくなくとも前者は上述から Caraka の説と知ら れよう。
(8) TSはつづいて k. 1699 において随生量を論破する。 随生量は Carakasamhita (p, 266b, p. 269b; 宇井伯寿 『印度哲学研究』 第2巻, p. 3,1.9, p. 8,7.2-4) にもみられる。
(9) TSはつづいて k.1700 において, 伝承量と直観を破す。 伝承量はCarakasomhita (p.266b, p. 268b; 宇井 op.cit.,p. 3,1.7, p. 6, 7.20) にもみられる。 直観は Carakasamhita に見い出しえな い。 直観は Bharthari の言語哲学にとって重要な概念であることはすでに指摘されたとおり である。(伊原照蓮 「pratibhā 説の一資料」 <『干潟博士古稀記念論文集』 昭和 39 所収 pp.97109; M. Hattori, “APOHA AND PRATIBHĀ," Sanskrit and Indian Studies, in honor of D.H. H. Ingalls, 1979 p.63 参照。)
なお, Durvekamiśra はかれの Dharmottarapradipa (Tibetan Sanskrit Works Series, Vol. II), p.35, 7.17-19 において、 「この世で世間的な人々に或る場合に生じる聖仙の知別称 直観 と呼ばれるは現量と比量のいずれにも含まれるとみとめられないから、 現量と比量と聖仙 の知との三つが量と許される,という古い勝論学派の (見解がある)」 (ārsasya jñanasya pratibhāparanāmnaḥ kadācid iha laukikānām utpadyamānasya pratyakṣānumānayor ekatrâpy antarbhāvāpradarśanāt pratyaksānumānārsāny evêti cirantaravaiśesikänām.)という。
(10) NS, I-i-4: 「現量は感官と対象との接触から生じ, 表現されず, 雑乱がなく、決知を本性と する知である。」 (indriyārthasannikarsotpannam jñānam avyapadeśyam avyabhicāri vyavasāyā - tmakam pratyakşam.)
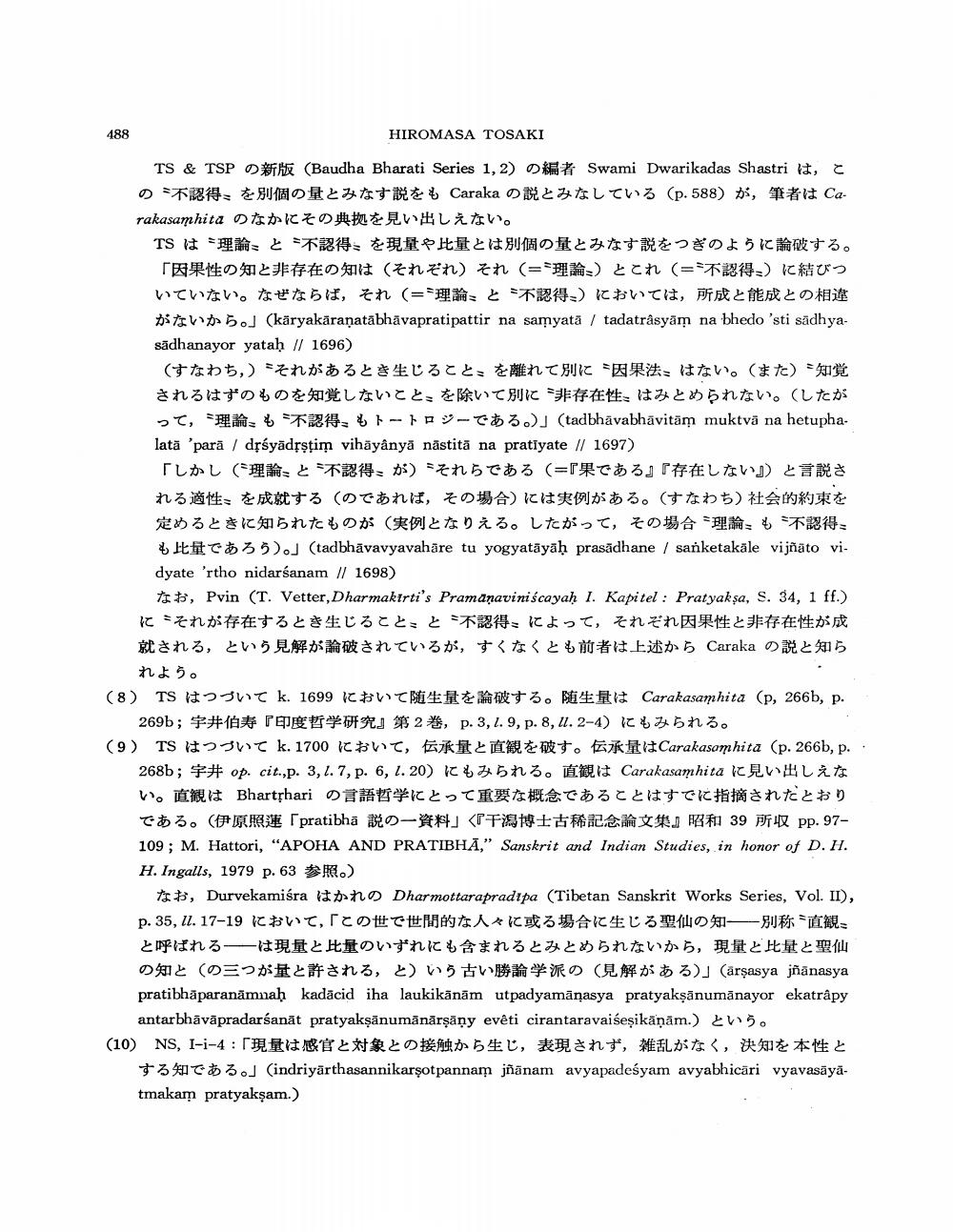
Page Navigation
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18