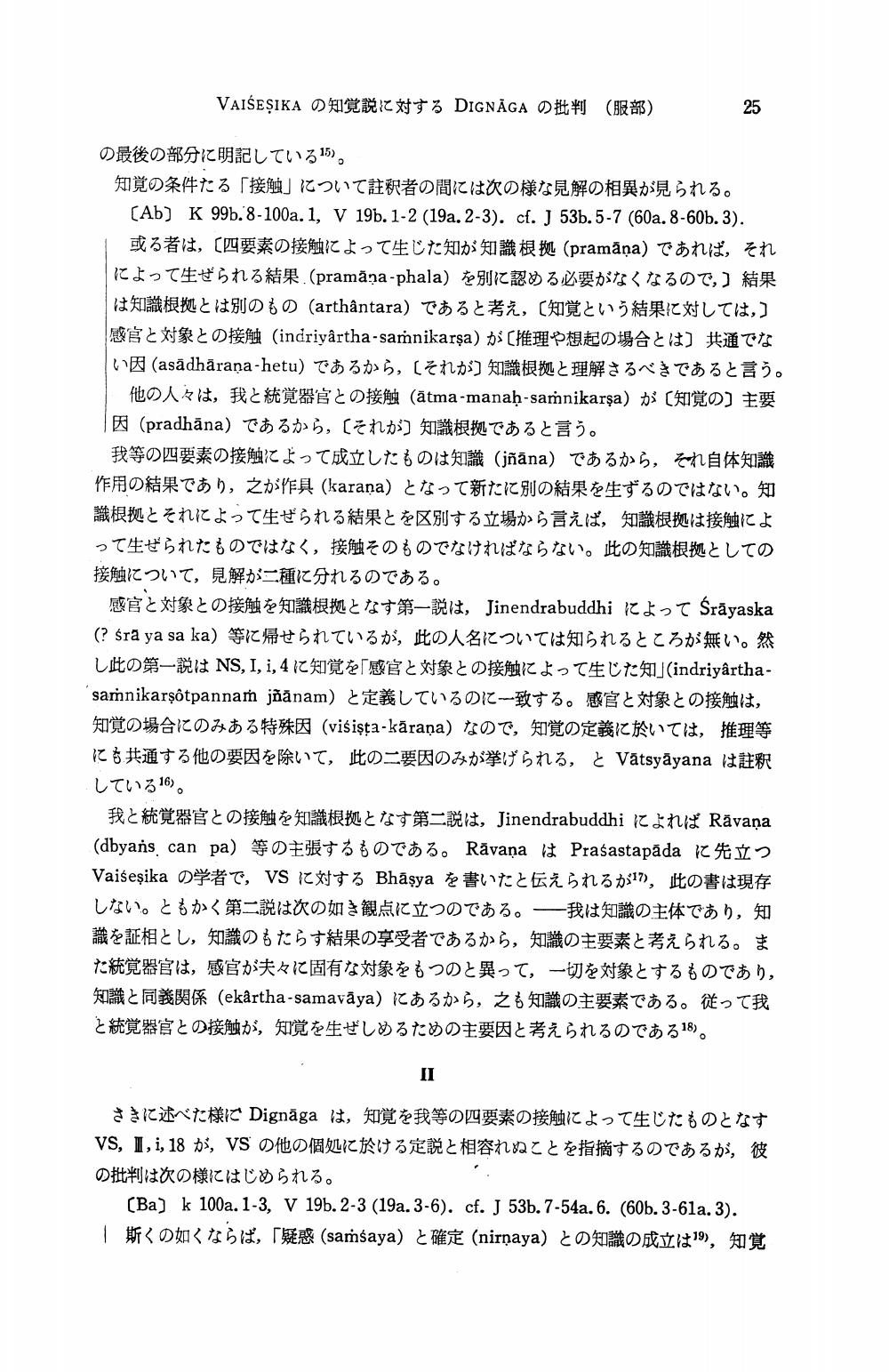Book Title: Vaisesika Dignaga Author(s): Publisher: View full book textPage 3
________________ VAISESIKA の知覚説に対するDIGNAGA の批判 (服部) 11 25 の最後の部分に明記している15)。 知覚の条件たる「接触」について註釈者の間には次の様な見解の相異が見られる。 [Ab] K 996.8-1002.1, V 196.1-2 (19a.2-3). cf. J 536.5-7 (60a.8-606.3). 或る者は,〔四要素の接触によって生じた知が知識根拠 (pramana) であれば,それ によって生ぜられる結果(pramana-phala)を別に認める必要がなくなるので,】結果 は知識根拠とは別のもの(arthantara)であると考え,[知覚という結果に対しては,】 感官と対象との接触 (indriyartha-samnikarsa) が[推理や想起の場合とは] 共通でな い因(asadharana-hetu)であるから,しそれが幻知識根拠と理解さるべきであると言う。 他の人々は,我と統覚器官との接触(atma-manah-samnikarsa) が「知覚の] 主要 | 因(pradhana) であるから,「それがコ 知識根拠であると言う。 我等の四要素の接触によって成立したものは知識(jñāna) であるから,それ自体知識 作用の結果であり,之が作具 (karana)となって新たに別の結果を生ずるのではない。知 識根拠とそれによって生ぜられる結果とを区別する立場から言えば、知識根拠は接触によ って生ぜられたものではなく,接触そのものでなければならない。此の知識根拠としての 接触について,見解が二種に分れるのである。 感官と対象との接触を知識根拠となす第一説は, Jinendrabuddhi によって Srayaska (? sra ya sa ka) 等に帰せられているが,此の人名については知られるところが無い。然 し此の第一説は NS, I, i, 4 に知覚を「感官と対象との接触によって生じた知」(indriyarthasamnikarsotpannam jiānam)と定義しているのに一致する。感官と対象との接触は, 知覚の場合にのみある特殊因 (visista-karana) なので、知覚の定義に於いては,推理等 にも共通する他の要因を除いて,此の二要因のみが挙げられる, と Vatsyayana は註釈 している。 我と統覚器官との接触を知識根拠となす第二説は,Jinendrabuddhi によればRavana (dbyans, can pa)等の主張するものである。 Ravana は Pratastapada に先立つ Vaisesika の学者で, VS に対する Bhasya を書いたと伝えられるが177, 此の書は現存 しない。ともかく第二説は次の如き観点に立つのである。一我は知識の主体であり,知 識を証相とし、知識のもたらす結果の享受者であるから、知識の主要素と考えられる。ま た統覚器官は,感官が夫々に固有な対象をもつのと異って,一切を対象とするものであり, 知識と同義関係 (ekartha-samavāya)にあるから,之も知識の主要素である。従って我 と統覚器官との接触が,知覚を生ぜしめるための主要因と考えられるのである18)。 さきに述べた様にDignaga は、知覚を我等の四要素の接触によって生じたものとなす VS, I, i, 18 が, VS の他の個処に於ける定説と相容れぬことを指摘するのであるが,彼 の批判は次の様にはじめられる。 [Ba] k 100a.1-3, V 196.2-3 (19a.3-6). cf. J 536.7-54a. 6. (606.3-61a.3). | 斯くの如くならば,「疑惑 (sarisaya) と確定(nirnaya) との知識の成立は199,知覚Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8