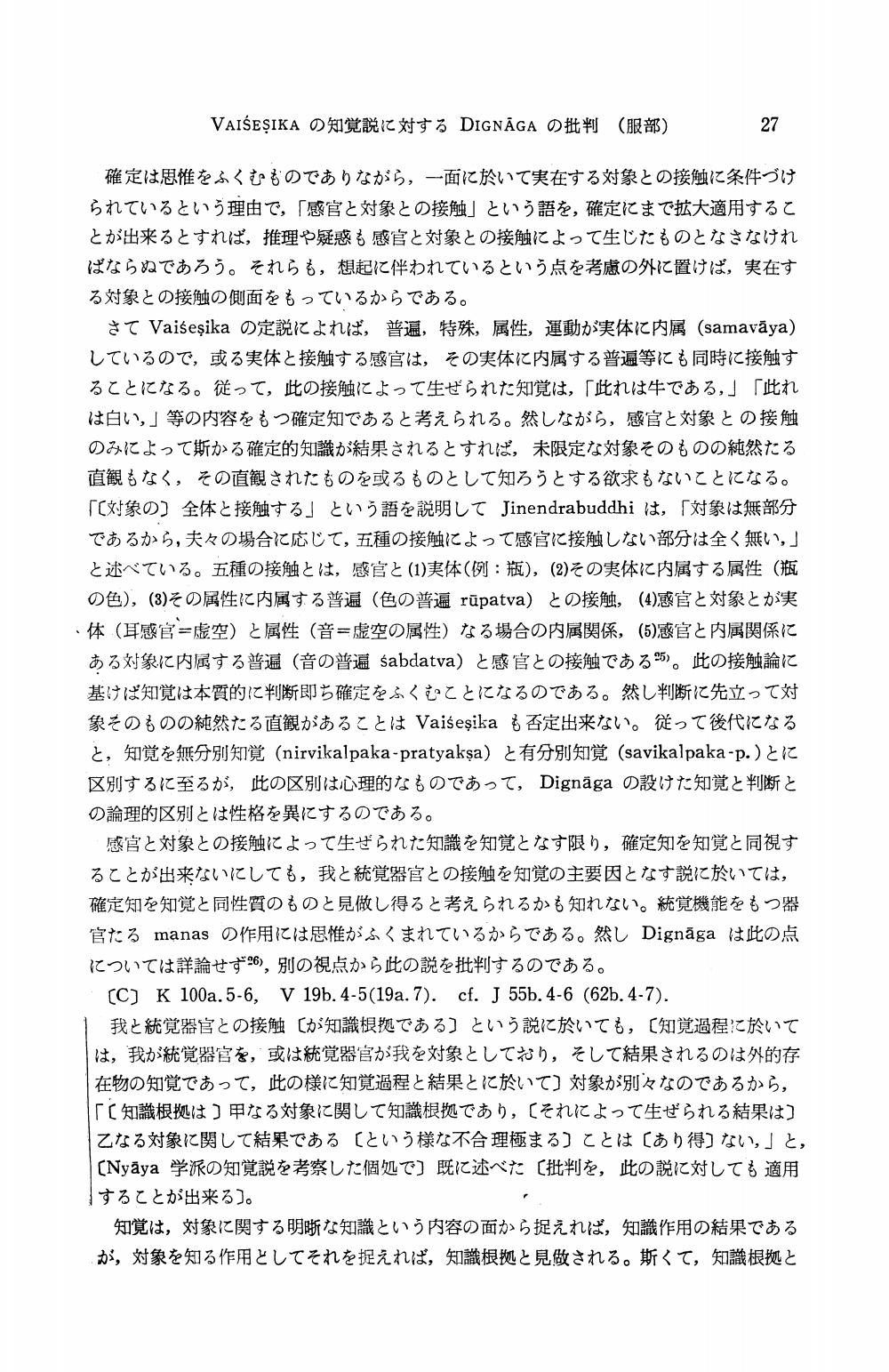Book Title: Vaisesika Dignaga Author(s): Publisher: View full book textPage 5
________________ VAISESIKA の知覚説に対する DIGNAGA の批判 (服部) 27 確定は思惟をふくむものでありながら,一面に於いて実在する対象との接触に条件づけ られているという理由で、「感官と対象との接触」という語を、確定にまで拡大適用するこ とが出来るとすれば,推理や疑惑も感官と対象との接触によって生じたものとなさなけれ ばならぬであろう。それらも,想起に伴われているという点を考慮の外に置けば、実在す る対象との接触の側面をもっているからである。 さて Vaisesika の定説によれば、 普遍,特殊,属性, 運動が実体に内属(samavāya) しているので,或る実体と接触する感官は, その実体に内属する普遍等にも同時に接触す ることになる。従って,此の接触によって生ぜられた知覚は,「此れは牛である,」「此れ は白い,」等の内容をもつ確定知であると考えられる。然しながら,感官と対象との接触 のみによって斯かる確定的知識が結果されるとすれば、未限定な対象そのものの純然たる 直観もなく,その直観されたものを或るものとして知ろうとする欲求もないことになる。 「対象の] 全体と接触する」 という語を説明して Jinendrabuddhi は,「対象は無部分 であるから、夫々の場合に応じて,五種の接触によって感官に接触しない部分は全く無いで」 と述べている。五種の接触とは、感官と (1)実体(例:瓶),(2)その実体に内属する属性(瓶 の色), (3)その属性に内属する普遍(色の普遍 rupatva) との接触,(4)感官と対象とが実 、体(耳感官=虚空)と属性(音=虚空の属性)なる場合の内属関係,(5)感官と内属関係に ある対象に内属する普遍(音の普遍 sabdatva) と感官との接触である。此の接触論に 基けば知覚は本質的に判断即ち確定をふくむことになるのである。然し判断に先立って対 象そのものの純然たる直観があることは Vaisesika も否定出来ない。従って後代になる と,知覚を無分別知覚 (nirvikalpaka-pratyaksa) と有分別知覚 (savikalpaka-p.)とに 区別するに至るが,此の区別は心理的なものであって, Dignaga の設けた知覚と判断と の論理的区別とは性格を異にするのである。 感官と対象との接触によって生ぜられた知識を知覚となす限り、確定知を知覚と同視す ることが出来ないにしても,我と統覚器官との接触を知覚の主要因となす説に於いては, 確定知を知覚と同性質のものと見做し得ると考えられるかも知れない。統覚機能をもつ器 官たる manas の作用には思惟がふくまれているからである。然し Dignaga は此の点 については詳論せず, 別の視点から此の説を批判するのである。 [C] K 100a.5-6, V 196.4-5(19a.7). cf. J 556.4-6 (626.4-7). | 我と統覚器官との接触が知識根拠である]という説に於いても,知覚過程に於いて は、我が統覚器官を,或は統覚器官が我を対象としており、そして結果されるのは外的存 在物の知覚であって、此の様に知覚過程と結果とに於いて]対象が別々なのであるから, 「[知識根拠は]甲なる対象に関して知識根拠であり,それによって生ぜられる結果は] 乙なる対象に関して結果である [という様な不合理極まる]ことはあり得〕ない,」と, [Nyaya 学派の知覚説を考察した個処で】 既に述べた「批判を,此の説に対しても適用 「することが出来る]。 知覚は,対象に関する明晰な知識という内容の面から捉えれば、知識作用の結果である が,対象を知る作用としてそれを捉えれば,知識根拠と見做される。斯くて、知識根拠とPage Navigation
1 ... 3 4 5 6 7 8