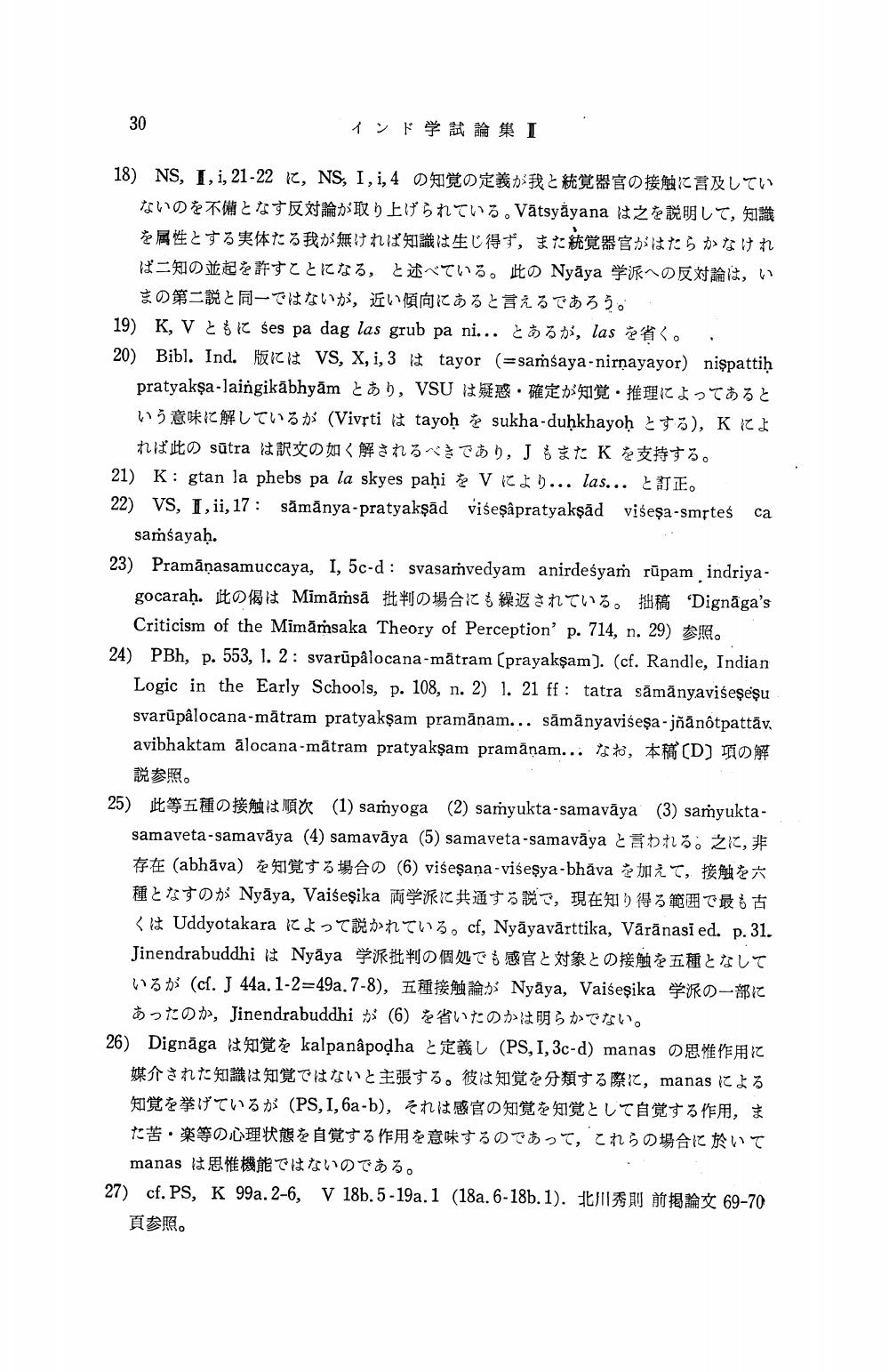Book Title: Vaisesika Dignaga Author(s): Publisher: View full book textPage 8
________________ 30 インド 学試論集1 18) NS, I, i21-22 に, NS, I,,4 の知覚の定義が我と統覚器官の接触に言及してい ないのを不備となす反対論が取り上げられている。Vatsyayana は之を説明して、知識 を属性とする実体たる我が無ければ知識は生じ得ず,また統覚器官がはたらかなけれ ば二知の並起を許すことになる, と述べている。此の Nyaya 学派への反対論は,い まの第二説と同一ではないが,近い傾向にあると言えるであろう。 19) K, V ともに ses pa dag las grub pa ni... とあるが,las を省く。 . 20) Bibl. Ind. 版には VS, X, i, 3 は tayor (=samsaya-nirnayayor) nispattih pratyaksa-laingikabhyam とあり, VSU は疑惑・確定が知覚・推理によってあると いう意味に解しているが(Vivrti は tayoh を sukha-duhkhayoh とする), K によ れば此の sutra は訳文の如く解されるべきであり, J もまたK を支持する。 21) K: gtan la phebs pa la skyes pahi を V により... las... と訂正。 22) VS, I, ii, 17: samanya-pratyaksad visesapratyaksad visesa-smrtes ca samsayah. 23) Pramanasamuccaya, I, 5c-d: svasamvedyam anirdesyam rupam indriya gocarah.此の傷はMimamsa 批判の場合にも繰返されている。 拙稿 "Dignaga's Criticism of the Mimamsaka Theory of Perception' p. 714, n. 29) El. 24) PBh, p. 553, 1. 2: svarupalocana-matram (prayaksam). (cf. Randle, Indian Logic in the Early Schools, p. 108, n. 2) 1. 21 ff : tatra samanyavisesesu svarupalocana-matram pratyaksam pramanam... samanyavisesa-jnanotpattav, avibhaktam alocana-matram pratyaksam pramanam... なお,本稿CD] 項の解 説参照。 25) 此等五種の接触は順次 (1) samyoga (2) samyukta-samavaya (3) samyukta samaveta-samavaya (4) samavaya (5) samaveta-samavaya と言われる。之に,非 存在(abhava) を知覚する場合の (6) visesana-visesya-bhava を加えて,接触を六 すのが Nyaya, Vaisesika 両学派に共通する説で,現在知り得る範囲で最も古 くは Uddyotakara によって説かれている。cf, Nyayavarttika, Varanasi ed. p.31. Jinendrabuddhi は Nyaya 学派批判の個処でも感官と対象との接触を五種となして いるが(cf. J44a.1-2-349a.7-8),五種接触論がNvava, Vaisesika 学派の一部に あったのか, Jinendrabuddhi が (6) を省いたのかは明らかでない。 26) Dignaga は知覚を kalpanapodha と定義し (PS, I, 3c-d) manas の思性作用に 媒介された知識は知覚ではないと主張する。彼は知覚を分類する際に, manas による 知覚を挙げているが(PS, I, 6a-b), それは感官の知覚を知覚として自覚する作用,ま た苦・楽等の心理状態を自覚する作用を意味するのであって,これらの場合に於いて manas は思惟機能ではないのである。 27) cf. PS, K 99a.2-6, V 186.5 -19a.1 (18a. 6-186.1). 北川秀則 前掲論文 69-70 頁参照。Page Navigation
1 ... 6 7 8