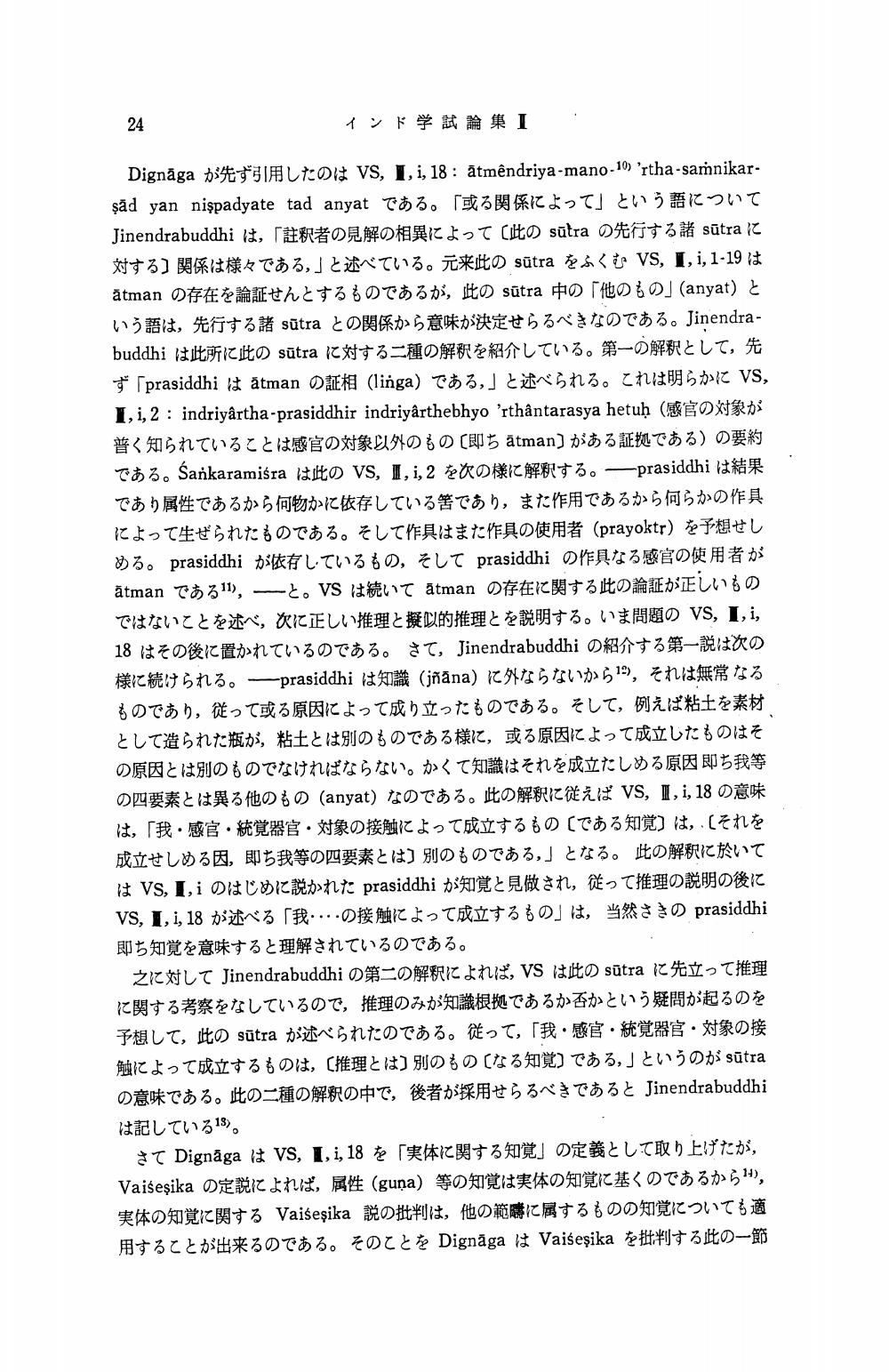Book Title: Vaisesika Dignaga Author(s): Publisher: View full book textPage 2
________________ インド学試論集1 Dignaga dists t olt VS, I, i, 18 : atmendriya-mano-10) 'rtha-samnikar. sad yan nipadyate tad anyat である。「或る関係によって」という語について Jinendrabuddhi は,「註釈者の見解の相異によって C此の sutra の先行する諸 sutra に 対する] 関係は様々である,」と述べている。元来此の sutra をふくむ VS, I, i, 1-19 は atman の存在を論証せんとするものであるが,此の sutra 中の「他のもの」(anyat)と いう語は,先行する諸 sutra との関係から意味が決定せらるべきなのである。Jinendrabuddhi は此所に此の sutra に対する二種の解釈を紹介している。第一の解釈として,先 ず「prasiddhi は atman の証相 (linga) である,」と述べられる。 これは明らかに VS, I, i, 2 : indriyartha-prasiddhir indriyarthebhyo 'rthantarasya hetuh ( O seti 普く知られていることは感官の対象以外のもの[即ち atman] がある証拠である)の要約 である。Saikaramitra は此の VS, I, i; 2 を次の様に解釈する。 prasiddhi は結果 であり属性であるから何物かに依存している筈であり,また作用であるから何らかの作具 によって生ぜられたものである。そして作具はまた作具の使用者(prayoktr)を予想せし める。 prasiddhi が依有しているもの、そして prasiddhi の作具なる感官の使用者が 18はその後に置かれているのである。 さて,Jinendrabuddhi の紹介する第一説は次の 様に続けられる。Sprasiddhi は知識(jñāna) に外ならないから197,それは無常なる ものであり,従って或る原因によって成り立ったものである。そして,例えば粘土を素材 として造られた瓶が,粘土とは別のものである様に,或る原因によって成立したものはそ の原因とは別のものでなければならない。かくて知識はそれを成立たしめる原因 即ち我等 の四要素とは異る他のもの(anyat) なのである。此の解釈に従えばVS, In, i, 18 の意味 は、「我・感官・統覚器官・対象の接触によって成立するものである知覚)は、それを 成立せしめる因、即ち我等の四要素とは)別のものである、」となる。 此の解釈に於いて はVS, I, i のはじめに説かれたprasiddhi が知覚と見做され,従って推理の説明の後に VS, I, i, 18 が述べる「我・・・・の接触によって成立するもの」は、当然さきの prasiddhi 即ち知覚を意味すると理解されているのである。 ウに対して Jinendrabuddhi の第二の解釈によれば, VS は此の sutra に先立って推理 に関する考察をなしているので、推理のみが知識根拠であるか否かという疑問が起るのを 予想して、此の sutra が述べられたのである。従って,「我・感官・統覚器官・対象の接 触によって成立するものは,推理とは別のものなる知覚)である」というのが sutra の意味である。此の二種の解釈の中で、後者が採用せらるべきであるとJinendrabuddhi は記している。 さて Dignaga は VS, I, i 18 を「実体に関する知覚」の定義として取り上げたが, Vaisesika の定説によれば、属性(guna)等の知覚は実体の知覚に基くのであるから'), 実体の知覚に関するVaisesika 説の批判は、他の範疇に属するものの知覚についても適 用することが出来るのである。 そのことを Dignaga は Vaisesika を批判する此の一節Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8