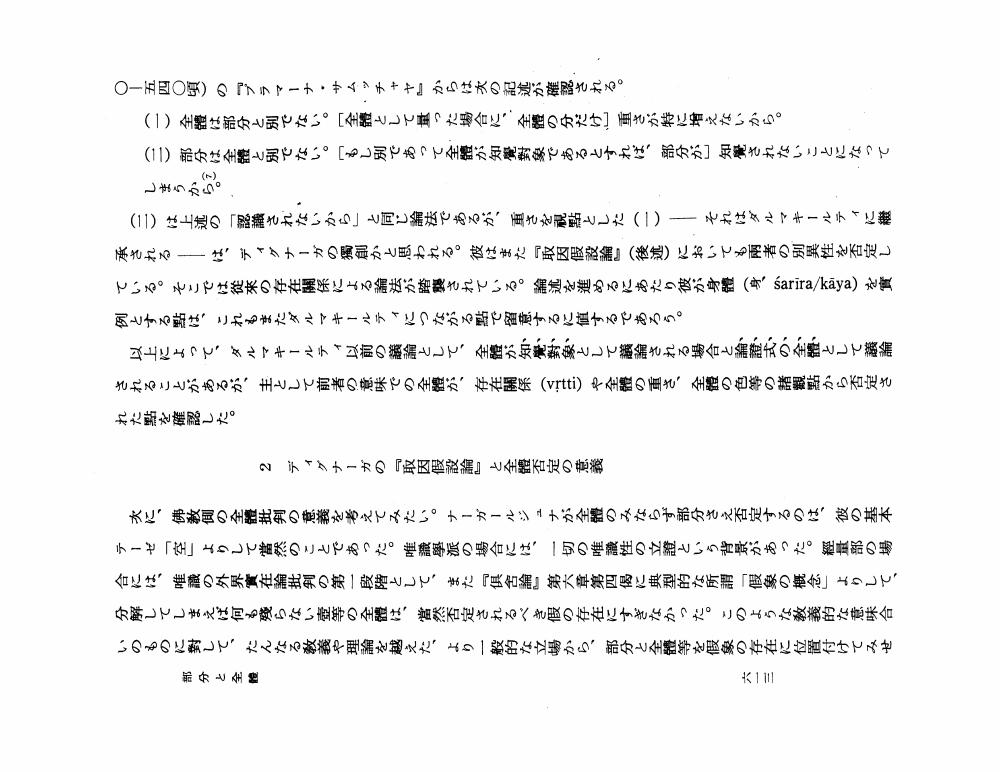Book Title: Bhava And Svabhava 01 Author(s): Publisher: View full book textPage 8
________________ ○|五四〇頃)の『プラマーナ・サムッチャヤ』からは次の記述が確認される。 (一)全體は部分と別でない。[全體として量った場合に、全體の分だけ]重さが特に増えないから。 (二)部分は全體と別でない。[ちし別であって全體が知覺對象であるとすれば、部分が〕知覚されないことになって しまうから。 (二)は上述の「認識されないから」と同じ論法であるが、重さを視點とした(-) | それはダルマキールティに継 承される -- は、ディグナーガの獨創かと思われる。彼はまた『取因假設論』(後述)においても兩者の別異性を否定し ている。そこでは從來の存在關係による論法が踏襲されている。論述を進めるにあたり彼が身體(身、sarira/kaya) を實 例とする點は、これもまたダルマキールティにつながる點で留意するに値するであろう。 以上によって、ダルマキールティ以前の議論として、全體が知覺對象として議論される場合と論證式の全體として議論 されることがあるが、主として前者の意味での全體が、存在關係 (vrtti)や全體の重さ、全體の色等の諸觀點から否定さ れた點を確認した。 2 ディグナーガの『取因假設論』と全體否定の意義 次に、佛教側の全體批判の意義を考えてみたい。ナーガールジュナが全體のみならず部分さえ否定するのは、彼の基本 テーゼ「空」よりして當然のことであった。唯識學派の場合には、一切の唯識性の立證という背景があった。経量部の場 合には、唯識の外界實在論批判の第一段階として、また『倶舎論』第六章第四偶に典型的な所謂「假象の概念」よりして、 分解してしまえば何も残らない壺等の全體は、當然否定されるべき假の存在にすぎなかった。このような教義的な意味合 いのものに對して、たんなる教義や理論を越えた、より一般的な立場から、部分と全體等を假象の存在に位置付けてみせ 部分と全位一 六三Page Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30