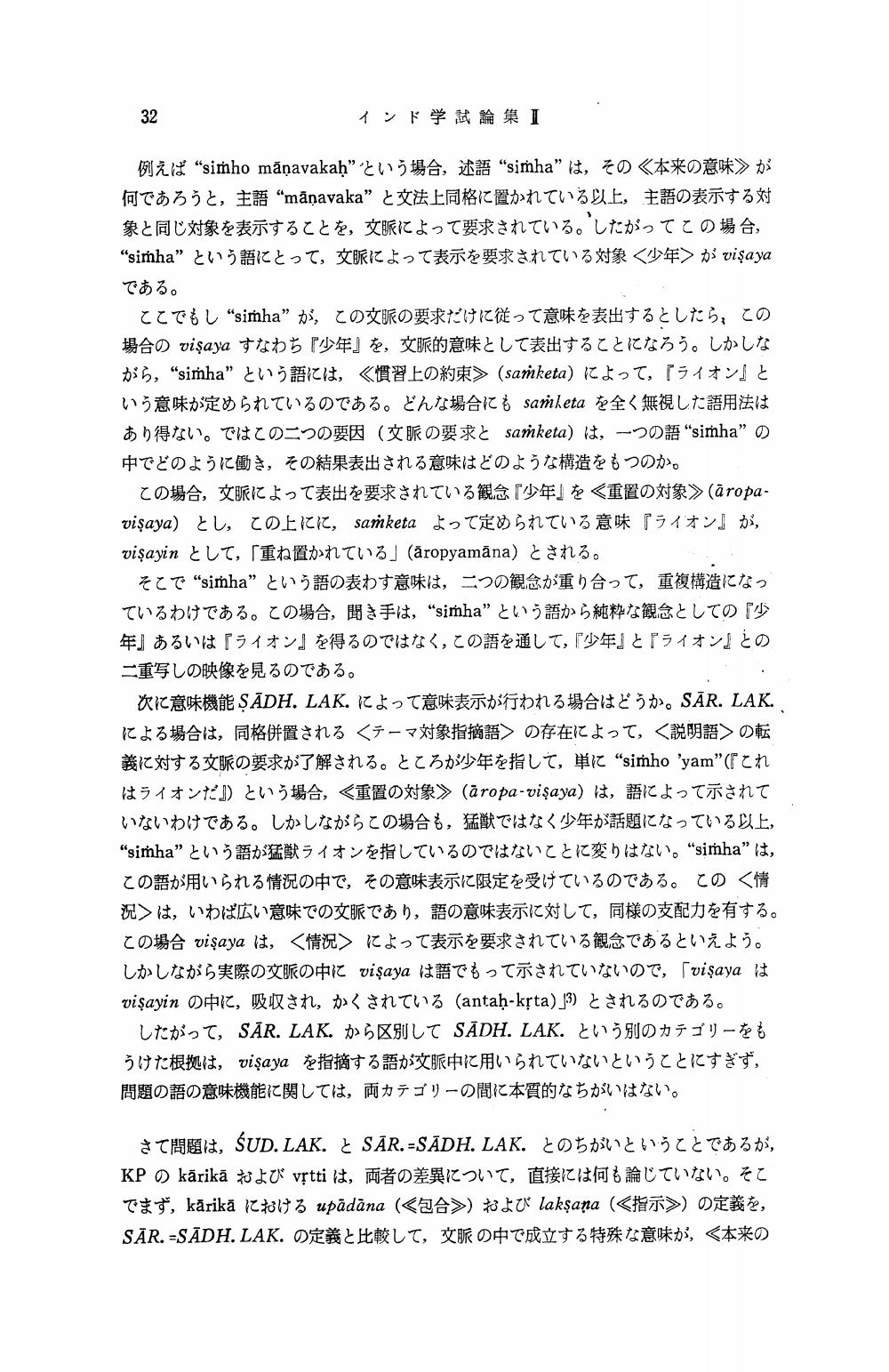Book Title: Laksana Laksyartha Author(s): Publisher: View full book textPage 2
________________ インド 学試論集 1 例えば“sinhomanavakah"という場合,述語“simha" は,そのく本来の意味》が 何であろうと,主語“manavaka"と文法上同格に置かれている以上,主語の表示する対 象と同じ対象を表示することを,文脈によって要求されている。したがって この場合, "sinha" という語にとって、文脈によって表示を要求されている対象 <少年> が visaya である。 ここでもし“simha" が, この文脈の要求だけに従って意味を表出するとしたら、この 場合のvisaya すなわち『少年』を,文脈的意味として表出することになろう。しかしな がら, "sinha" という語には、“慣習上の約束> (sanketa) によって,『ライオン』と いう意味が定められているのである。どんな場合にも samleta を全く無視した語用法は あり得ない。ではこの二つの要因(文脈の要求と samketa) は,一つの語“simha" の 中でどのように働き、その結果表出される意味はどのような構造をもつのか。 この場合,文脈によって表出を要求されている観念『少年』をく重置の対象》(āropavisava) とし,この上にに, samketa よって定められている意味 『ライオン』が, rvisayin として,「重ね置かれている」(aropyamana)とされる。 そこで "simha" という語の表わす意味は、二つの観念が重り合って、重複構造になっ ているわけである。この場合、聞き手は、“simha" という語から純粋な観念としての『少 年』あるいは『ライオン』を得るのではなく、この語を通して、 『少年』と『ライオン』との 二重写しの映像を見るのである。 次に意味機能 SADH. LAK. によって意味表示が行われる場合はどうか。SAR. LAK.. による場合は,同格併置される <テーマ対象指摘語〉の存在によって、く説明語>の転 義に対する文脈の要求が了解される。ところが少年を指して,単に“sinho 'yam"(T これ はライオンだ」)という場合,≪重置の対象》(aropa-visaya) は,語によって示されて いないわけである。しかしながらこの場合も,猛獣ではなく少年が話題になっている以上, simha"という語が猛獣ライオンを指しているのではないことに変りはない。“simha" は, この語が用いられる情況の中で、その意味表示に限定を受けているのである。 この く情 況> は,いわば広い意味での文脈であり,語の意味表示に対して,同様の支配力を有する。 この場合 visaya は,<情況> によって表示を要求されている観念であるといえよう。 しかしながら実際の文脈の中にvisaya は語でもって示されていないので,「visaya は visayin の中に,吸収され,かくされている(antah-krta) 33) とされるのである。 したがって,SAR. LAK. から区別して SADH. LAK. という別のカテゴリーをも うけた根拠は, visaya を指摘する語が文脈中に用いられていないということにすぎず, 問題の語の意味機能に関しては,両カテゴリーの間に本質的なちがいはない。 さて問題は、SUD. LAK. と SAR. -SADH. LAK. とのちがいということであるが, KP の karika および vrtti は,両者の差異について、直接には何も論じていない。そこ でまず, karika における upadana (<包合う) および Laksana (<指示>)の定義を、 SAR. -SADH.LAK. の定義と比較して,文脈の中で成立する特殊な意味が,≪本来のPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24