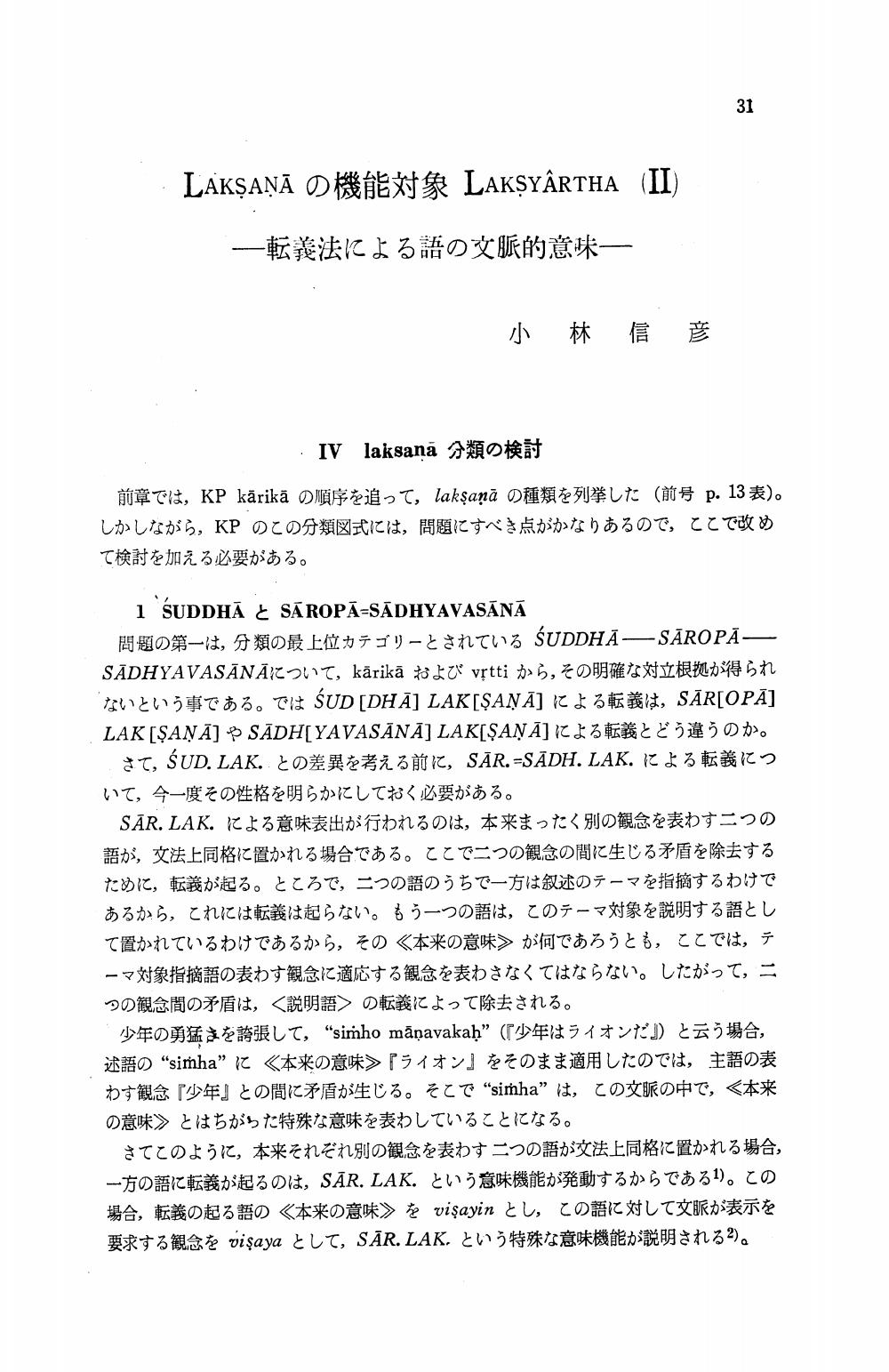Book Title: Laksana Laksyartha Author(s): Publisher: View full book textPage 1
________________ LAKSANA D EXT LAKSYARTHA (II) 一転義法による語の文脈的意味一 小林信彦 IV laksana 分類の検討 前章では, KP karika の順序を追って, laksana の種類を列挙した(前号 p. 13 表)。 しかしながら, KP のこの分類図式には、問題にすべき点がかなりあるので、ここで改め て検討を加える必要がある。 1 SUDDHA C SAROPA=SADHYAVASANA SADHYAVASANAについて, karika および vrtti から, その明確な対立根拠が得られ ないという事である。では SUD [DH A] LAKESAN A] による転義は,SAR[OPA] LAK [SANA] や SADHEYAVASANA] LAK[SAN A] による転義とどう違うのか。 さて, SUD. LAK. との差異を考える前に, SAR. -SADH. LAK. による転義につ いて、今一度その性格を明らかにしておく必要がある。 SAR. LAK. による意味表出が行われるのは、本来まったく別の観念を表わす二つの 語が,文法上同格に置かれる場合である。ここで二つの観念の間に生じる矛盾を除去する ために,転義が起る。 ところで、二つの語のうちで一方は叙述のテーマを指摘するわけで あるから,これには転義は起らない。もう一つの語は、このテーマ対象を説明する語とし て置かれているわけであるから,その《本来の意味が何であろうとも、 ここでは、テ ーマ対象指摘語の表わす観念に適応する観念を表わさなくてはならない。したがって,二 つの観念間の矛盾は,<説明語>の転義によって除去される。 少年の勇猛さを誇張して, "sinho manavakah" (『少年はライオンだ』)と云う場合, 述語の“simha”に本来の意味>『ライオン』をそのまま適用したのでは,主語の表 わす観念『少年』との間に矛盾が生じる。そこで“simha" は、この文脈の中で、本来 の意味》とはちがった特殊な意味を表わしていることになる。 さてこのように、本来それぞれ別の観念を表わす二つの語が文法上同格に置かれる場合, 一方の語に転義が起るのは、SAR. LAK. という意味機能が発動するからである)。この 場合,転義の起る語の “本来の意味》 を visayin とし, この語に対して文脈が表示を 要求する観念を disaya として,SAR. LAK, という特殊な意味機能が説明される)。Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24