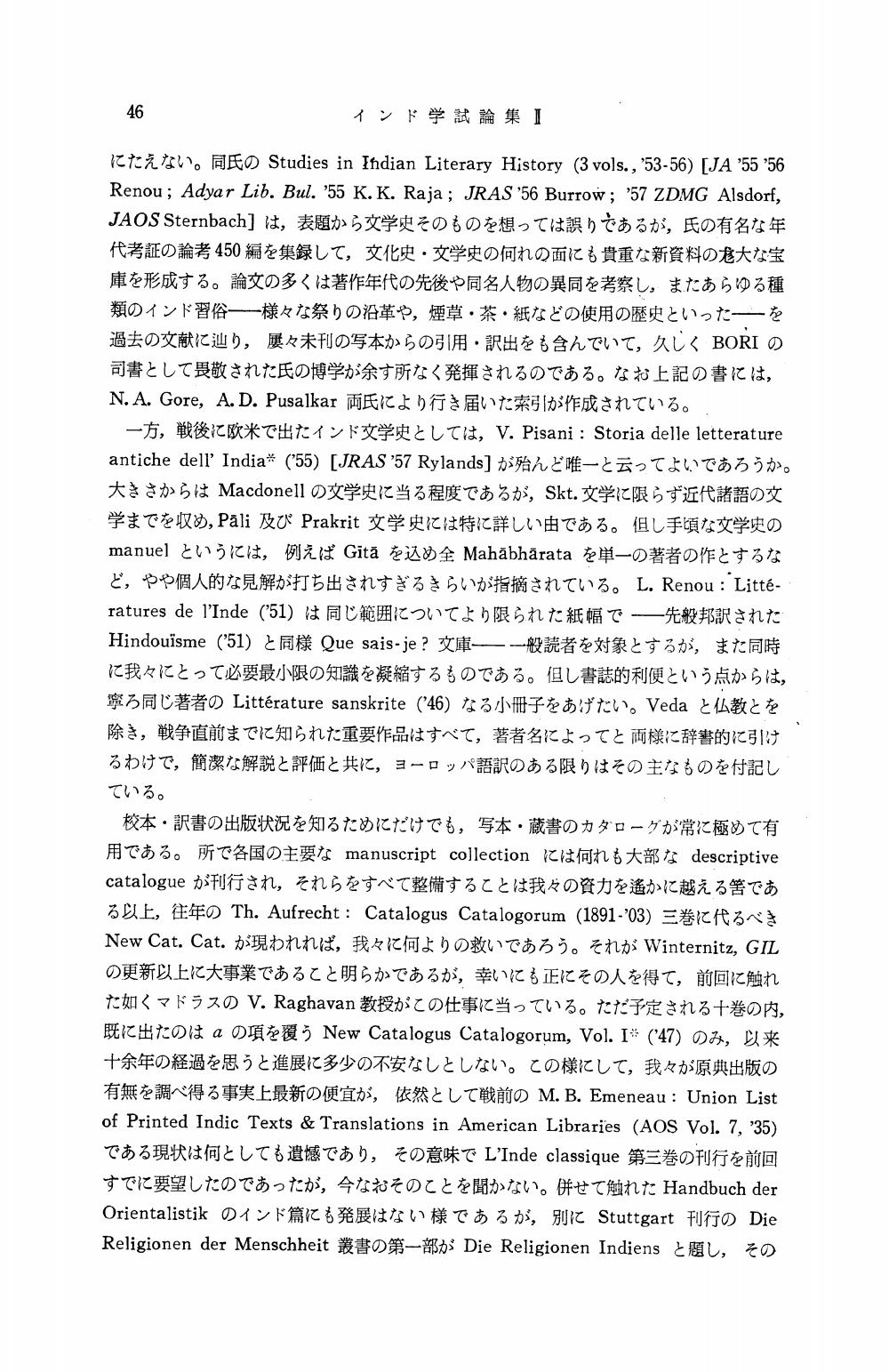Book Title: Laksana Laksyartha
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ 46 インド学試論集1 にたえない。同氏の Studies in Indian Literary History (3 vols., "53-56) [JA '55 56 Renou ; Adyar Lib. Bul. '55 K. K. Raja; JRAS P56 Burrow; '57 ZDMG Alsdorf, JAOS Sternbach] は, 表題から文学史そのものを想っては誤りであるが、氏の有名な年 代考証の論考450 編を集録して、文化史・文学史の何れの面にも貴重な新資料の虎大な宝 庫を形成する。論文の多くは著作年代の先後や同名人物の異同を考察し、またあらゆる種 類のインド習俗――様々な祭りの沿革や,煙草・茶・紙などの使用の歴史といったーを この文献にみり, 屋々未刊の写本からの引用・訳出るも含んでいて、久しくBORI の 司書として畏敬された氏の博学が余す所なく発揮されるのである。なお上記の書には, N. A. Gore, A. D. Pusalkar 両氏により行き届いた索引が作成されている。 一方、戦後に欧米で出たインド文学史としては、V. Pisani: Storia delle letterature antiche dell India* (55) [JRAS '57 Rylands] が殆んど唯一と云ってよいであろうか。 大きさからは Macdonell の文学史に当る程度であるが, Skt.文学に限らず近代諸語の文 学までを収め, Pali 及び Prakrit 文学史には特に詳しい由である。但し手頃な文学 manuel というには, 例えば Gita を込め全 Mahabharata を単一の著者の作とするな どやや個人的な見解が打ち出されすぎるきらいが指摘されている。 L. Renou: Litteratures de l'Inde (51) は 同じ範囲についてより限られた紙幅で一先般邦訳された Hindouisme (251) と同様 Que sais-je? 文庫―― 一般読者を対象とするが,また同時 に我々にとって必要最小限の知識を凝縮するものである。但し書誌的利便という点からは、 密ろ同じ著者の Litterature sanskrite (46) なる小冊子をあげたい。Veda と仏教とを 除き,戦争直前までに知られた重要作品はすべて,著者名によってと両様に辞書的に引け るわけで、簡潔な解説と評価と共に、ヨーロッパ語訳のある限りはその主なものを付記し ている。 校本・訳書の出版状況を知るためにだけでも、写本・蔵書のカタローグが常に極めて有 用である。 所で各国の主要なmanuscript co]lection には何れも大部な descriptive catalogue が刊行され,それらをすべて整備することは我々の資力を遙かに越える筈であ る以上,往年の Th. Aufrecht: Catalogus Catalogorum (1891-'03) 三巻に代るべき New Cat. Cat. が現われれば、我々に何よりの救いであろう。それが Winternitz, GIL の更新以上に大事業であること明らかであるが、幸いにも正にその人を得て,前回に触れ た如くマドラスの V. Raghavan 教授がこの仕事に当っている。ただ予定される十巻の内 既に出たのは a の項を覆う New Catalogus Catalogorum, Vol. I * (47) のみ,以来 十余年の経過を思うと進展に多少の不安なしとしない。この様にして,我々が原典出版の 有無を調べ得る事実上最新の便宜が,依然として戦前の M. B. Emeneau: Union List of Printed Indic Texts & Translations in American Libraries (AOS Vol. 7, '35) である現状は何としても遺憾であり, その意味で L'Inde classique 第三巻の刊行を前回 すでに要望したのであったが,今なおそのことを聞かない。併せて触れた Handbuch der Orientalistik のインド篇にも発展はない様であるが,別にStuttgart 刊行の Die Religionen der Menschheit 叢書の第一部がDie Religionen Indiens と題し,その
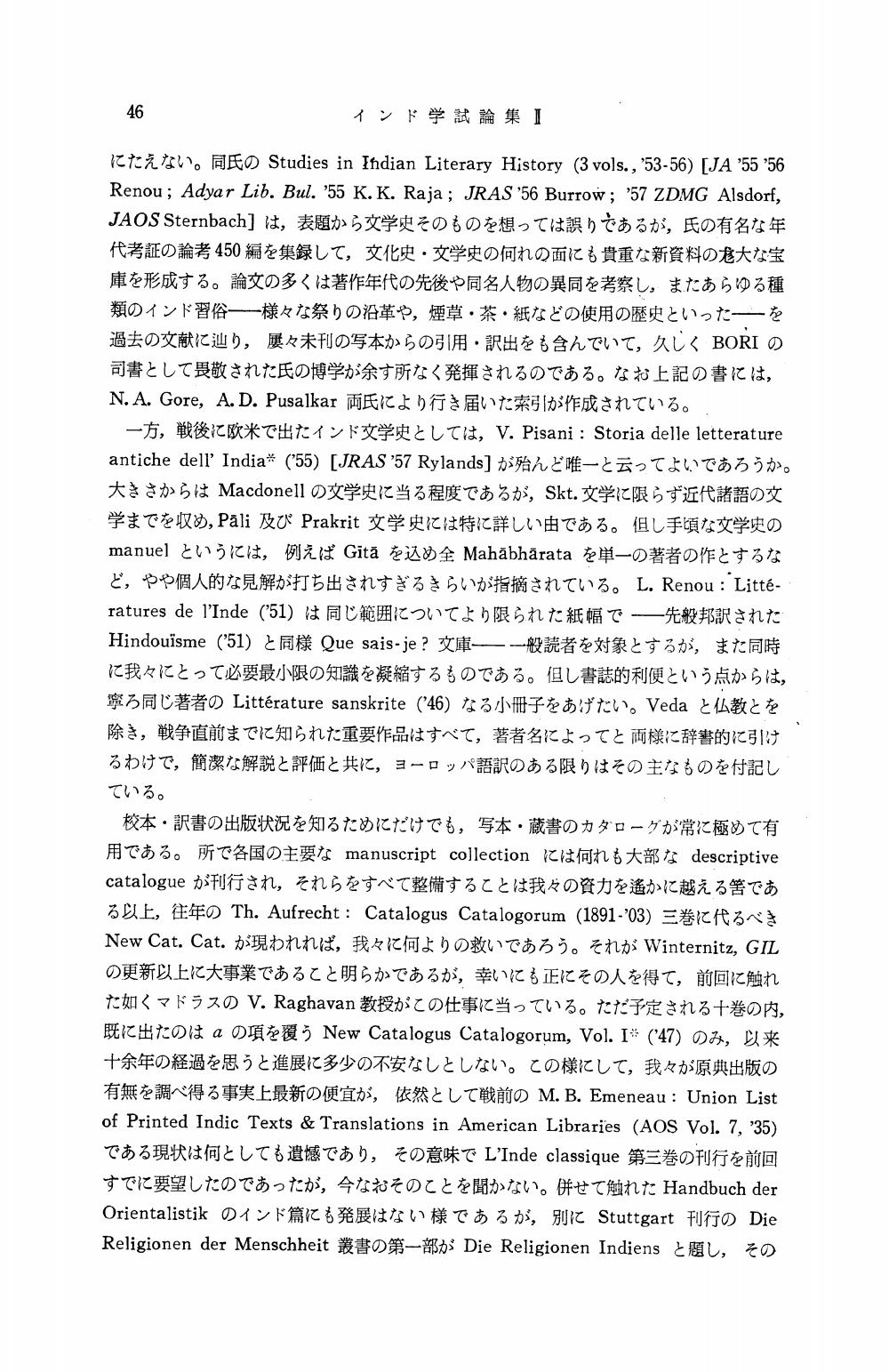
Page Navigation
1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24