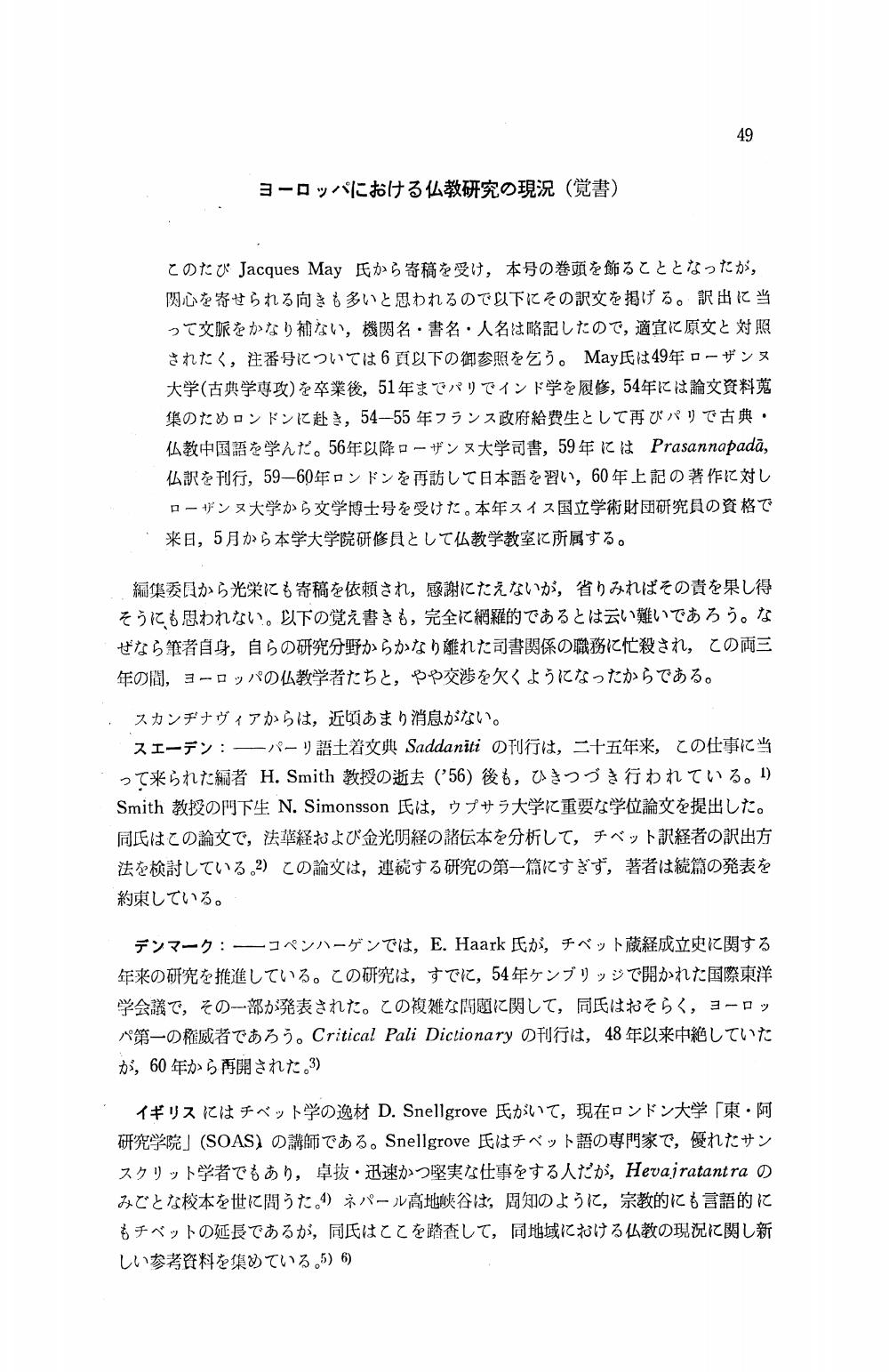Book Title: Laksana Laksyartha
Author(s):
Publisher:
View full book text
________________ ヨーロッパにおける仏教研究の現況(覚書) このたび Jacques May 氏から寄稿を受け,本号の巻頭を飾ることとなったが, 関心を寄せられる向きも多いと思われるので以下にその訳文を掲げる。訳出に当 って文脈をかなり補ない,機関名・書名・人名は略記したので、適宜に原文と対照 されたく、注番号については6頁以下の御参照を乞う。 May氏は49年 ローザンヌ 大学(古典学専攻)を卒業後,51年までパリでインド学を履修,54年には論文資料蒐 集のためロンドンに赴き、54-55年フランス政府給費生として再びパリで古典・ 仏教中国語を学んだ。56年以降ローザンヌ大学司書,59年にはPrasannapada, 仏訳を刊行,59-60年ロンドンを再訪して日本語を習い、60年上記の著作に対し ローザンヌ大学から文学博士号を受けた。本年スイス国立学術財団研究員の資格で 来日,5月から本学大学院研修員として仏教学教室に所属する。 編集委員から光栄にも寄稿を依頼され,感謝にたえないが,省りみればその責を果し得 そうにも思われない。以下の覚え書きも、完全に網羅的であるとは云い難いであろう。な ぜなら筆者自身、自らの研究分野からかなり離れた司書関係の職務に忙殺され、この両三 年の間,ヨーロッパの仏教学者たちと、やや交渉を欠くようになったからである。 スカンザナヴィアからは、近頃あまり消息がない。 ス エーデン: パーリ語土着文典 Saddaniti の刊行は、二十五年来,この仕事に当 って来られた編者 H. Smith 教授の逝去(56) 後も,ひきつづき行われている。1) Smith 教授の門下生 N. Simonsson 氏は,ウプサラ大学に重要な学位論文を提出した。 同氏はこの論文で,法華経および金光明経の諸伝本を分析して,チベット訳経者の訳出方 法を検討している。2) この論文は,連続する研究の第一篇にすぎず,著者は続篇の発表を 約束している。 デンマーク:ーコペンハーゲンでは, E. Haark氏が,チベット蔵経成立史に関する 年来の研究を推進している。この研究は,すでに、54年ケンブリッジで開かれた国際東洋 学会議で,その一部が発表された。この複雑な問題に関して,同氏はおそらく、ヨーロッ パ第一の権威者であろう。Critical Pali Dictionary の刊行は、48年以来中絶していた が、60年から再開された。3) イギリス には チベット学の逸材 D. Snellgrove 氏がいて,現在ロンドン大学「東・阿 研究学院」(SOAS) の講師である。Snellgrove 氏はチベット語の専門家で,優れたサン スクリット学者でもあり、卓抜・迅速かつ堅実な仕事をする人だが、Hevairatantraの みごとな校本を世に問うた。) ネパール高地峡谷は、周知のように、宗教的にも言語的に もチベットの延長であるが,同氏はここを踏査して,同地域における仏教の現況に関し新 しい参考資料を集めている。5) 6)
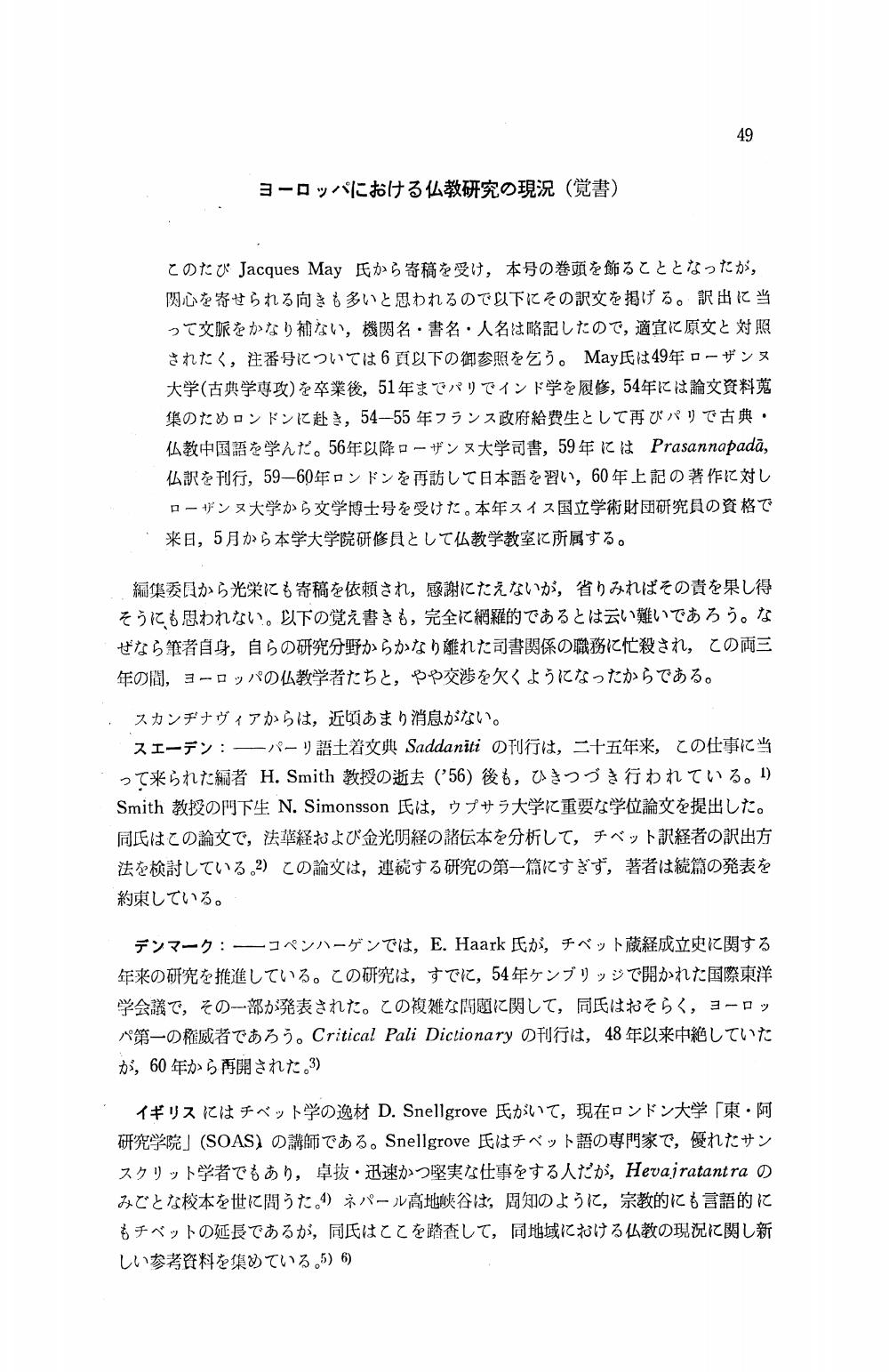
Page Navigation
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24