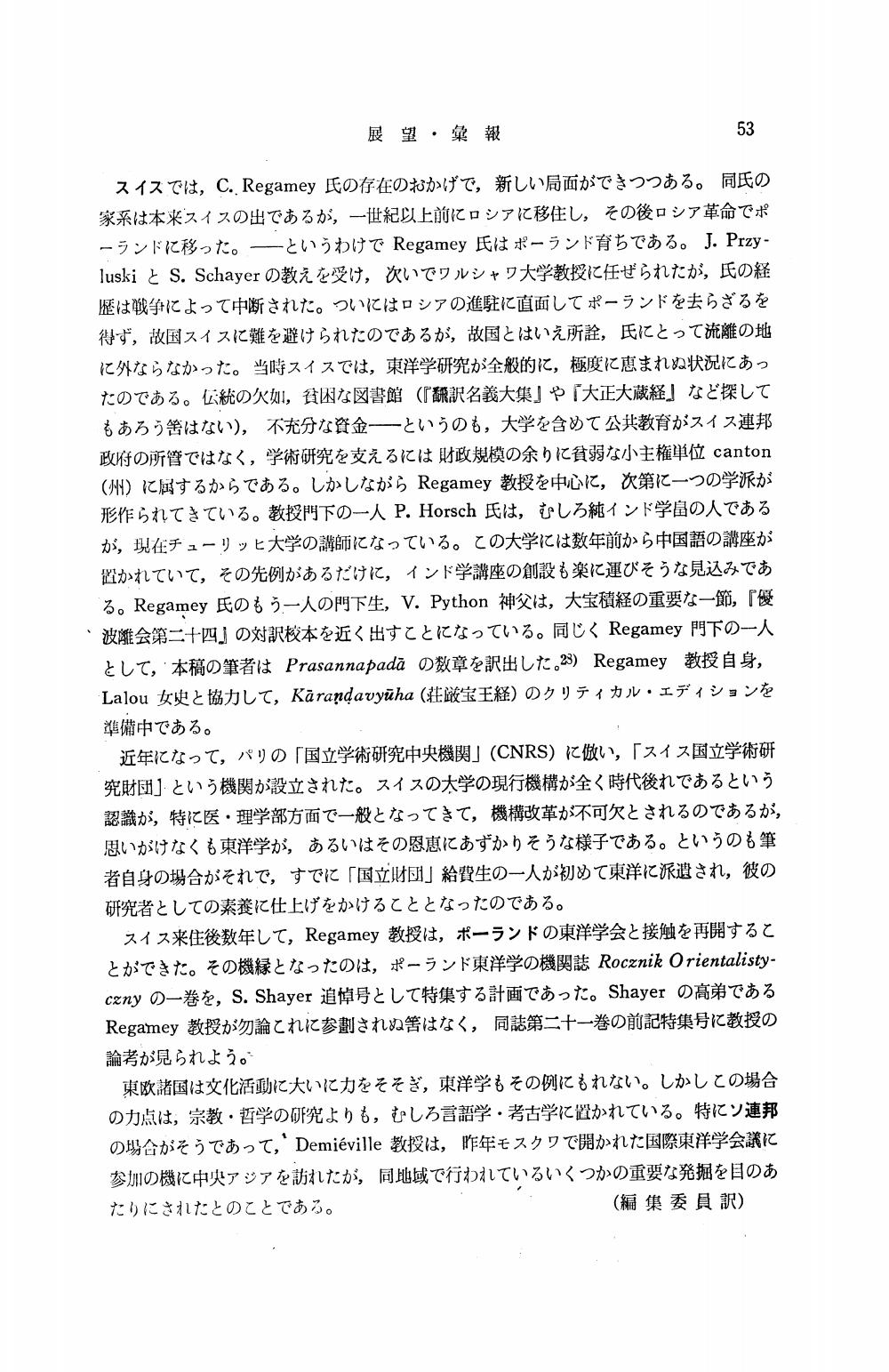________________ 展望・彙報 スイスでは, C. Regamey 氏の存在のおかげで,新しい局面ができつつある。 同氏の 家系は本来スイスの出であるが,一世紀以上前にロシアに移住し, その後ロシア革命でポ ーランドに移った。 というわけで Regamey 氏はポーランド育ちである。 J. Przyluski と S. Schayer の教えを受け,次いでワルシャワ大学教授に任ぜられたが,氏の経 歴は戦争によって中断された。ついにはロシアの進駐に直面してポーランドを去らざるを 得ず、故国スイスに難を避けられたのであるが、故国とはいえ所詮,氏にとって流離の地 に外ならなかった。当時スイスでは,東洋学研究が全般的に、極度に恵まれの状況にあっ たのである。伝統の火,貧困な図書館 (『験訳名義大集」や「大正大蔵経」など探して もあろう筈はない),不充分な資金というのも、大学を含めて公共教育がスイス連邦 政府の所管ではなく、学術研究を支えるには財政規模の余りに貧弱な小主権単位 canton (州)に屈するからである。しかしながら Regamey 教授を中心に,次第に一つの学派が 形作られてきている。教授門下の一人 P. Horsch 氏は、むしろ純インド学日の人である が,現在チューリッヒ大学の講師になっている。 この大学には数年前から中国語の講座が 置かれていて、その先例があるだけに,インド学講座の創設も楽に運びそうな見込みであ る。Regamey 氏のもう一人の門下生, V. Python 神父は,大宝積経の重要な一節,『優 波離会第二十四」の対訳校本を近く出すことになっている。同じく Regamey 門下の一人 として,本稿の筆者は Prasannapada の教章を訳出した。23) Regamey 教授自身, Lalou 女史と協力して, Karandavyaha (荘厳宝王経)のクリティカル・エディションを 準備中である。 近年になって、パリの「国立学術研究中央機関」(CNRS) に倣い,「スイス国立学術研 究財団」という機関が設立された。 スイスの大学の現行機構が全く時代後れであるという 認識が,特に医・理学部方面で一般となってきて,機構改革が不可欠とされるのであるが, 思いがけなくも東洋学が,あるいはその恩恵にあずかりそうな様子である。というのも筆 者自身の場合がそれで、すでに「国立財団」給費生の一人が初めて東洋に派遣され、彼の 研究者としての素養に仕上げをかけることとなったのである。 スイス来住後数年して, Regamey 教授は,ボーランドの東洋学会と接触を再開するこ とができた。その機縁となったのは、ポーランド東洋学の機関誌 Rocznik Orientalistycany の一巻を, S. Shayer 追悼号として特集する計画であった。Shayer の高弟である Regamey 教授が勿論これに参劃されぬ筈はなく、同誌第二十一巻の前記特集号に教授の 論考が見られよう。 東欧諸国は文化活動に大いに力をそそぎ、東洋学もその例にもれない。しかしこの場合 の力点は、宗教・哲学の研究よりも,むしろ言語学・考古学に置かれている。特にソ連邦 の場合がそうであって, Demieville 教授は,昨年モスクワで開かれた国際東洋学会議に 参加の機に中央アジアを訪れたが,同地域で行われているいくつかの重要な発掘を目のあ たりにされたとのことである。 (編集委員訳)