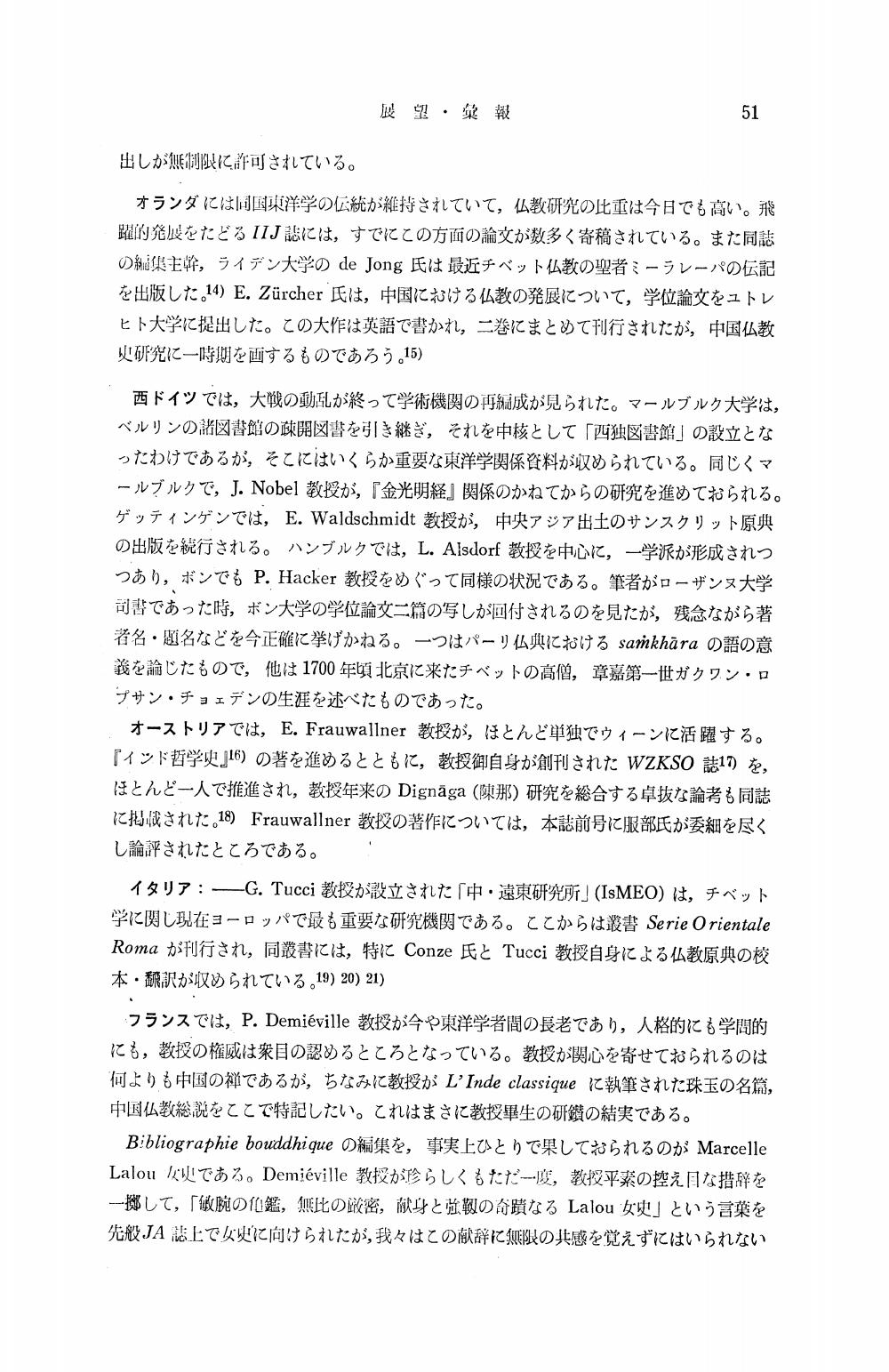________________ 展望彙報 出しが無制限に許可されている。 オランダには同国東洋学の伝統が維持されていて、仏教研究の比重は今日でも高い。飛 躍的発展をたどるIIJ誌には、すでにこの方面の論文が数多く寄稿されている。また同誌 の集主幹, ライデン大学の de Jong 氏は 最近チベット仏教の聖者ミーラレーパの伝記 を出版した。14) E. Zurcher 氏は、中国における仏教の発展について,学位論文をユトレ ヒト大学に提出した。この大作は英語で書かれ、二巻にまとめて刊行されたが,中国仏教 史研究に一時期を画するものであろう。15) 西ドイツでは、大戦の動乱が終って学術機関の再編成が見られた。マールブルク大学は, ベルリンの諸図書館の疎開図書を引き継ぎ,それを中核として「西独図書館」の設立とな ったわけであるが,そこにはいくらか重要な東洋学関係資料が収められている。同じくマ ールブルクで, J. Nobel 教授が,『金光明経』関係のかねてからの研究を進めておられる。 ゲッティンゲンでは, E. Waldschmidt 教授が, 中央アジア出土のサンスクリット原典 の出版を続行される。 ハンブルクでは, L. Alsdorf 教授を中心に,一学派が形成されつ つあり,ボンでも P. Hacker 教授をめぐって同様の状況である。筆者がローザンヌ大学 司書であった時,ボン大学の学位論文二篇の写しが回付されるのを見たが,残念ながら著 者名・題名などを今正確に挙げかねる。一つはパーリ仏典における samkhara の語の意 義を論じたもので、他は1700年頃北京に来たチベットの高僧,章嘉第一世ガクワン・ロ プサン・チョェデンの生涯を述べたものであった。 オーストリアでは, E. Frauwallner 教授が,ほとんど単独でウィーンに活躍する。 『インド哲学史』16)の著を進めるとともに,教授御自身が創刊された WZKSO 誌17) を、 ほとんど一人で推進され、教授年来のDignaga (F形) 研究を総合する卓抜な論考も同誌 に掲載された。18) Frauwallner 教授の著作については,本誌前号に服部氏が委細を尽く し論評されたところである。 イタリア: G. Tucci 教授が設立された「中・遠東研究所」(ISMEO) は,チベット 学に関し現在ヨーロッパで最も重要な研究機関である。ここからは叢書 Serie Orientale Romaが刊行され、同叢書には、特に Conze 氏と Tucci 教授自身による仏教原典の校 本・飜訳が収められている。19) 20) 21) フランスでは, P. Demieville 教授が今や東洋学者間の長老であり、人格的にも学問的 にも,教授の権威は衆目の認めるところとなっている。教授が関心を寄せておられるのは 何よりも中国の神であるが、ちなみに教授が L'Inde classique に執筆された珠玉の名篇, 中国仏教総説をここで特記したい。これはまさに教授畢生の研鑽の結実である。 Bibliographie bouddhi que の編集を,事実上ひとりで果しておられるのが Marcelle Lalou反である。Demiéville 教授が珍らしくもただ一度, 教授平素の控え目な措辞を 一概して,「敏腕の低鑑,無比の厳密,献身と強靭の奇蹟なる Lalou 女史」という言葉を 先般JA誌上で女史に向けられたが、我々はこの献辞に無限の共感を覚えずにはいられない