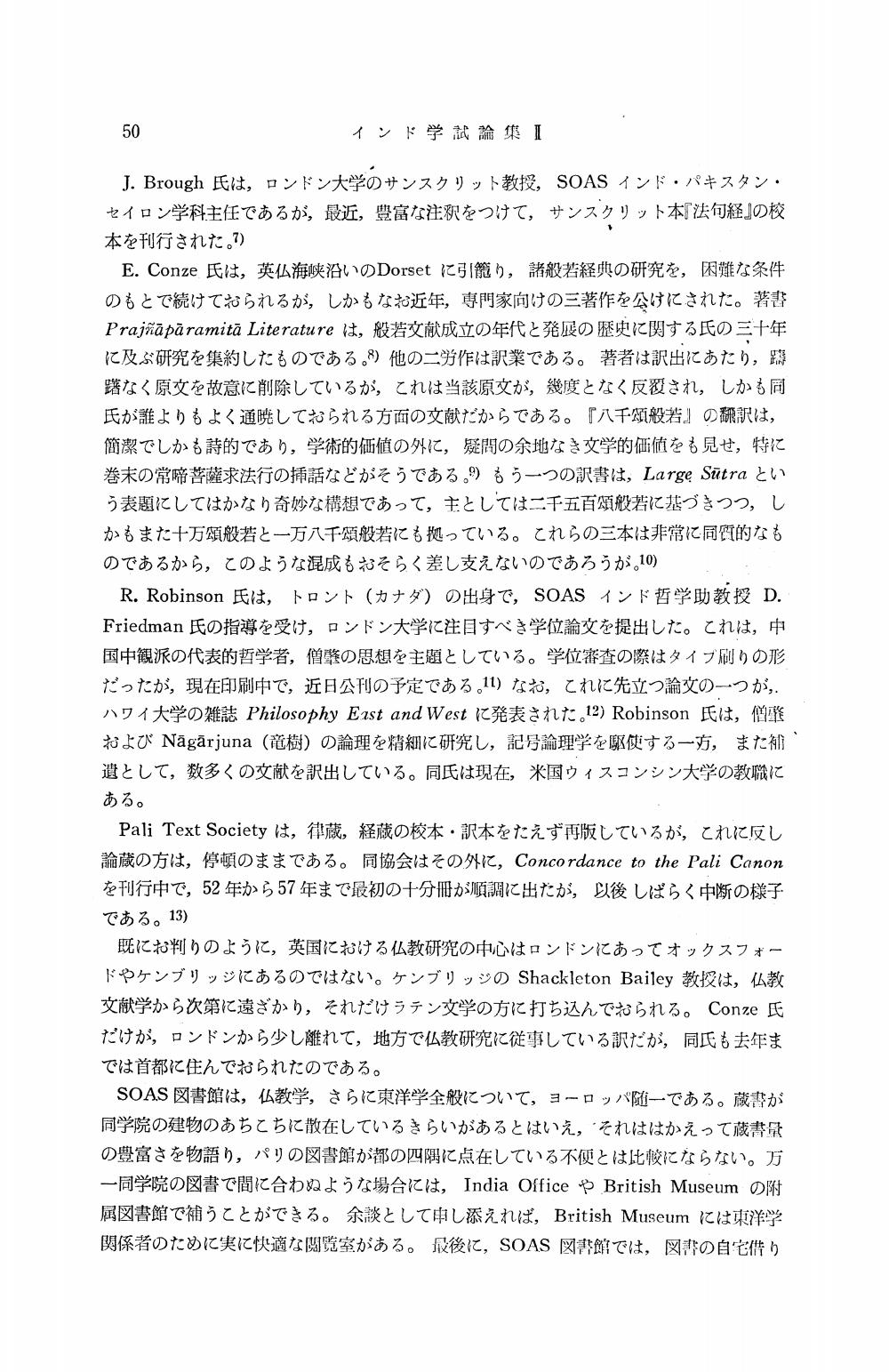________________ 50 インド学試論集II J. Brough 氏は、ロンドン大学のサンスクリット教授,SOAS インド・パキスタン・ セイロン学科主任であるが,最近,豊富な注釈をつけて, サンスクリット本「法句経』の校 本を刊行された。) E. Conze 氏は英仏海峡沿いのDorset に引籠り, 諸般若経典の研究を、困難な条件 のもとで続けておられるが,しかもなお近年,専門家向けの三著作を公けにされた。著書 Prajaparamita Literature は、般若文献成立の年代と発展の歴史に関する氏の三十年 に及ぶ研究を集約したものである。) 他の二労作は訳業である。 著者は訳出にあたり, 躇なく原文を故意に削除しているが,これは当該原文が,幾度となく反覆され,しかも同 氏が誰よりもよく通暁しておられる方面の文献だからである。『八千頃般若』の翻訳は、 簡潔でしかも詩的であり、学術的価値の外に、疑問の余地なき文学的価値をも見せ,特に 巻末の常密菩薩求法行の挿話などがそうである。)もう一つの訳書は, Large Satra とい う表題にしてはかなり奇妙な構想であって,主としては二千五百頃般若に基づきつつ,し かもまた十万頌般若と一万八千頌般若にも拠っている。これらの三本は非常に同質的なも のであるから,このような混成もおそらく差し支えないのであろうが。10) R. Robinson 氏は, トロント(カナダ)の出身で, SOAS インド哲学助教授 D. Friedman氏の指導を受け, ロンドン大学に注目すべき学位論文を提出した。これは,中 国中観派の代表的哲学者,僧聲の思想を主題としている。学位審査の際はタイブ刷りの形 だったが,現在印刷中で,近日公刊の予定である。11) なお,これに先立つ論文の一つが,. ハワイ大学の雑誌 Philosophy East and Westに発表された。12) Robinson 氏は,個性 および Nagarjuna (竜樹)の論理を精細に研究し,記号論理学を駆使する一方, また神 遺として,数多くの文献を訳出している。同氏は現在,米国ウィスコンシン大学の教職に ある。 Pali Text Society は,律蔵,経蔵の校本・訳本をたえず再版しているが、これに反し 論蔵の方は,停頓のままである。 同協会はその外に、Concordance to the Pali Canon を刊行中で, 52 年から57 年まで最初の十分冊が順調に出たが, 以後 しばらく中断の様子 である。13) 既にお判りのように,英国における仏教研究の中心はロンドンにあってオックスフォー ドやケンブリッジにあるのではない。ケンブリッジの Shackleton Bailey 教授は、仏教 文献学から次第に遠ざかり,それだけラテン文学の方に打ち込んでおられる。 Conze 氏 だけが、ロンドンから少し離れて、地方で仏教研究に従事している訳だが,同氏も去年ま では首都に住んでおられたのである。 SOAS 図書館は、仏教学,さらに東洋学全般について,ヨーロッパ随一である。蔵書が 同学院の建物のあちこちに散在しているきらいがあるとはいえ,それははかえって蔵書量 の豊富さを物語り, パリの図書館が都の四隅に点在している不便とは比較にならない。万 一同学院の図書で間に合わぬような場合には, India Office や British Museum の附 属図書館で補うことができる。 余談として申し添えれば,British Museum には東洋学 関係者のために実に快適な閲覧室がある。 最後に, SOAS 図書館では,図書の自宅借り