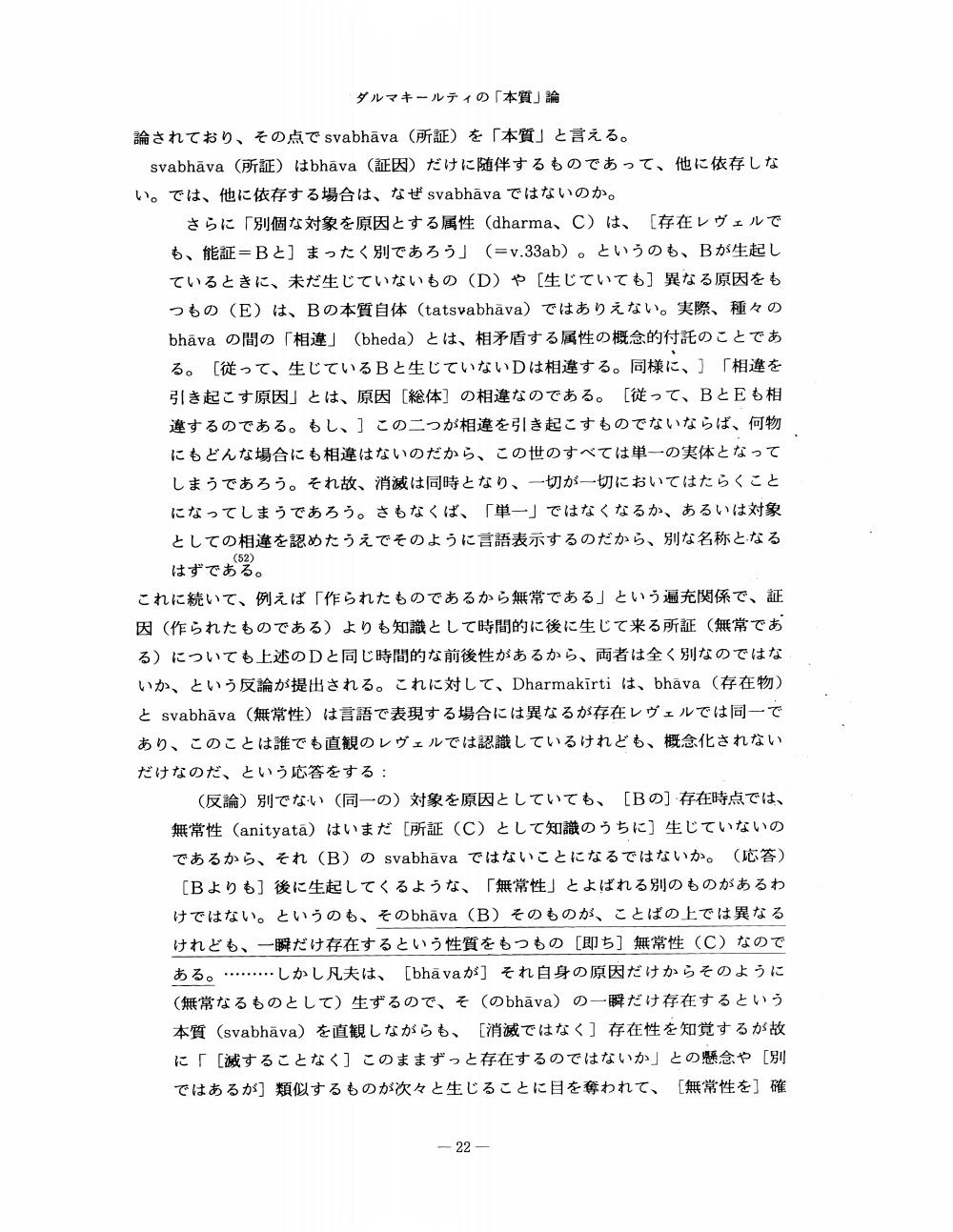________________ ダルマキールティの「本質」論 論されており、その点で svabhava(所証)を「本質」と言える。 svabhava(所証)はbhava (証因)だけに随伴するものであって、他に依存しな い。では、他に依存する場合は、なぜ svabhava ではないのか。 さらに「別個な対象を原因とする属性(dharma、C)は、存在レヴェルで も、能証=Bと] まったく別であろう」(=v.33ab)。というのも、Bが生起し ているときに、未だ生じていないもの(D) や [生じていても] 異なる原因をも つもの(E)は、Bの本質自体 (tatsvabhava)ではありえない。実際、種々の bhava の間の「相違」(bheda)とは、相矛盾する属性の概念的付託のことであ る。[従って、生じているBと生じていないDは相違する。同様に、]「相違を 引き起こす原因」とは、原因[総体]の相違なのである。[従って、BとEも相 違するのである。もし、] この二つが相違を引き起こすものでないならば、何物 にもどんな場合にも相違はないのだから、この世のすべては単一の実体となって しまうであろう。それ故、消滅は同時となり、一切が一切においてはたらくこと になってしまうであろう。さもなくば、「単一」ではなくなるか、あるいは対象 としての相違を認めたうえでそのように言語表示するのだから、別な名称となる はずである。 これに続いて、例えば「作られたものであるから無常である」という遍充関係で、証 因(作られたものである)よりも知識として時間的に後に生じて来る所証(無常であ る)についても上述のDと同じ時間的な前後性があるから、両者は全く別なのではな いか、という反論が提出される。これに対して、Dharmakirti は、bhava(存在物) と svabhava (無常性)は言語で表現する場合には異なるが存在レヴェルでは同一で あり、このことは誰でも直観のレヴェルでは認識しているけれども、概念化されない だけなのだ、という応答をする: (反論)別でない(同一の)対象を原因としていても、[Bの] 存在時点では、 無常性(anityata)はいまだ「所証(C)として知識のうちに生じていないの であるから、それ(B) の svabhava ではないことになるではないか。(応答) [Bよりも]後に生起してくるような、「無常性」とよばれる別のものがあるわ けではない。というのも、そのbhava (B) そのものが、ことばの上では異なる けれども、一瞬だけ存在するという性質をもつもの「即ち] 無常性(C)なので ある。 ......しかし凡夫は、[bhavaが] それ自身の原因だけからそのように (無常なるものとして)生ずるので、そ(のbhava)の一瞬だけ存在するという 本質 (svabhava) を直観しながらも、「消滅ではなく]存在性を知覚するが故 に「[滅することなく」このままずっと存在するのではないか」との懸念や[別 ではあるが」 類似するものが次々と生じることに目を奪われて、「無常性を] 確 -22