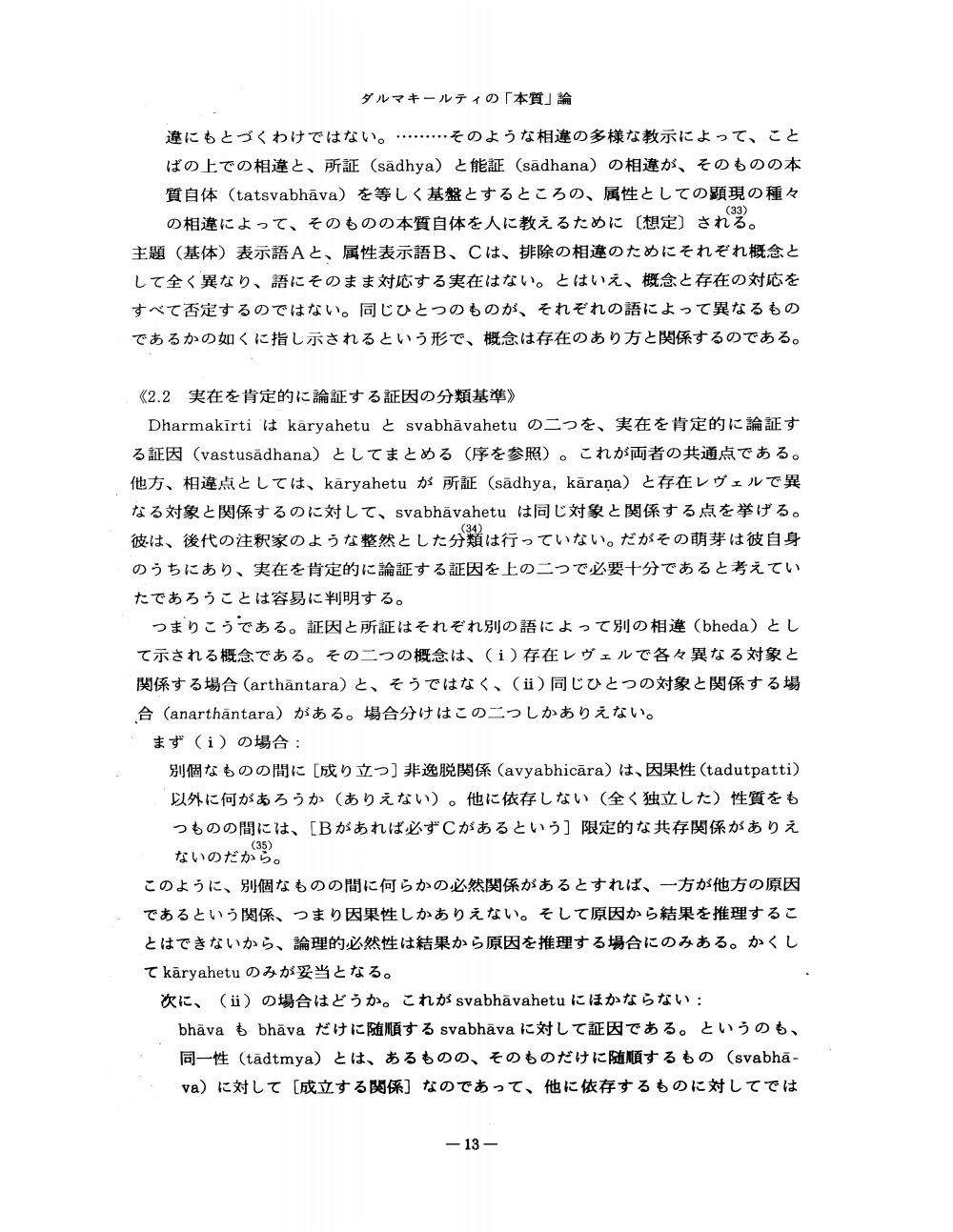________________ ダルマキールティの「本質」論 違にもとづくわけではない。 ......そのような相違の多様な教示によって、こと ばの上での相違と、所証(sadhya)と能証(sadhana)の相違が、そのものの本 質自体(tatsvabhava)を等しく基盤とするところの、属性としての顕現の種々 の相違によって、そのものの本質自体を人に教えるために「想定」される。 主題(基体)表示語Aと、属性表示語B、Cは、排除の相違のためにそれぞれ概念と して全く異なり、語にそのまま対応する実在はない。とはいえ、概念と存在の対応を すべて否定するのではない。同じひとつのものが、それぞれの語によって異なるもの であるかの如くに指し示されるという形で、概念は存在のあり方と関係するのである。 <<2.2 実在を肯定的に論証する証因の分類基準》 Dharmakirti は karyahetu と svabhavahetu の二つを、実在を肯定的に論証す る証因 (vastusādhana)としてまとめる(序を参照)。これが両者の共通点である。 他方、相違点としては、karyahetu が 所証 (sadhya, karana) と存在レヴェルで異 なる対象と関係するのに対して、svabhavahetu は同じ対象と関係する点を挙げる。 彼は、後代の注釈家のような整然とした分類は行っていない。だがその萌芽は彼自身 のうちにあり、実在を肯定的に論証する証因を上の二つで必要十分であると考えてい たであろうことは容易に判明する。 つまりこうである。証因と所証はそれぞれ別の語によって別の相違 (bheda) とし て示される概念である。その二つの概念は、(i)存在レヴェルで各々異なる対象と 関係する場合 (arthantara) と、そうではなく、(i)同じひとつの対象と関係する場 合 (anarthantara)がある。場合分けはこの二つしかありえない。 * まず(i)の場合: 別個なものの間に成り立っ] 非逸脱関係 (avyabhicara) は、因果性 (tadutpatti) 以外に何があろうか(ありえない)。他に依存しない(全く独立した)性質をも つものの間には、[Bがあれば必ずCがあるという]限定的な共存関係がありえ ないのだから。 このように、別個なものの間に何らかの必然関係があるとすれば、一方が他方の原因 であるという関係、つまり因果性しかありえない。そして原因から結果を推理するこ とはできないから、論理的必然性は結果から原因を推理する場合にのみある。かくし て karyahetu のみが妥当となる。 次に、(i)の場合はどうか。これが svabhavahetu にほかならない: bhava も bhava だけに随順する svabhava に対して証因である。というのも、 同一性(tadtmya) とは、あるものの、そのものだけに随順するもの(svabha, va)に対して「成立する関係]なのであって、他に依存するものに対してでは -13