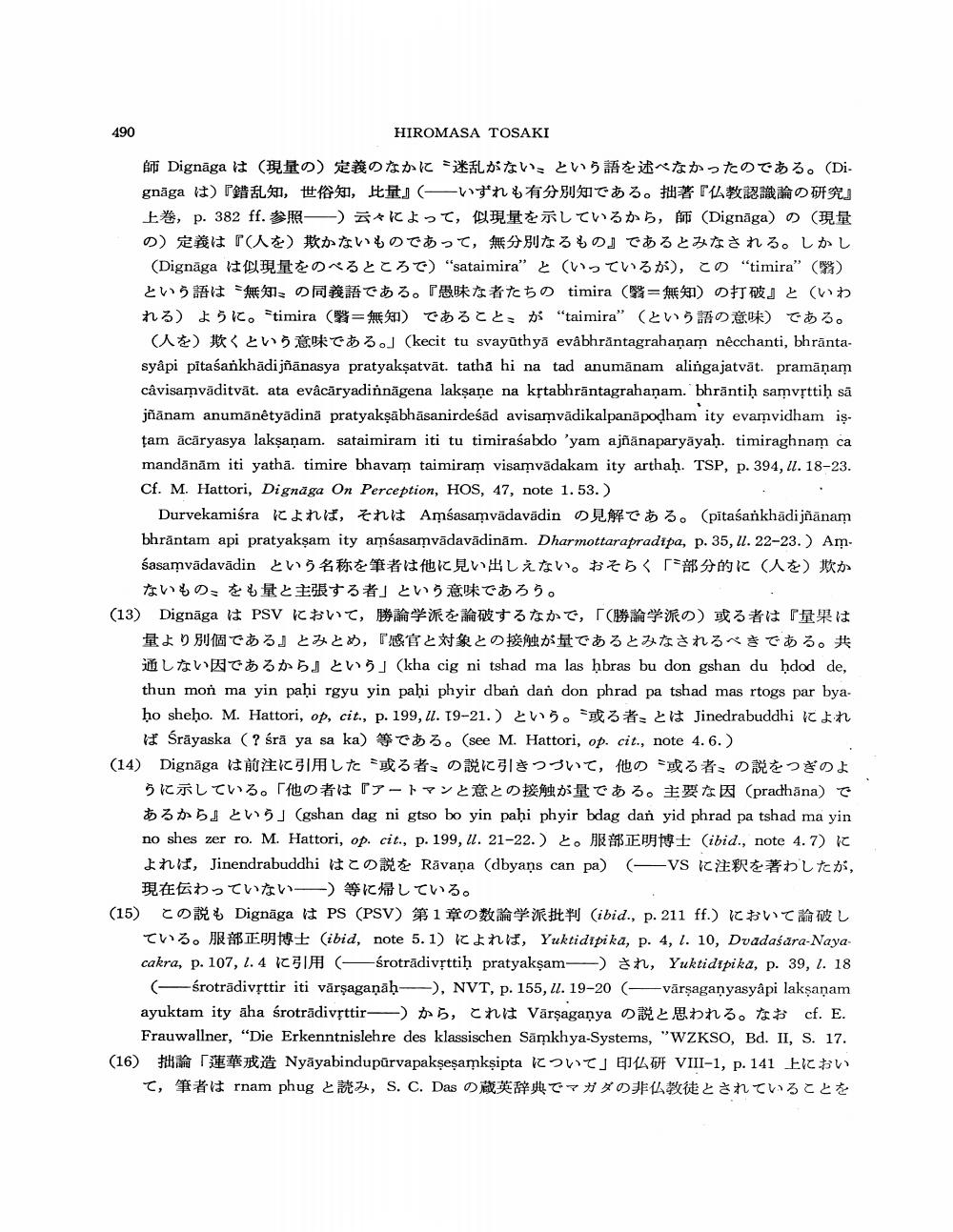________________
490
HIROMASA TOSAKI
師 Dignaga は(現量の)定義のなかに迷乱がない、という語を述べなかったのである。(Dignaga は)『錯乱知,世俗知,比重』( いずれも有分別知である。拙著『仏教認識論の研究』 上巻, p. 382 ff. 参照——)云々によって、似現量を示しているから,師 (Dignaga) の(現量 の)定義は『(人を)欺かないものであって、無分別なるもの』であるとみなされる。しかし (Dignaga は似現量をのべるところで)“sataimira" と(いっているが),この“timira" (影) という語は「無知」の同義語である。『愚味な者たちの timira (嘴=無知)の打破』と(いわ れる)ように。 timira (l=無知)であることが “taimira"(という語の意味)である。
(人を)欺くという意味である。」 (kecit tu svayathyá evabhrantagrahanam nécchanti, bhrantasyâpi pītasankhādijñānasya pratyakşatvāt. tatha hi na tad anumānam alingajatvāt. pramāņam câvisamvāditvāt. ata evâcāryadinnāgena lakṣaṇe na křtabhrāntagrahaņam. bhrāntiḥ samvșttiḥ sā jñānam anumānêtyādina pratyakşābhāsanirdeśad avisamvādikalpanāpodham ity evamvidham istam ācāryasya lakṣaṇam. sataimiram iti tu timiraśabdo 'yam ajñānaparyāyaḥ. timiraghnam ca mandānām iti yathā. timire bhavam taimiram visamvādakam ity arthaḥ. TSP, p. 394, 11. 18-23. Cf. M. Hattori, Dignāga On Perception, HOS, 47, note 1.53.)
Durvekamisra によれば,それは Amsasamvadavadin の見解である。(pitasaikhadijñānam bhrāntam api pratyakşam ity ambasamvādavādinām. Dharmottarapradipa, p. 35, 11. 22-23.) Am. sasamvadavadin という名称を筆者は他に見い出しえない。おそらく「部分的に(人を)吹か
ないものをも量と主張する者」という意味であろう。 (13) Dignaga は PSVにおいて,勝論学派を論破するなかで,「(勝論学派の)或る者は『量果は
量より別個である』とみとめ,『感官と対象との接触が量であるとみなされるべきである。共 通しない因であるから』という」(kha cig ni tshad ma lashbras budongshan du hdod de, thun mon ma yin paḥi rgyu yin pahi phyir dban dan don phrad pa tshad mas rtogs par byaho sheho. M. Hattori, op, cit, p. 199, M. 19-21.)という。或る者とは Jinedrabuddhi によれ
It Śrāyaska (? śrā ya sa ka) 2. (see M. Hattori, op. cit., note 4.6.) (14) Dignaga は前注に引用した「或る者の説に引きつづいて、他の一或る者の説をつぎのよ。 うに示している。「他の者は『アートマンと意との接触が量である。主要な因(pradhana) で
3051 2115] (gshan dag ni gtso bo yin paḥi phyir bdag dan yid phrad pa tshad ma yin no shes zer ro. M. Hattori, op. cit, p. 199, M. 21-22.)と。服部正明博士 (ibid., note 4.7) に よれば, Jinendrabuddhi はこの説を Ravana (dbyans can pa) ( VS に注釈を著わしたが,
現在伝わっていない―)等に帰している。 (15) との説も Dignaga は PS (PSV) 第1章の数論学派批判(ibid., p.211 ff.)において論破し
ている。服部正明博士 (ibid, note 5.1)によれば, Yuktidipika, p. 4, 1. 10, Dradasara-Nayacakra, p. 107, 1.4 CSIN - śrotrādivșttiḥ pratyakşam- ) th, Yukti dipika, p. 39, 1. 18
- śrotrādivpttir iti vārşagaņāḥ- ), NVT, p. 155, 11. 19-20 vārşaganyasyäpi laksanam ayuktam ity aha srotradivrttir )から、これは Varsaganya の説と思われる。なおcf. E.
Frauwallner, "Die Erkenntnislehre des klassischen Sāmkhya-Systems, "WZKSO, Bd. II, S. 17. (16) 拙論「蓮華戒造 Nyayabindupurvapaksesamksipta について」印仏研 VIII-1, p.141 上におい
て、筆者は rnam phug と読み, S. C. Das の蔵英辞典でマガダの非仏教徒とされていることを