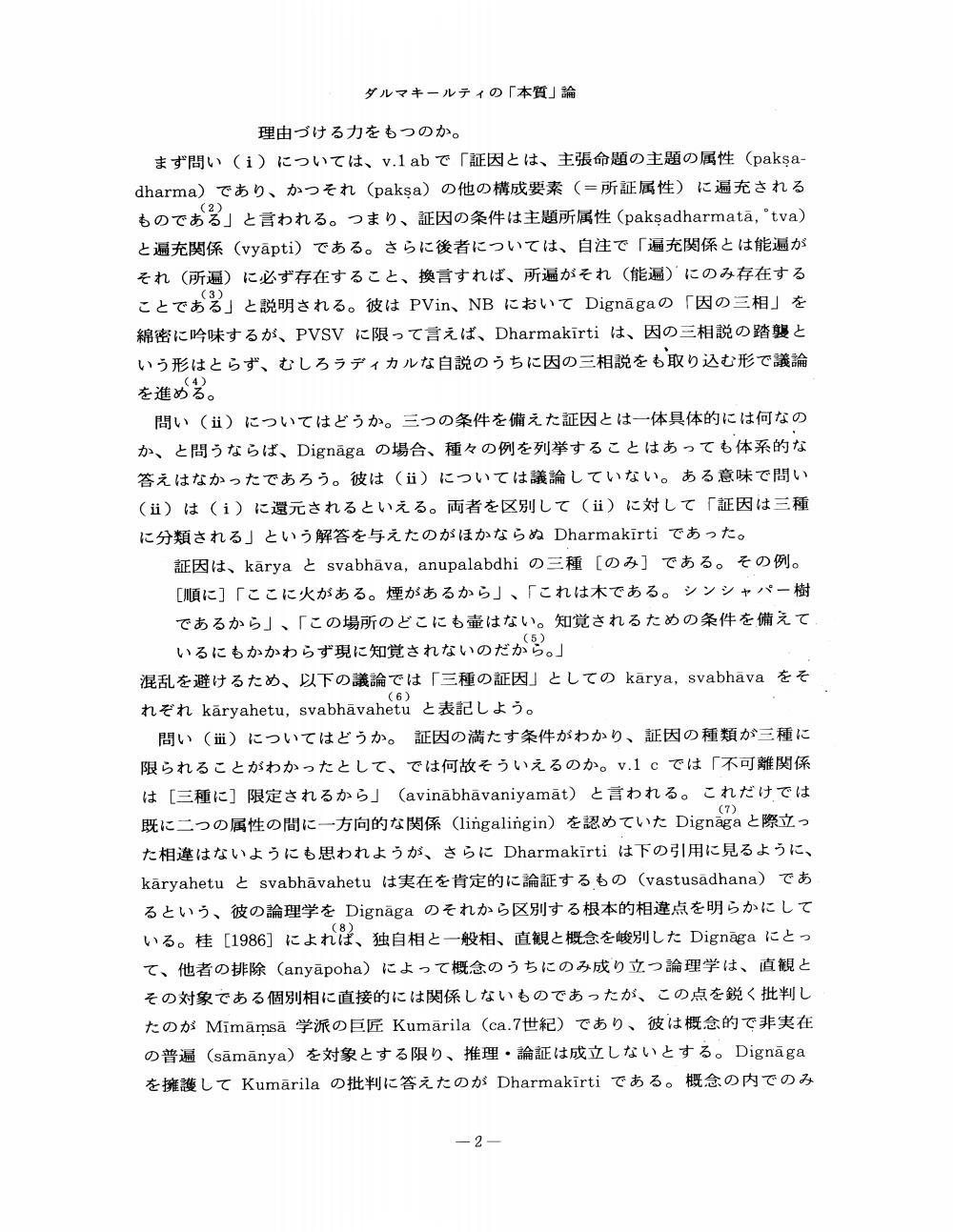________________ ダルマキールティの「本質」論 ( 2 ) 理由づける力をもつのか。 まず問い(i)については、v.1 ab で「証因とは、主張命題の主題の属性(paksadharma)であり、かつそれ(paksa)の他の構成要素(=所証属性)に遍充される ものである」と言われる。つまり、証因の条件は主題所属性 (paksadharmata, tva) と遍充関係 (vyapti) である。さらに後者については、自注で「遍充関係とは能遍が それ(所遍)に必ず存在すること、換言すれば、所遍がそれ(能遍)にのみ存在する ことである」と説明される。彼は PVin, NB において Dignagaの「因の三相」を 綿密に吟味するが、PVSV に限って言えば、Dharmakirti は、因の三相説の踏襲と いう形はとらず、むしろラディカルな自説のうちに因の三相説をも取り込む形で議論 を進める。 問い (ii)についてはどうか。三つの条件を備えた証因とは一体具体的には何なの か、と問うならば、Dignaga の場合、種々の例を列挙することはあっても体系的な 答えはなかったであろう。彼は(i) については議論していない。ある意味で問い (i) は(i) に還元されるといえる。両者を区別して(i)に対して「証因は三種 に分類される」という解答を与えたのがほかならぬ Dharmakirti であった。 証因は、karya と svabhava, anupalabdhi の三種 [のみ]である。その例。 [順に]「ここに火がある。煙があるから」、「これは木である。シンシャパー樹 であるから」、「この場所のどこにも壷はない。知覚されるための条件を備えて いるにもかかわらず現に知覚されないのだから。」 混乱を避けるため、以下の議論では「三種の証因」としての karya, svabhava をそ れぞれ karyahetu, svabhavahetu と表記しよう。 問い (ii)についてはどうか。 証因の満たす条件がわかり、証因の種類が三種に 限られることがわかったとして、では何故そういえるのか。v.1 c では「不可離関係 は「三種に] 限定されるから」(avinabhavaniyamat) と言われる。これだけでは 既に二つの属性の間に一方向的な関係 (lingalingin)を認めていた Dignagaと際立っ た相違はないようにも思われようが、さらに Dharmakirti は下の引用に見るように、 karyahetu と svabhavahetu は実在を肯定的に論証するもの (vastusadhana)であ るという、彼の論理学を Dignaga のそれから区別する根本的相違点を明らかにして いる。桂[1986] によれば、独自相と一般相、直観と概念を峻別した Dignaga にとっ て、他者の排除 (anyapoha)によって概念のうちにのみ成り立っ論理学は、直観と その対象である個別相に直接的には関係しないものであったが、この点を鋭く批判し たのが Mimamsa 学派の巨匠 Kumarila (ca.7世紀)であり、彼は概念的で非実在 の普遍(samanya) を対象とする限り、推理・論証は成立しないとする。Dignaga を擁護して Kumarila の批判に答えたのが Dharmakirti である。概念の内でのみ (6) (7) -2