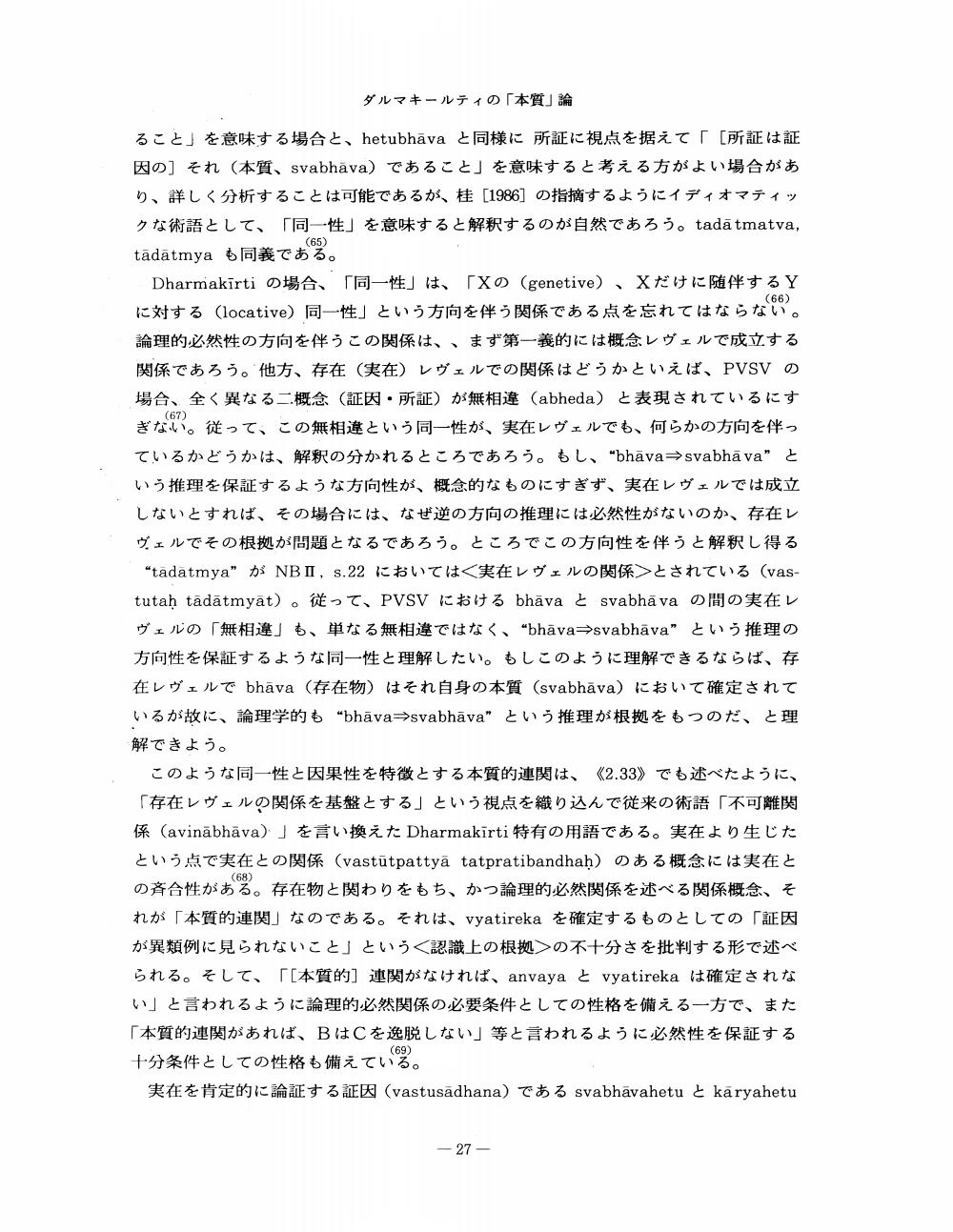________________ ダルマキールティの「本質」論 (65) (66) (67) ること」を意味する場合と、hetubhava と同様に 所証に視点を据えて「[所証は証 因の]それ(本質、syabhava)であること」を意味すると考える方がよい場合があ り、詳しく分析することは可能であるが、桂[1986]の指摘するようにイディオマティッ クな術語として、「同一性」を意味すると解釈するのが自然であろう。tadátmatva, tadatmya も同義である。 Dharmakirti の場合、「同一性」は、「Xの(genetive)、Xだけに随伴するY に対する(locative)同一性」という方向を伴う関係である点を忘れてはならない。 論理的必然性の方向を伴うこの関係は、、まず第一義的には概念レヴェルで成立する 関係であろう。他方、存在(実在)レヴェルでの関係はどうかといえば、PVSV の 場合、全く異なる二概念(証因・所証)が無相違(abheda)と表現されているにす ぎない。従って、この無相違という同一性が、実在レヴェルでも、何らかの方向を伴っ ているかどうかは、解釈の分かれるところであろう。もし、“bhava⇒ svabhava" と いう推理を保証するような方向性が、概念的なものにすぎず、実在レヴェルでは成立 しないとすれば、その場合には、なぜ逆の方向の推理には必然性がないのか、存在レ ヴェルでその根拠が問題となるであろう。ところでこの方向性を伴うと解釈し得る "tadatmya" が NB II , S.22 においては<実在レヴェルの関係>とされている (vastutah tadátmyat)。従って、PVSV における bhava と svabhava の間の実在レ ヴェルの「無相違」も、単なる無相違ではなく、“bhava→svabhava” という推理の 方向性を保証するような同一性と理解したい。もしこのように理解できるならば、存 在レヴェルで bhava(存在物)はそれ自身の本質 (svabhava)において確定されて いるが故に、論理学的も“bhava→svabhava” という推理が根拠をもつのだ、と理 解できよう。 このような同一性と因果性を特徴とする本質的連関は、《2.33》でも述べたように、 「存在レヴェルの関係を基盤とする」という視点を織り込んで従来の術語「不可離関 係 (avinabháva)」を言い換えた Dharmakirti特有の用語である。実在より生じた という点で実在との関係 (vastutpattya tatpratibandhah)のある概念には実在と の斉合性がある。存在物と関わりをもち、かつ論理的必然関係を述べる関係概念、そ れが「本質的連関」なのである。それは、vyatireka を確定するものとしての「証因 が異類例に見られないこと」というく認識上の根拠>の不十分さを批判する形で述べ られる。そして、「[本質的]連関がなければ、anvaya と vyatireka は確定されな い」と言われるように論理的必然関係の必要条件としての性格を備える一方で、また 「本質的連関があれば、BはCを逸脱しない」等と言われるように必然性を保証する 十分条件としての性格も備えている。 実在を肯定的に論証する証因 (vastusadhana) である svabhavahetu と karyahetu (68) -27