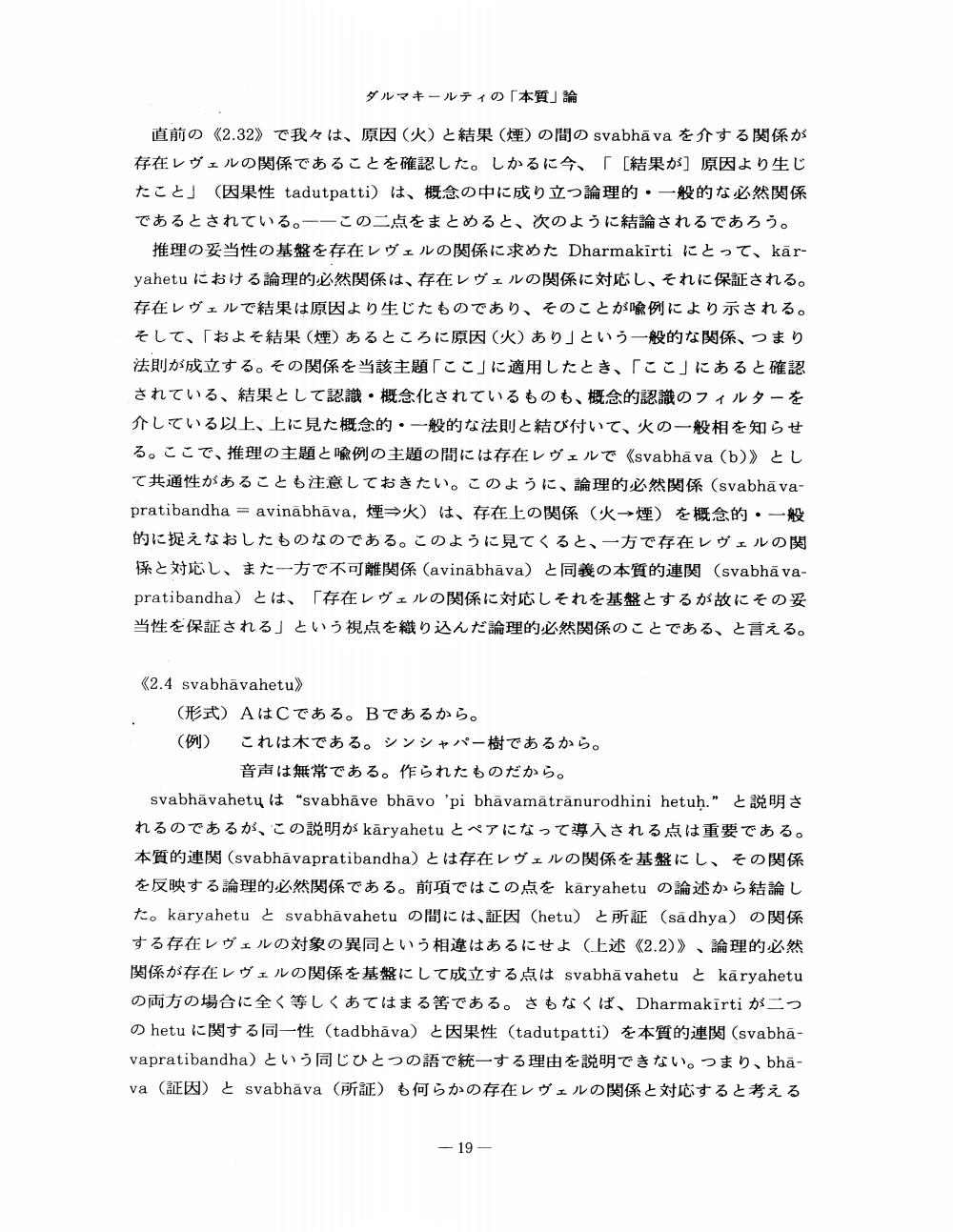________________ ダルマキールティの「本質」論 直前の《2.32》 で我々は、原因(火) と結果(煙)の間の svabhava を介する関係が 存在レヴェルの関係であることを確認した。しかるに今、「[結果が] 原因より生じ たこと」(因果性 tadutpatti)は、概念の中に成り立つ論理的・一般的な必然関係 であるとされている。――この二点をまとめると、次のように結論されるであろう。 推理の妥当性の基盤を存在レヴェルの関係に求めた Dharmakirti にとって、karyahetu における論理的必然関係は、存在レヴェルの関係に対応し、それに保証される。 存在レヴェルで結果は原因より生じたものであり、そのことが喩例により示される。 そして、「およそ結果(煙) あるところに原因(火) あり」という一般的な関係、つまり 法則が成立する。その関係を当該主題「ここ」に適用したとき、「ここ」にあると確認 されている、結果として認識・概念化されているものも、概念的認識のフィルターを 介している以上、上に見た概念的・一般的な法則と結び付いて、火の一般相を知らせ る。ここで、推理の主題と喩例の主題の間には存在レヴェルで《svabhava (b)》とし て共通性があることも注意しておきたい。このように、論理的必然関係 (svabhavapratibandha = avinabhava, 煙⇒火)は、存在上の関係(火→煙)を概念的・一般 的に捉えなおしたものなのである。このように見てくると、一方で存在レヴェルの関 係と対応し、また一方で不可離関係 (avinabhava)と同義の本質的連関 (svabhávapratibandha)とは、「存在レヴェルの関係に対応しそれを基盤とするが故にその妥 当性を保証される」という視点を織り込んだ論理的必然関係のことである、と言える。 (2.4 svabhavahetu) (形式)AはCである。Bであるから。 (例) これは木である。シンシャパー樹であるから。 音声は無常である。作られたものだから。 svabhavahetu la "svabhave bhavo 'pi bhavamatranurodhini hetuh." C U れるのであるが、この説明が karyahetu とペアになって導入される点は重要である。 本質的連関 (svabhavapratibandha) とは存在レヴェルの関係を基盤にし、その関係 を反映する論理的必然関係である。前項ではこの点を karyahetu の論述から結論し た。 karyahetu と svabhavahetu の間には、証因 (hetu)と所証 (sadhya) の関係 する存在レヴェルの対象の異同という相違はあるにせよ(上述《2.2)》、論理的必然 関係が存在レヴェルの関係を基盤にして成立する点は svabhavahetu と karyahetu の両方の場合に全く等しくあてはまる筈である。さもなくば、Dharmakirti が二っ の hetu に関する同一性 (tadbhava) と因果性 (tadutpatti) を本質的連関 (svabhavapratibandha) という同じひとつの語で統一する理由を説明できない。つまり、bhava(証因)と svabhava(所証)も何らかの存在レヴェルの関係と対応すると考える -19